


�@
�@
�@
����26�i2014�j�N�x
�w�����Ńw���X�`�F�b�N�L�����y�[�����J��
�@
�@�v���č���w�����ł́A����T���W���i�j�P�P���R�O���`�P�S���̊ԂɁA�w�����̐H���Ɩ����ϑ�
���Ă��銔����Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂āA�w���X�`�F�b�N�L�����y�[�����J�Â��܂����B
�@�L�����y�[���ɂ͗�����T�O�����Q�����A�������̑���A���̌��N�x����ɉ����A�����_�o�E
�������_�o�𑪒肷��@��𗘗p���ăX�g���X�x�`�F�b�N���܂����B
�@���茋�ʂ܂��āA�Q���������������́A�H���ƌ��N�ɂ��ẴA�h�o�C�X�������[���Ă�
�܂����B
 |
 |
 |
�w���X�`�F�b�N�L�����y�[���̗l�q
�@
�@
����26�i2014�j�N�x
���̂Â��苳��Z���^�[�J�������J��
�@
�@�v���č���́A����S���Q�R���i���j�Ɂu���̂Â��苳��Z���^�[�v�J�������s���܂����B
�@���Z���^�[�́A�V���������@�B�H��H��C�@�B�������y�ѓd�C�E������������S�ʉ��C����
���̂ŁA�w���̈��S�����ŗD��ɁA�菑���}�̊��������n���f�U�C�����y�тR�c�v�����^�E
�v���O��������̃t���C�X���������`���K������z�u���܂����B
�@�J�����ł́A��c�F�Z���A�ΊۖΕv�e�N�m�l�b�g�v���ĉ�̈��A�A�a�u�����厖�̃Z
���^�[�T�v�����̌�A�g�y�r�V�Z�p���A��U�ȂQ�N�̎R�{�I�N�A�������p���w�ȂT�N��i
�痢�������t�̗z�C�̒��e�[�v�J�b�g���s���܂����B
�@�����ĎQ���҂ɂ��Z���^�[���w���s���A�e���������̒S���҂������̍\����V�K�ɓ���
���ꂽ�����@�퓙�̐������s���܂����B
 |
 |
 |
���̂Â��苳��Z���^�[�J�����y�ь��w��̗l�q
�@
�@
����26�i2014�j�N�x
�w�����ŏt�̗��Ղ��J��
�@
�@�S���P�X���i�y�j�A�w�����ɂďt�̗��Ղ��J�Â��܂����B
�@����́A�O���l���w����̌����������܂ޒ}�����Ƃ����̗�����P�T�O�����Q�����܂����B
�@���Ԃ̓X�|�[�c�Ŋ��𗬂��A�[������̓o�[�x�L���[�����Ȃ��痾�����m�̌𗬂�[�߂܂����B
�@��������ψ����ł����{�@�q�N�i�d�C�d�q�H�w�ȂS�N�j���͂��ߗ�������ψ��̂����b��
���A�Q���҂����́A���₩�Ŋy�����ꎞ���߂����܂����B
 |
 |
 |
�t�̗��Ղ̗l�q
�@
�@
����26�i2014�j�N�x
�w�����ɂĔ��P�������{
�@
�@�w�����ł́A�S���P�V�� (��)���ی�A���P�������{���܂����B
�@����́A�w�����̔��o�H�A�W���ꏊ�A�_�ĕ��@�̊m�F���s���A�n�k�ɂ��|��Ȃǂ̋���
������A�댯�ł���Ƒz�肵�āA���ꏊ�ł��鏬�X��Z��R�~���j�e�B�[�Z���^�[�ɔ���
�����B
�@�ޗ��H�w�ȂR�N�̒J���@�听���h��������擪�ɁA�P�����ݗ����Ă��������X�R���i�}����
�V�T���A�����P�W���j�́A�[���̃��b�V���A���[�̎��ԑтɂ�������炸���R�ƈړ����A
���߂�`���闾����������R�O����ɂ́A���X��Z��R�~���j�e�B�[�Z���^�[�ɓ������A
�_�Ăɂ��S���������m�F���܂����B
�@����̌P���ŁA��펞�̔��ꏊ�A���o�H�A�����@���m�F���邱�Ƃ��ł��܂����B
 |
 |
 |
�i������j�}�������֑O�œ_�Ă��Ă��闾��, ���ꏊ����������,���X��R�~���j�e�B�[�Z���^�[�őS���̖������m�F
�@
�@
����26�i2014�j�N�x
�w�����ɂđΖʎ����J��
�@
�@�S���W���i�j�[�H���ɁA�w�����̑Ζʎ����J�Â��܂����B
�@�}�����ɂ͂R�V���A�����ɂ͂V���A����Ƀ}���[�V�A�A�C���h�l�V�A����̂R���̗��w��
���}���A�V���ɂS�V����������������̑����͂P�V�V���ƂȂ�܂����B
�@���҂ƕs���ɋ���c��܂����V�������}����ɂ�����A��{�p�������厖����A�u�吨��
�W�c�����ƂȂ�̂ŁA�z�e���̂悤�ȃT�[�r�X�����҂�����A�A�p�[�g�̂悤�Ȏ��R���܂܂�
������]��ł͂Ȃ�Ȃ��B��炵�₷�����ƂȂ�悤�A�����ЂƂ�ЂƂ肪�A�K������������
�𑗂邱�Ƃ����҂���v�Ƃ̘b������A�V�����̖x�@���k�N�i�@�B�H�w�ȂS�N�j����́u���
�ł������v���č���Ɋ����悤�A������͊��ʼn����������v�Ƃ������A������܂����B
�@�܂��A���N�x�łQ�N�ڂɓ��闾���厖���̋����i�����A���{�A�J�A�ĉi�j���Љ��A
�Ō�ɁA���������y�������̂ɁA���L�Ӌ`�Ȃ��̂ɂ��邽�߁A�S���ŋ��͂��đf���炵��
�������グ�Ă������Ɛ��������܂����B
 |
 |
 |
�Ζʎ��̗l�q
�@
�@
����26�i2014�j�N�x
�����Q�U�N�x���w�������s
�@
�@�����Q�U�N�S���V���i���j�A�{�Z���̈�قɂ����ĕ����Q�U�N�x���w�������s����A�{�ȂQ�O�U���A
�ғ����R���A��U�ȂR�O���Ƃ��̕ی�҂̕��X���o�Ȃ��܂����B
�@���ł́A��c�Z��������w���錾���s���A�{�ȐV������\�A�ғ�����\�A��U�ȐV��
����\�̏��ɐ������q�ׂ��܂����B
�@�����čZ�������ł́A�u���ƂƂ����S�[���Ɍ������āA�������g�������邱�Ƃ��K�v�v
�Ƃ̌��t������܂����B
�@���I����A�厖�A�w�Ȓ��A�S�C�̏Љ�s���A�V���������͂��ꂩ��͂��܂鍂�ꐶ����
���҂ƕs���A�ْ��̖ʎ����ŏo�Ȃ��Ă��܂����B
 |
 |
 |
�{�ȐV������\�ɂ�鐾��
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�����Q�T�N�x���Ǝ��E�C���������s
�@
�@�����Q�U�N�R���P�V���i���j�A�{�Z���̈�قɂ����ĕ����Q�T�N�x���Ǝ��E�C���������s
����A�{�ȂP�X�W���̑��Ɛ��A��U�ȂR�S���̏C�����Ƃ��̕ی�҂̕��X���o�Ȃ��܂����B
�@���́A���Ɛ��E�C�����̎�������l�ЂƂ�ǂݏグ���A�Z�������ł́A�u�����̐S�������āA
���҂�Љ�̗��v���l���Ȃ���A�l���̍r�g�����z���Ăق����v�Ƃ̘b������A���ɗ��o���A
�Ɛi�݁A���l�ȕ��͋C�̒��ŏI�����܂����B
�@���ł͈��������A�\�������s���A�݊w���ɕw�A�ۊO�������ɂ����ėD�G�Ȑ��т����߂�
�w���ɕ\�����^����܂����B
�@���I����́A�e�w�ȁA��U�ɕ����ꋳ���ֈړ����A�S�C����e�l�ɑ��Ə؏��E�C���؏���
���^����A���߂�����͑��̈�قɂ����đs�s����s���A���Ɛ��E�C������ی�ҁE���E����
���H�������ɂ��Ȃ���A�{�ȑ��ƁE��U�C�����j���܂����B
 |
 |
 |
�i������j�Z�������A���ƁE�C���������A��U�Ȑ��֏C���؏��̎��^
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�r�W�l�X�}�i�[�u�K����J��
�@
�@�Q���Q�P���i���j�P�R���`�P�S���R�O���A�{�Z�̂c�P�����ɂ����āA�w���H���̋Ɩ����ϑ����Ă���
������Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂āA�c��@�����i���ЌF�{�u���b�N���[�_�[�j���u�t
�Ƃ��Č}���A�r�W�l�X�}�i�[�u�K����J�Â��܂����B
�@����͏A�E�����x����ړI�Ƃ������̂ŁA���ꂩ��A�E�������n�߂�S�N���̊�]�҂S�Q����
�r�W�l�X�X�[�c�̒����A�����V�̎d���A�h��̐������g�����A���[���Ɋւ����V�A�ʐڎ���
���ӓ_�Ȃǂ�^���Ɋw��ł��܂����B
 |
 |
 |
���Ȏp���̎w���A�����V�̎w��
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�v���ăe�N�m�u���b�W�ɏo�W
�@
�@�v���č���́A����Q���Q�W���i���j�ɋv���ăr�W�l�X�v���U�ŊJ�Â��ꂽ�u�v���ăe�N�m�u���b
�W�v���C�Ȓ����Љ�Ɍ����ā`�m�����������ăr�W�l�X�`�����X�`�i��B�o�ώY�ƋǁA�v���Ďs
����Áj�ɏo�W���A�n��A�g�����̎��g�݂Ɋւ���|�X�^�|�̓W�����s���܂����B
�@���̋v���ăe�N�m�u���b�W�́A�S������W�߂�ꂽ�D�ꂽ�����Z�p�̔��\�y�т��̋Z�p��n��
��Ƃƒn�掑���̉˂����Ƃ����Ƃ��Ė��N�J�Â���Ă�����̂ŁA���ɐ݂���ꂽ�W��
�u�[�X�ł́A�n��A�g�����̎�g�Ƃ��ē��c��r�����i�{�Z�@�B�H�w�ȁj�́u�V���R�[���S���̑f��
�����������������p���i���̃f�U�C���J���v���Љ�A��������������ƊW�҂̕��X���M�S
�Ɍ������Ă��܂����B
 |
 |
�v���ăe�N�m�u���b�W�o�W�̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
����@�\�㌎�������{�Z�����@
�@
�@�����������w�Z�@�\�̏㌎�������A����P���R�P���i���j�ɖ{�Z��K�₵�܂����B
�@�ߑO���ɍZ���̎{�݂����w���A�ŏ��ɋL�O�قɂ����ē��Z�̂V�T�N�ɂ킽����j�Ɠ`���ɐG
��A�����ċ@�B�v�f�v�������ɂ����āA�w���̎���i�����Ȃ���A���N���{�H�w���狦��
����\�����ꂽ�@�B�v�f�v����̎�g�Ɋւ���������܂����B���̌�A�d�C��H�A���w�A
�p�ꉉ�K���̎��ƁA�w������Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[�̏d�_�����v���W�F�N�g���A����ɑS��
�H���ɂ��{�N�x���烊�j���[�A�����ꂽ�}���ق����Z���^�[��IT�����Ȃǂ����@���܂����B
 |
�}���ق����@����㌎��������@�\����
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�O���]���ψ�����J��
�@
�@�v���č���ł́A����P���Q�X���i���j�ɊO���]���ψ�����J�Â����B�n���̑�w�A�s�A���w�Z
��n���Ƃ���̊O���L���҂V���̈ψ����o�Ȃ��A���Z����͏�c�Z�����͂��߁A�e�厖�E�w��
���A���������E�ے���P�X�����o�Ȃ��܂����B
�@�ψ���́A�R�c�~��B��w�H�w�������ψ����߁A�Z���̈��A�ɑ����āA���ȓ_���]����
�ɑ����āA�����厖����u����̌���Ɖ��P�����v�A�w���厖����u�w���ւ̎x���v�A����
�厖����u�w�����̌���v�A��U�Ȏ厖����u��U�Ȃɂ����鋳��̌���v�A���厖����u�Ǘ�
�^�c�v�A�Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[������u���������̏Ɛ��K�w���ȊO�ɑ��鋳��T�[�r
�X�̏v�A�����ے�����u�{�݁E�ݔ��̐����v�ɂ��Ă̐������s���܂����B
�@�e�O���]���ψ�����́A���猤�����̉��P�Ɏ�����M�d�Ȉӌ�����������o����A���Z��
�́A����������̊w�Z�^�c�̉��P�ɂȂ��Ă������ƂƂ��Ă��܂��B
 |
 |
�O���]���ψ���̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
���X��Z��܂��Â���^�c���c��A���N�琬���c������Z
�@
�@���X��Z��܂��Â���^�c���c��̋ߓ���Ə��X��Z����N�琬���c��̕P����
�Q���Q�P���i���j�ɗ��Z����܂����B�������A����P�U���ɊJ�Â��ꂽ�v���Ďs���N���S�琬
�w�`�Ɍ����āA�{�Z���㋣�Z���������X��Z��`�[���̏��w���̗��K���w���������Ƃւ�
���炪�A��c�Z���Ɨ��㋣�Z����\�ږ�̐Ԓː搶�ɑ��ďq�ׂ��܂����B
�@���w���̒j���P�O�l���P�`�[���ƂȂ��ĂP�O��ԁi�P�S.�W�����j�𑖂邱�̉w�`���ɂ́A���N��
�R�X�`�[�����Q�����A���X��Z��`�[���͂U�ʂɓ��܁A��N�ɑ����Q�N�A�����܂��ʂ����܂�
���B
�@���㋣�Z�����͍��N�P���̖�P�����Ԃɂ킽��A���X�쏬�w�Z�̃O���E���h�����w���ƈꏏ
�ɑ���Ȃ���A��l�͐擪�̑��҂����[�h���A������l�͍ŏI���҂��܂��Ȃ��町�������
�����̐��ŁA�q�ǂ������̗��K�w�����s���܂����B
�@����܂łQ�O�ʂƒ�����Ă����`�[���̑��т��A���㋣�Z�����̎w�����n�߂Ă���A
�Q�N�A�����܂ւƔ���I�ɏ㏸�������Ƃ𗼉�͊��ł����A���N���w�������肢������
�Ƃ̊�]���q�ׂ��܂����B
 |
 |
�w���������㋣�Z���������A���Z���ꂽ�ߓ���i������2�Ԗځj�A�P���i���[�j
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
��P�X��V���|�W�E��in�v���ā@��ʌ��J���
���炭��V�E�q��Ɋw�ԕ������R����A�g�e�N�m���W�[�J��
�@
�@�v���č���ł́A��ʎs���̕���ΏۂɁA����ɂ��Ă�藝����[�߂Ă��炤���Ƃ�ړI�ɁA
�P���Q�T���i�y�j�A��19��V���|�W�E��in�v���Ă��J�Â����̂ɕ����A�u���炭��V�E�q��
�Ɋw�ԕ������R����A�g�e�N�m���W�[�v�Ƒ肵���C�x���g���J�Â��܂����B
�@�v���Ďs�ANPO�@�l�v���Ă��炭��U����̋��͂̉��A�u���炭��V�E�q��v���Ɠc���v�d��
�l�Ă����u�|�g�����q�v��u���ޖ��v�̓W���������s���A�{�Z������u���炭��V�E�q��v�̏��C
�Ԃ��������C�@�֎Ԗ͌^�̎������s���ƂƂ��ɁA�]�ˎ��㒆���ɗL�n�˂����サ���a�Z
�̉�����s���܂����B
�@���̋Ɛтɂ��Ȃ�ŁA�����R���ꍇ���łR����v���R���A��s���{�b�g�̎�����\�[���[�{�[�g
�̓W�����s��ꂽ�ق��A�k��B���ꂩ��ɂ����Z���T�[���{�b�g�A�L�����ꂩ��}�C�N���o�u��
�ɂ��C�����u�A�v���č��ꂩ��|���U�q���̍��ꂪ�ւ�D�ꂽ�Z�p���Љ��܂����B
�܂��A����̒m���x�A�b�v�̂��߂̐i�H�����E���k����Â��܂����B
�@�����J�̍~�鈫�V��ɂ�������炸�A��S�O�O���̓���҂�����A���͑����̏����w����
�ی�҂œ��킢�܂����B
 |
 |
 |
���炭��V�E�q��Ɋw�ԕ������R����A�g�e�N�m���W�[�̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
��P�X��V���|�W�E��in�v�����J��
�@
�@�@�v���č���ł́A����P���Q�T���i�y�j�A �g���ꂩ�甭�i�I�u�Ȋw�Z�p�E�m�̑n���v�h���e�[�}��
��P�X��V���|�W�E��in�v���Ă��J�Â��܂����B
�@����V���|�W�E���́A�v���č���̌Ăт����ɂ��A��P�����W(�P�X�X�U)�N�P���ɋv���Ă�
�J�Â���Ĉȍ~�A�S���̍��ꐶ�̌������\�A�𗬕��тɋ������݂̘A�g�̏�Ƃ��āA�S������
���ŊJ�Â���Ă���A�Q���Ґ����N�X�����Ă��Ă��܂��B
�@�J��ł́A��c�F��Z���̊J�È��A�̂��ƁA�����G�������������w�Z�@�\�������A����
�p����B��w��w�@�������H�w�{�w�{������j�����q�ׂ��܂����B�����������́A�u�V���|�W�E���Ō������\���s�����ƂŁA
�����ȊO�̐l�ɑ�������̓����A�����ɂ��ė������\���łȂ��_��������@��ƂȂ�A
���傫�������ł���v�ƁA���ɏW�܂������ꐶ�Ɋ��҂����߂��G�[���𑗂��Ă��܂����B�����
�v���Ďs���L�́A�n���v���Ă��������Ɓu���炭��V�E�q��v���Ɠc���v�d����P�T�O�N�O��
���삵���u�|�g�����q�v�i��N�W���A���{�@�B�w��̋@�B��Y�ɔF��j�̎������s���A�����|��
�������Ƃ��ɂ́A��i�̋Z�p�̍����ɑ傫�Ȕ��肪�����Ă��܂����B
�@���������s��ꂽ���ʍu���ł́A�{�Z�����H�w�ȁi���@�ޗ��H�w�ȁj���ƂŁA�����ȃZ���~�b�N
�X�̊J���ɐ��������r���������i������Ѓ��[���h���{��\������j���u�t�Ɍ}���A�u�Ȋw�Z�p�E
�m�̑n���\�����ȃZ���~�b�N�X�̊J����ʂ��ā[�v�Ƒ肷��u�����s���܂����B�r�����́A�u����
�̌����ɊF���S�����悤�ɂȂ邽�߂ɂ́A������x�̒i�K�܂ŁA�����Ō������ʂ����߂Ȃ�
�Ƃ����Ȃ��A�펯�ɑ���ꂸ���R�Ȋw�̐^����Nj����邱�ƂŁA�C�m�x�[�V���������܂��v�ƌ��
�o�Ȏ҂͔M�S�Ɏ����X���Ă��܂����B
�@����̃V���|�W�E���́A����E��w�E��ƂȂǂ��Q�����A�S�X�R���̔��\�i�������\�R�O�S���A�|�X
�^�[���\�P�W�X���j�A�V�O�O������Q���ғo�^������A�Z���̂P�Q�����Ō������\�A�T�����Ń|�X�^�[
���\���s���܂����B�܂��A�X�P�[�������b�g�����������S���j�n�r�d�m�����l�b�g���[�N�U����
�����Љ�s��ꂽ�ق��A�u���炭��V�E�q��Ɋw�ԕ������R����A�g�e�N�m���W�[�v���e�[�}
�Ɉ�ʌ��J�̃C�x���g�������ɊJ�Â��A�����̂����ɏI�����܂����B
 |
 |
 |
��c�Z�����A�A��������@�\�������̏j���A������B��w��w�@�������H�w�{�w�{���̏j���̏j��
 |
 |
�s�������ی�ۂɂ��|�g���q�̎����A�r���������ɂ��u��
 |
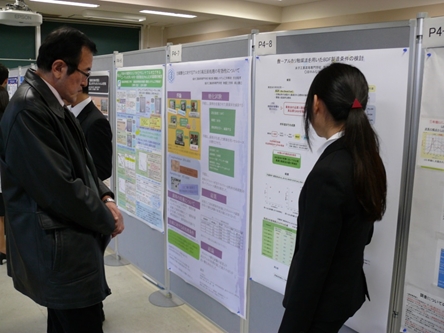 |
�w���̌������\�A�|�X�^�[���\�̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�������[�^�[�V���[�Q�O�P�S��B�w������ԗ��W�ɏo�W�E���ʏ��
�@
�@�v���č���́A�P���Q�S�i���j������Q�V���i���j�ɂ����ĊJ�Â��ꂽ�������[�^�[�V���[�Q�O�P�S��
�����Ċ�悳�ꂽ��B�w������ԗ��W�ɏo�W���܂����B
�@���̎ԗ��W�͎����ԃ��[�J�[��֘A���i���[�J�[�y�ш�ʗ���҂ȂǁA�����̗���҂��K���
���[�^�[�V���[�ɁA�w������ԗ���W�����邱�Ƃɂ��A�w���̎����Ԑ���ӗ~�ƋZ�p������
���߁A�����Ėk����B�̎����ԎY�Ƃ̐U����}��ړI�ŊJ�Â��ꂽ���̂ŁA��B�n��̑�w
�⍂��A���w�Z�A�H�ƍ��Z�̊w���E���k�����삵���P�V��̎ԗ����W������A��l����q��
�܂ő吨�̗���҂����w�ɖK��A�w���E���k�����̐����Ɏ����X���Ă��܂����B
�@�{�Z�̎ԗ��͋@�B�H�w�Ȓ������m�������̖{�Ȑ��E��U�Ȑ��y�уG�R�p���[���D��ɂ��
���삳�ꂽ���̂ŁA���R�@�ւƔ�r���ĔR���̓��͕ϊ������������A�����㎩���ԗp�̓��͌�
�Ƃ��Ċ��҂���Ă��鐅�f��R���Ƃ����N���[���ȓ��͌��A�R���d�r�G�R�����J�[�i1�l���R��
���Z�p�ԗ��j���o�W�B
�@�Q�U���ɂ͏o�W�ԗ���ΏۂƂ����R����J�Â���A�G�R�J�[����œ��ʏ܂���܂��܂����B
 |
 |
 |
�W���ԗ��A����҂ɐ�������w���A������̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
��������@�\���������v���č���ƍ���V���|�W�E�������@
�@
�@�Ɨ��s���@�l�����������w�Z�@�\�̏����G�����������A����P���Q�T���i�y�j�ɋv���č�
��Ɠ��Z�ŊJ�Â��ꂽ����V���|�W�E�������@���܂����B
�@�ŏ��ɏ�c�F�Z������T�v����������A�L�O�ق�K��āA���������v���č����H�Ɗw�Z
�ȗ��̓����̗l�q���Â��ʐ^��^�C�K�[�v�Z�@�������w���܂����B�����ċ@�B�v�f������
�ł́A�����Q�O�`�Q�Q�N�x�̕��ȏȋ���f�o�ł̓��e���X�ɔ��W�E�[���������f�W�^���G���W�j�A��
���O��p�����@�B�v�f�v����̎�g�ɂ��āA����ɎY�w���A�g�e�N�m�Z���^�[�ł́A�d�_
�����v���W�F�N�g���ł̃v���W�F�N�g�ɂ��āA���ꂼ��@������Ȃ�����������ق��A
�w������}���قȂǂ����@���܂����B�e�ꏊ�Ő������������ɑ��A�����̎�g��{�݂̗��p
�ȂǐϋɓI�Ɏ��₵�Ă��܂����B
�@�����������́A���ꎋ�@��A���Z�ŊJ�Â��ꂽ����V���|�W�E���̊J��ŗ��o���A���q��
����A�S������Q���������ꐶ�̌������\���͓I�ɉ��A���\�w���ɑ��Ď��������
�ȂǔM�S�Ɍ������\���Ă��܂����B
 |
 |
 |
�@�B�v�f�v����̐����������鏬��������(������2�l�ځj�A�w���������̗l�q�A�|�X�^�[���\���s�����w���̐������l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
����25�N�x��B�E����n�捂��e�N�m�Z���^�[������c���J��
�@
�@�v���č���ł́A����P���Q�S���i���j�A�����Q�T�N�x��B�E����n�捂��e�N�m�Z���^�[
������c���J�Â��܂����B
�@�@���̉�c�͍���łP�P��ځB�ŏ��ɋv���č����S���Z�Ƃ��ĊJ�Â���A��B�E����n��
�X����P�O�L�����p�X���ꏄ���A�ēx�v���č��ꂪ�S���Z�Ƃ��ĊJ�Â���Ă��܂��B
�@��c�ɂ́A��B�E����n��e����̃e�N�m�Z���^�[�����ɉ����A�����������w�Z�@�\����
�獂���O�n��C�m�x�[�V�������i�{���Y�w�A�g�E�m�I���Y���i�����炪�o�Ȃ��܂����B
�@��c�F�Z���̈��A�̌�A���c��r�v���č���Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[�����i��Ƃ��āA
�c�����i�߂��A�e���ꂪ��������_�A����A�V���Ȏ��݂̎��{�ȂǁA�����Ȉӌ�����
�E�c�_���s���܂����B
�@��c�I����́A���c�Z���^�[���̈ē��̉��A�w���{�݁i�Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[���j
�̌��w���s���A����ɏꏊ��ς��Č𗬉���s���܂����B
�@���̉�c��ʂ��āA��B�E����n��e����̃e�N�m�Z���^�[���Ԃŏ�L������ɐi�݁A
�A�g����w�[�߂��܂����B
 |
 |
 |
��c�̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
���炭��V�E�q��W�Łu����C�x���g�f�[�v�����{
�@
�@�v���ďo�g�̔����Ƃ�(��)���ł̑n�Ǝ҂ł���c���v�d�̋Ɛт����ǂ�u���炭��V�E�q��W�v
�������p�قŊJ�Â���Ă��邱�Ƃɂ��Ȃ݁A�v���č���͂P���P�P���ɓ����p�ق����ɂ��āA
�v���č���C�x���g�f�[�����{���܂����B
�@�ٓ��ł́A���{�b�g�𑀍삷��u���{�b�g�ŗV�{�b�g�I�v�A�o�[�`�����ȉԉ�e��v���O������
�̌��ł���u�\�t�g�E�F�A�w����i�v�A��V��v���Ĕˎ�̗L�n���䂫�i�u�䂫�v�͂��傤�ɂ�ׂ��
���j���˓��ŏ��サ���u�v���Ă̘a�Z�v�̂R�R�[�i�[��݂��A�q�ǂ����������E����w���̐�����
�āA���ꂼ��̉ۑ�ɔM�S�Ɏ��g��ł��܂����B
�@���p�ّO�̍L��ł́A�c���v�d�����삵�����C�@�֎Ԃ̖͌^��͂��ċv���č��ꂪ���삵��
���C�@�֎Ԗ͌^�̐����Ǝ������s���A�ڂ̑O���������Ƒ���n�߂����C�@�֎ԂɁA�q�ǂ�
��������傫�Ȋ�����������܂����B
�@�A�x�����Ƃ������Ƃ������āA���͂V�U�X���̗���҂œ��킢�܂����B��Ԃ��߂��Ă�������
�q�ǂ����������Ɏc��A�C�x���g�͐����̂����ɖ�����܂����B
 |
 |
 |
���C�@�֎Ԏ����̗l�q�A�v���O���~���O�Q�[���ŗV�Ԏq�������A���{�b�g�ŗV�{�b�g�I
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
���؏܍�Ƃ̈��������Y������Z��K��
�@
�@����P���P�W���A�v���č��ꑲ�Ɛ��ő�P�S�W�؏܂���܂������j�����Ƃ̈��������Y��
����Z��K�₵�܂����B
�@���Z���O�r�[���n�a�ł���������́A�����ږ�̍]�菸���A�����G�T�y�����̈ē��ŁA
���O�r�[���n�a��̍��X�ؕq�������ƃ��O�r�[���̗��K�̗l�q��A���������쎌��������
�����܂�Ă���O���E���h���̓����n���T�O���N�L�O���������A�Z������K��A��c�F�Z��
�ƍ��k���Ă���A�}���قɐ݂���ꂽ�w���������Y�R�[�i�[�x�����w���܂����B
�@���̃R�[�i�[�́A�}���ق̑S�ʉ��C�H�����I���A���N�x���烊�j���[�A���I�[�v����������
���_�@�ɐ݂����A������������ꂽ�S��i��W���������̂ŁA�R�T��i�X�V�����P�[�X��
���߂��Ă��܂��B�������́A���ފكQ�[�g���ʂ̃P�[�X�ɓW�����ꂽ����̑S��i�����S�[��
�l�q�ň�]���A��y�w���̂��߂ɍ���������̊����Ă��܂����B
 |
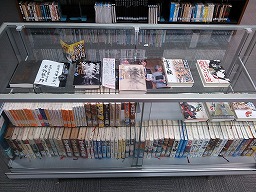 |
�������̖K��̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�����Q�T�N�x�w�������l�����J��
�@
�@�v���č���ł́A����P���P�U���i�j�A�����Q�T�N�x�w�������l�����J�Â��A���w���i�C�������N
�i�ޗ��H�w�ȂR�N�j�j���܂ނQ�V���̐V���l���j�����܂����B
�@���ł́A�n�߂ɉ��������\���Ď��яr�M�����i�d�C�d�q�H�w�ȂS�N�j����V���l�ɑ���
�j��������A���̌�A�F�������N�i�@�B�H�w�ȂT�N�j����V���l���\���Ďӎ����q�ׂ��A
�u���ꂩ�琬�l�Ƃ��Ă̎��o�������Ċ撣�肽���B�v�Ƃ̕���������Ă��܂����B
�@�Ō�ɁA��{�p�������厖����́A�V���l�ւ̏j���Ƃ��āA�u����w�̎��o�ƐӔC�������āA
���X�̐����𑗂��Ăق����B�v�Ƃ̃G�[���������܂����B
�@�V���l�����́A����ʂ��Đ��l�Ƃ��Ă̎��o�����߂Ċ����Ă���l�q�ł����B
 |
 |
 |
�w�������l���̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�}���[�V�A�EMJII�iMARA-JAPAN Industrial Institute�j�̊w���Ƃ̍��ی�
�@
�@����P�Q���P�W���i���j�A�}���[�V�A�̂l�i�h�h�ɍݐЂ���w���P�Q���Ƌ����Q�����{�Z��K��܂�
���B
�@����́A���v���c�@�l�I�C�X�J�����{����}���[�V�A�E�l�i�h�h�w���K���v���O�����̈�Ƃ��āA
���@�l���{�Z�֎����̗v�������������̂ł��B
�@�{�Z�֓�����A�n�߂ɍ��؏ˌ����厖�₩��{�Z�̏Љ����A���̌㐶�����p���w�Ȃ�
�w���Ƃ̌𗬂��s���A�l�i�h�h�̊w������}���[�V�A�̕��x������I���ꂽ�ق��A�����O���[�v
�ɕ�����Ă̍��b���s���܂����B
�@�����āA�E�F�[�u�z�[���i�w���H���j�A�w�����y�ѐ}���ق̌��w�����H�w�Ȃ̊w����
�����������̌𗬂��s���܂����B
�@�Ō�ɁA�{�Z�ݐЂ̗��w���Ƃ̍��k���s���A�{�Z�ɂ�����}���[�V�A�E�l�i�h�h�w���K���v��
�O�������I���܂����B
 |
|
 |
 |
(��j�������p���w�Ȃ̊w���Ƃ̌𗬁A�i��������j������H�w�Ȃ̊w���Ƃ̌𗬁A�{�Z���w���Ƃ̌�
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�w�����ɂďH�̗��Ղ��J��
�@
�@����P�Q���V���i�y�j�A�}�����Ƃ������痯�w�����܂ޖ�P�Q�O���̗������Q�����āA�w��
���ɂďH�̗��Ձi�����ψ����F�@�B�H�w�ȂS�N���c�֔V�N�j���J�Â��܂����B
�@�܂��O���[�v�ɕ�����Ă����������s���A����Ȃ��n�ɍŏ��͌˘f���Ȃ�����݂���
�y����ł��܂����B
�@���ɁA�X�|�[�c���ł́A�`�[���ɕ�����ă\�t�g�{�[�����Z���s���A���𗬂��Ȃ���A�y��
�����Ƀv���C���Ă��܂����B
�@�Ō�ɗ[������o�[�x�L���[�p�[�e�B�[���s���A�H�̗��Ղ���߂�����܂����B
 |
 |
 |
(������j�݂��A�����݂��ۂ߂�l�q�A�X�|�[�c���̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
��U�Ȑݒu20���N���L�O����u������J��
�@
�@�{�Z�ł́A��B�E����n�捂��ōŏ��ɐݒu���ꂽ��U�Ȃ��A�Q�O�N�̐ߖڂ̔N���}���A����
�P�P���Q�X���ɋL�O�u������J�Â����B�Q�O�O������ݍZ���E���E�����o�Ȃ��܂����B
�@��c�F�Z������̊J��̈��A�̂��ƁA�u����͎O���\���ōs���A��ꕔ�ł́A����������
�i��B��w��w�@�������H�w�����@�����j�Ə����������i��ꐸ�H������Џ햱������i�{�Z
�@�B�H�w�ȑ��j�j���u�t�Ɍ}���A�u���ꑲ�Ɛ��A��U�ȏC�����Ɋ��҂������́v�Ƒ肵�ču����
�s��܂����B
�@������ł́A�{�Z��U�Ȃ̏C�����ŁA���݊�Ƃ̑����Ŋ������̎Љ�l���w�@��
���u�t�Ɍ}���A�u�Љ�l�Ƃ��Ă̖����v�u��y�̊F����ցv�Ƒ肵�A�Љ�l�Ƃ��Ă̐S�\���A�݊w��
�ɂ���Ă����ׂ����Ƃ��y�����炱���킩��݊w���̔Y�݂ɂ��ču�����s���܂����B�C����
�̑�������w�@�ɐi�w���Ă��邱�Ƃ�����A����Ƒ�w�̈Ⴂ�A����̗ǂ��Ƒ�w�̗ǂ��Ȃǂ�
�Љ��܂����B
�@��O���ł́A�u�t�E��U�ȏC�������A���̍ݍZ���ƃp�l���f�B�X�J�b�V�����`���ŁA���^��
�����s���A�݊w������͐�y�����̎��̌������Ɛ������̎��₪���܂����B
�@�o�Ȃ����w���́A�^���Ȃ܂Ȃ����ōu�t�̘b�ɕ�������A��y�����̎��̌��܂����b��
�l�X�Ȃ��Ƃ������Ƃ����l�q�ł����B
�@�Ō�ɁA�r�c����U�Ȏ厖�����̈��A���s���A�����̂����ɋL�O�u����͕�A
���̌�A�����ڂ��č��e��s���A�u�t�y�ъw�Z�W�҂Ő�U�Ȑݒu20���N���j���܂����B
 |
 |
 |
(������j��y�֍u�������U�ȏC�����A�����A�p�l���f�B�X�J�b�V�����̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�����Q�T�N�x�m�I���Y�Ɋւ���u�K����J��
�@
�@����P�Q���T���ɓƗ��s���@�l�����������w�Z�@�\�n��C�m�x�[�V�������i�{���Y�w�A�g�E
�m�I���Y���i�������R�[�f�B�l�[�^�̖쒆���������u�t�Ɍ}���A�����Q�T�N�x�m�I���Y�Ɋւ�
��u�K����J�Â��܂����B
�@���̍u�K��́A�v���č���̋��E����ΏۂƂ��āA���猤��������Y�w�A�g�̐��ʂ̂����L
�v�Ȓm�I���Y�̌������A�Љ�ɂ����銈�p�A�y�ђm�I�n���T�C�N���̍X�Ȃ�W�J�A���тɒm�I
���Y�ւ̑Ή��\�͂̌����ړI�Ƃ��ĊJ�Â���A�Q�R���̋��E������u���܂����B
�@�����čs��ꂽ�ʑ��k��ł́A�ߔN�v���č���ɕ��C���������Ȃǂ������֘A�̑��k��
�s���A�\�莞����啝�ɃI�[�o�[����Ȃǐ����̂����ɏI�����܂����B
 |
 |
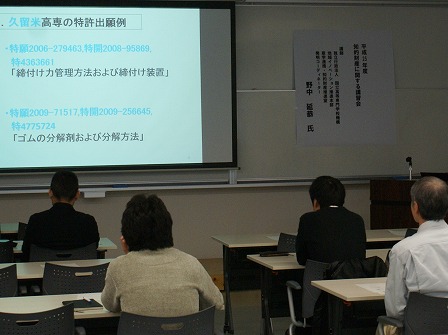 |
�u�K��̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
��B����n��j�n�r�d�m�V�Z�p�}�b�`���O�t�F�A�Q�O�P�R�ɎQ��
�@
�@����P�P���P�R���A�Ɨ��s���@�l�Ȋw�Z�p�U���@�\�Ƌ�B����n��X����́A���m�Â���t�F�A
�Q�O�P�R�i�����H�ƐV���Ў�Áj�̕��ÃC�x���g�Ƃ��āA�u��B����n��j�n�r�d�m�V�Z�p�}�b�`���O
�t�F�A�Q�O�P�R�v���}�������b�Z����(�����s)�ŊJ�Â��܂����B
�@���̃C�x���g�́A��B����n��X���ꂪ�ۗL���関���J������JST���ƍ̑��Č����A������
�i�Z�p�ۗL�ҁj���g����ƊW�҂�ΏۂɁA���p���ւ̓W�]�܂����Z�p�������s���A���{
��Ƃ⌤���p�[�g�i�[���W���邱�Ƃ�ړI�Ɏ��{�������̂ł��B
�@�e���ꂩ��V���̔��\������A�v���č��ꂩ��́u�����ԘI�o�B�e�ɂ����ăn���[�V��������
�摜���o�͂���J�����V�X�e���v�Ƒ肵�A���{���L�����i������H�w�ȁj�����\���s���܂����B
�@���\��ɂ͌ʑ��k�R�[�i�[���݂����A�S������������҂ɑ��Ď��ۂɋ@�B����ɂ�
�ĐV�Z�p�̐������s���܂����B����͎��p���Ɍ�������̓I�Ȏ��g�݂̐��i�⋤��������
�ւ̔��W�����҂���Ă��܂��B
 |
 |
 |
���\���s�����{����
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
��������@�\�\�������E�㓡�l���ے����{�Z��K��
�@
�@�����������w�Z�@�\�̌\����j�����ƌ㓡�����l���ے����A�P�P���P�T���{�Z��K�₵
�܂����B
�@�\��������͏�c�F�Z����ƍ��k���s������A�w�Z���{�݂����@���܂����B
�@�ŏ��ɁA�L�O�قł͖{�Z�̂V�O�N�ȏ�ɂ킽����j�Ɠ`���ɐG��A�����ė��̓I�ȍ\������
�v�E���}�����K����b�`�c���K���i�@�B�H�w�ȓ��j�A�w�����̋����E�H���Ȃǂ�Y�w���A�g
�e�N�m�Z���^�[�̏d�_�v���W�F�N�g���A���N�R�����C�H���ɂ�胊�j���[�A�������}���ق�
�}���قQ�K�Ɉړ]��������Z���^�[��IT�����⑽�ړI���Ȃǂ����@���܂����B
�@�\��������́A���@�������ꂼ��̏ꏊ�Ő������������ɑ��āA���Ƃ�w���A�Y�w
���A�g�̌����ۑ�Ȃǂɂ��ĐϋɓI�Ɉӌ��������s���܂����B
 |
 |
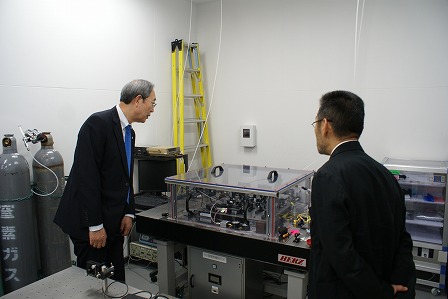 |
�w�����@�̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�^�C�̍��Z�����{�Z��K��
�@
�@�P�O���Q�S���ɁA�^�C�̍��Z���P�T�����A�{�Z��K��܂����B
�@����̖K��́A�Ɨ��s���@�l�������N����U���@�\�����{����u�����Q�T�N�x�����Ȋw��
�ϑ����Ɓi���N����{�݂����p�����𗬎��Ɓj�^�C�������Z�����ٌ𗬎��Ɓ@�`���E�^�C
���N�����ナ�[�_�[�̈琬�`�v�̈�Ƃ��āC������{�������N���R�̉Ƃ�������^�C
�̍��Z�����C���{�̐��N�Ƃ̌𗬂��邽�߂ɖK�ꂽ���̂ł��B
�@���Z�������͕ꍑ�œ��{����Q�O����Ƃ��Ċw�K���Ă���A�{�Z�v���O���~���O���{����
�w���Ɠ��{����܂����Ȃ���𗬂��C�S������v���O���~���O�R���e�X�g�̎�܍�i�̃f����
���w������C�|���U�q��p�������������Ȃǂ��s�����B�܂��A���̃A�W�A��������{�Z�ɗ��w
���Ă���w���Ƃ����{��Ŋ��k���s���A�w���ԂŌ𗬂�[�߂Ă��܂����B
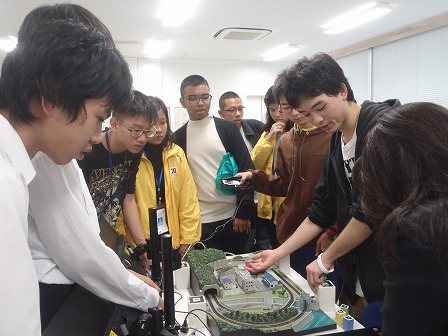 |
 |
 |
�K��̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�u��P�W��}�i�r�B�����h�v�Ɂu�ӂꂠ�����H�w�W�v���o�W
�@
�@�P�P���P�O���ɁA���[��s�A�v���ĂŊJ�Â��ꂽ��P�W��}�i�r�B�����h�E���ǂ��t�F�X�e�B�o���ɂ���
�āu�ӂꂠ�����H�w�W�v���o�W���܂����B�����́A���V�ɂ�������炸�q�ǂ���e�q�Â��P,�Q�O�O��
���K��A�����̂����ɏI�����܂����B
�@�}�i�r�B�����h�́A�s���̐��U�w�K�ւ̈ӗ~�ƊS�����߂邽�߁A�v���Đ��U�w�K���i�s������
�v���Ďs�ق��̎�ÂŎ��{����Ă�����̂ŁA�{�Z�͏��w���𒆐S�Ƃ�����ʎs���Ɂu���H�w�v��
�ʔ�����s�v�c����̌����Ă��炤���Ƃ�ʂ��āA���ɐ��N�̗��H�w�ɑ��鋻���E�S��[��
�邱�Ƃ�ړI�ɖ��N�o�W���Ă��܂��B
�@���N�̏o�W���ł́A�e�w�Ȃ̋��͂āA�u���{�b�g�ŗV�{�b�g�I�v�A�u�d�q�H��@�N���b�v���[�^
�[�ƁA�Â��Ȃ�ƃs�J�s�J����d�q�z�^������낤�v�A�uKinect��p�����摜����/���{�b�g�A�[����
�R�����O���t�B�b�N�X�v�A�u�}�C�N���J�v�Z���y���_���g�v�A�u�ӂ����ȋ����ɂ���낤�v�A�u����������
�s�v�c�Ȍ��ہv�̂U�̑̌��E�����R�[�i�[��݂��܂����B
�@���C�x���g�ł��Ȃ��݂ƂȂ����o�W���ɂ́A�������̋��E���≞���w���̎p�����ڂɁA�J���
�҂���т�q�ǂ��̃O���|�v��e�q�Âꂪ���������A�I�[�v���Ɠ����ɂ��ړ��ẴR�|�i�|
�ɉ�����ȂǁA�q�ǂ���������łȂ���l���傢�ɋ������������l�q�ŋv���č���Ȃ�ł�
�́u�Ȋw��H�w�̐��E�v���y����ł��܂����B
 |
 |
 |
������u���{�b�g�ŗV�{�b�g�I�v�A���S�i�A�u����������s�v�c�Ȍ��ہv�̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�X�P�A�[�h�X�g���[�g�����ɂ���ʈ��S�u�K������{
�@
�@�i�`���ς̎x���A�������x�@�{���A�v���Čx�@���̋��͂āA�P�O���R�O���ɖ{�Z�O���E���h
�őS�w�N��ΏۂɌ�ʈ��S�u�K������{���܂����B
�@���u�K��́A�{�Z�̂قƂ�ǂ̊w�������]�ԁE�o�C�N�E�����Ԃɂ��ʊw���Ă��邽�߁A���
���S�ӎ��̌����ړI�Ƃ������̂ŁA�x�@�����ɂ��u�b�ɉ����A���ۂ̌�ʎ��̗̂l�q��
�v���̃X�^���g�}������������X�P�A�[�h�X�g���[�g�i���|�̎����j�����ɂ����{����܂����B
�@�����ł́A���]�Ԃ̕��i�A��l���A�P�����A�g�ѓd�b��C���z���̎g�p�Ȃǂ̈ᔽ���s�A
�ꎞ�s��~�A�M�������ɂ��}�Ȕ�яo���A��^�Ԃ̍��܊������݂ȂǁA�X�^���g�}�������
���̂����A���ɍČ�����܂����B
�@�Q�������w���́A�u���ۂɎ����ԂƎ��]�Ԃ��Փ˂���u�Ԃ��������́A���]�Ԃ̕������v
���{���ɐS�z�����B�܂��A���]�Ԃɏ���Ă��Ă��A���肪���]�Ԃ���s�҂ł���Α傫�Ȏ���
�ɂȂ���̂Œ��ӂ������B�v�Ɗ��z���q�ׂĂ��܂����B�܂��A��Q�҂ƂȂ��Ă��A���Q�҂ƂȂ���
���A���̂̕|����m��悢�@��ƂȂ����悤�ł����B
 |
 |
 |
��ʈ��S�u�K��̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
SuperCon2013�ŗD�������w���`�[�����v���Ďs���s����\�h�K��
�@
�@���̉āA�����H�Ƒ�w�Ƒ���w���J�Â����u�Ă̓d�]�b�q���v��P�X��X�[�p�[�R���s���[
�e�B���O�R���e�X�g�iSuperCon2013�j�ŏ��D�����ʂ�����������H�w�ȂQ�N���Ńv���O���~���O
���{���ɏ�������imishinn�i���݂���j�`�[���̊w���R���i�v�ۓc�˕��N�A�t�z��l�N�A�g�c
����N�N�j�Ə�c�F�Z���A�w�������̍��؏ˌ��y�����炪�A�P�O���Q�W���ɋ��{���F�v���Ďs
���s����\�h�K�₵�A�D���̕��s���܂����B
�@�����o�[�̋g�c����N�N�́u���Z�����ɂ����A�C�f�A�������сA�R�l�Ō���i�߂Ă���������
�������\�Ȃ��Ƃ������������͖{���Ɋ����������B�v�ƗD���̊�т����A���{���s������́A
���j���ƌ���̌��t���q�ׂ��A�w���������̊���𐾂��Ă��܂����B
�@����̃R���e�X�g�́A���H��̃X�[�p�[�R���s���[�^�ł���TSUBAME2.0���g���ĕ���
���s���v���O�������쐬���C���̐��x�Ƒ��x���������Z���E���ꐶ�P�`�R�N���Ώۂ̃R���e�X�g�B
�S���ŗ\�I�������������Q�O�`�[�����A�T���Ԃ������ē��������v���O�������쐬���A����
���\�����������܂����B
�@�Ȃ��A�D���ɂ��R���̊w���͗��N�Q���ɊJ�Â������{���I�����s�b�N�̖{�I�o�ꌠ��
�l�����܂����B
 |
 |
 |
�\�h�K��̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�w����𒆐S�Ƃ���L�u�̊w�����v���Ďs�X�n�y�ъw�Z���ӂ̐��|���������{
�@
�@�P�O���P�X���A�w����𒆐S�Ƃ�����U�O���̗L�u�w�����A�ʊw�̌o�H�Ƃ��đ����̊w�������p
���鐼�S�v���ĉw���ӂƊw�������̒��S�ł��鏬�X��n��ɂāA���|���������{���܂����B
�@���̐��|�����́A������肨���b�ɂȂ��Ă���n��̕��X�֊��ӂ̈ӂ����߂Ď��{��������
�ŁA�w���ӂ̏��X�X�Ȃǂ���̗v�]�܂��āA�S�~�E����ǂ̗����������Ȃǂ��s���A�Ō�
�ɍZ���̃S�~�E����Ԃ̔��A�����s���āA1���̐��|�������I���܂����B
�@�Q�������w���́A�u������n��ɕ�炷���X�֏����ł��v���ł��邱�Ƃ�����Α����Ă�����
���B�܂��A���|���������łȂ��l�X�Ȋ�����ʂ��Č𗬂��[�߂Ă��������B�v�Ǝ��ւ̐V���ȕ�
��������Ă���A�L�Ӌ`�Ȑ��|�����ƂȂ����悤�ł����B
 |
 |
 |
���|�����̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�����Q�T�N�x�w�Z������E���w����J��
�@
�@�����Q�T�N�x�w�Z������E���w����P�O���P�X���ɊJ�Â��A���w���A�ی�҂Ȃǖ�R�O�O�����{�Z
��K��܂����B
�@�w�Z������ł́A��c�F�Z�����w�Z�S�̂̊T�v�������s������A�R�{�苳���厖�₩��e�w
�Ȃ̏Љ�� �����Q�U�N�x���w�����ɂ��Đ������s���܂����B
�@���������s��ꂽ�w�Z���w��ł́A�e�w�ȂŎ������̐ݔ���W�����Ȃǂ����J����܂����B
�@�Q���������w������́A�u���H�I�ȕ��Ɏ��g�߂邱�ƁA��̏A�E�A�i�w���������邢���@��
�ƂȂ����B�v�A�u����ɂ��Đ[���������邱�Ƃ��ł��A�����ւ̖ڕW�����m�ɂȂ����B�v�Ȃǂ̊��z
�����܂����B
 |
 |
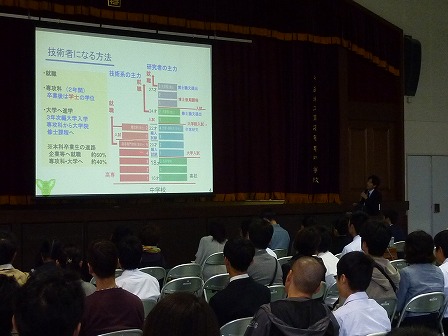 |
�w�Z������̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�����Q�T�N�x�v���Ďs���P�ʌ݊�����Z�ɂ��u�����u�`�v���J�u
�@
�@�P�O���P�P���A�Q�T���̂Q���ԁA�v���Ďs���P�ʌ݊�����Z�i�v���đ�w�A�v���čH�Ƒ�w�A���}
���A�w�@��w�A�v���ĐM�����w�@�Z����w�A�v���čH�ƍ������w�Z�j�ɂ�鋤���u�`���J�u
���܂����B
�@���̋����u�`�͋v���Ďs��5�̑�w���Ƌv���Ďs���A�g���A���N��̃e�[�}�Ŋe��w����
������F�������u�������ꂼ��ɊJ�u������̂ŁA���N�́u�v���Ă̐����Ɗ��v���e�[�}
�ɍu�`���s���܂����B
�@�{�Z����́A�P�O���P�P���ɓ��c��r�����i�@�B�H�w�ȁj���u�v���Ă̊��ƃ��r���e�B�v�A�P�O��
�Q�T���ɋ��؍G�a�y�����i�������p���w�ȁj���u��������p�������v�Ƒ肵�u�`���s���A����
�Z�̊w����X�O������u���܂����B
 |
 |
 |
�����u�`�̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�����Q�T�N�x�v���čL�揤�k��ɏo�W
�@
�@�v���čL�揤�k��i��ÁF�v���čL��莩�����y�іk����B�r�W�l�X�}�b�`���O���c��j���A�P�O���Q�S����
�v���ă��T�[�`�E�p�[�N�ōs���A�{�Z�͎Y�w�A�g�R�[�i�[�ɂ����āA�{�Z�ɂ�����Y�w�A�g�ւ̎��g�ݏ�
��e�N�m�l�b�g�v���Ăɂ��ďЉ��|�X�^�|�W�����s���܂����B
�@���̏��k��́A�n��Y�Ƃ̐U���E��������}�邽�߁A�n�������Ƃ̊�Ƃ�ΏۂƂ��ĐV�K����J��̏�Ƃ���
���N�J�Â���Ă���A����łW��ڂ��}���A��N�����̊�Ƃ��Q�����Ă��܂��B
�@�W���u�[�X�O�ł́A�{�Z�ɋ������������Q���҂������~�߂ă|�X�^�|�Ɍ�����A�S���̖{�Z�E���֎Y�w�A�g��
�����e�N�m�l�b�g�v���Ă̊T�v�Ȃǂɂ��ĔM�S�Ɏ��₷��p�������������܂����B
 |
 |
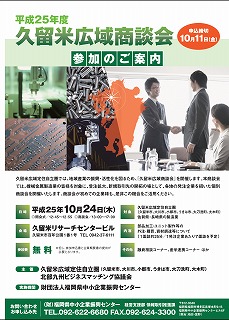 |
�v���čL�揤�k��̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�����Q�T�N�x�v���āE�����n��Y�w���e�N�m�𗬉�ɎQ��
�@
�@������Ћv���ă��T�[�`�E�p�[�N����Â���v���āE�����n��Y�w���e�N�m�𗬉�A�P�O���Q�Q���ɋv���ă��T
�[�`�E�p�[�N�ɂčs���A�{�Z����́A�n��A�g�����̎��g�݂Ɋւ��锭�\�y�у|�X�^�|�W���Ȃǂ��s���܂����B
�@���̌𗬉�́A���̂Â���ɖ𗧂�������l�b�g���[�N�Â���̏�Ƃ��āA���N�J�Â���Ă�����̂ŁA����
�Q�T�N�x�́w���m�Â��蒆����Ƃɂ�����Y�w���A�g�J���̊��ǂ���x�Ƃ����e�[�}�ŊJ�Â���A�P�U�̊�ƁE�c�̂���
�Q��������܂����B
�@�𗬉�ł͕������H�ƋZ�p�Z���^�[�����_�J���G���ɂ���u���̌�A�����@�ւ̎Y�w�A�g�����̏Љ��
�A�g�J������Љ�s���A�{�Z����͓��c��r�Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[�����u�v���č���ɂ�����n��A�g
�̐��i�ɂ��āv�Ƒ肵�Ĕ��\���s���܂����B
�@�܂��A���ɐ݂���ꂽ�W���u�[�X�ł́A�{�Z�̒n��A�g�����̎�g�Ƃ��āu�e�N�m�l�b�g�v���āv�y�сu�Y�w��
�A�g�e�N�m�Z���^�[�v�̎��Ɗ������p�l���⎑���ŏЉ�A��������������ƊW�҂̕��X�͎b�������~�߁A
�M�S�Ɍ������Ă��܂����B
 |
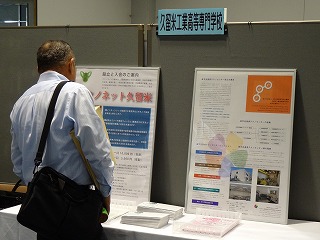 |
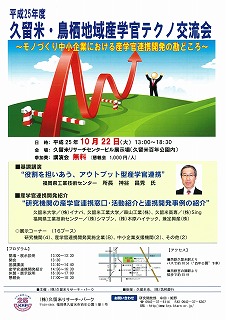 |
�e�N�m�𗬉�̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�v���Ďs���T��w���A�g�ɂ��s�����J�u�����J�u
�@
�@�P�O���P�X���A�v���č�����܂ގs���T�̑�w�E�Z��E����ō\������鍂������R���\�[�V�A���v���Ă���Â�
��s�����J�u���ɂ����āA�{�Z�͍��L���y�����i��ʉȖڕ��Ȍn�j���u�������S���q�������֖L���Ȏ��R�����ǂ�
����Ύc����̂��v���e�[�}�ɁA�u���o�ϊw�v�̍u�����s���܂����B
�@�u���ł́A�ߔN�[�������Ă�������ɂ��āA�����K���ɕ]������Ă��Ȃ����v�D��̎s��o�ό^�Љ��
���_���������ƂƂ��ɁA�����\�ȎЉ�̂�����Ƃ��̂��߂̋�̓I�ȕ�����������o�ϊw�̏Љ���s���܂����B
�@��u�҂́A�������S���q�������֖L���Ȏ��R�����c���Ă������߂ɁA���o�ϊw�̍l�����ɂ��ė������A��
��������̖�肪�����ł���̂����l����@��ƂȂ����悤�ł����B
 |
 |
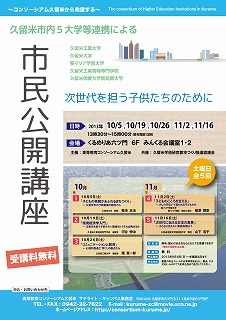 |
�s�����J�u���̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�w�����ɂĔ��H�V�~�����[�V�����Ȃǖh�Д��P�������{
�@
�@�P�O���P�U���A�w�����ɂďH�̖h�Д��P�������{���܂����B
�@�n�߂ɖh�Д��P���̈�Ƃ��āA�w�����̋��H�Ɩ����ϑ����Ă��銔����Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂̂��ƁA
�w�����H���ɂ����Ĕ��H�����ۂɐH������H�V�~�����[�V���������{���܂����B
�@�[������͏��h�����ł���Ð��N�i�@�B�H�w�ȂS�N�j�̍��}�ƂƂ��ɁA�}�����Q�K��H������Ђ���������
�Ƃ����z��ŁA�������E���P�����s������A�����P���E���ΌP�������{���܂����B
�@�Q���҂͋v���čL����h�{�������̐�����w���ɔM�S�Ɏ����X����ȂǁA�h�Ђɑ���ӎ������߂Ă��܂����B
 |
 |
 |
���H�V�~�����[�V�����E���ΌP���̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�w�����ɂĘa�H��@�u�K����J��
�@
�@�P�O���P�R���A�w�����H���ɂāA�a�H��@�u�K����J�Â��܂����B
�@���̍u�K��́A�����ւ̐H�����ϑ����Ă��銔����Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂āA�����Q�R�N�x����J��
���Ă�����̂ŁA���Ђ̒��������u�t�Ƃ��Č}���A���c���������͂��߂Ƃ��鑽���̃X�^�b�t�ɂ���|����ꂽ�{�i
���Η��������\����@�ɂȂ���A���{�����̊�{�I�Ȃ��ču�K���܂����B
�@�Q���҂́A���w���̂T�����܂ނQ�O���̗����i�}�����P�V���A�����R���j�ŁA���̎g�������̎������Ȃǂ�
��{�I�ȍ�@����A�G�߂̏{�̐H�ނ������������{�����̓`���₵������܂łɂ킽��A���{��g�ɕt���邱�Ƃ�
�ł��܂����B
 |
 |
 |
�a�H�u�K��̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�����Q�T�N�x�����n��R���ꎖ���E���i�ے��⍲���j���C����J��
�@
�@�����n��R����̘A�g���Ƃ̈�Ƃ��āA�����Q�T�N�x�����n��R���ꎖ���E���i�ے��⍲���j���C��A�v����
����łX���Q�T���ɊJ�Â���܂����B
�@�{���C�́A�����Q�Q�N�x���玖�����E����Ώۂɖ��N���{���Ă�����̂ŁA����͉ے��⍲��ΏۂɁA�\�́E�ӎ�
�̌���ƍ���Ԃ̌𗬂�}�邱�Ƃ�ړI�ɁA�L������A�k��B����y�ыv���č���̉ے��⍲�S���i�X���j���Q����
�܂����B
�@���C�ł́A���N�R���ɋv���č�����N�ސE�����O���������̏������ꎁ���u�t�Ɍ}���āA�u�@�l����P�O�N���o��
�������̖�E�҂Ɋ��҂���Ă���\�͂Ƃ́v�Ƒ肵���u�b�Ɓu���ǂ��Ă��镔���̂���ׂ��g�D�͂��������邽�߂�
�d�_�����v���e�[�}�ɂ��ăO���[�v���[�N���s���܂����B
�@�u�t�̖L�x�Ȓm���ƌo���ɗ��ł����ꂽ�u�b�ł́A�����X���M�S�Ƀ�����������肳����ɂ��Ȃ�����ʂ���
���������A�O���[�v���[�N�ł́A�E���ɕK�v�Ȕ\�͂�������ɂ��ĔY�݂����L���������Ȉӌ��������s���
�܂����B
�@���ߊ���Ƃ��ču�t����A���F�����������͓I�ȍ�������Ƃ��Đ����c�邽�߂ɂ͑g�D�͂����߂�H�v����������
���邱�ƁA���̂��߂ɂ͕⍲�Ƃ��āu���E���̐��������߂��g�Ƃ��āA�ϋɓI�Ȏw���E������S�����ė~�����B�v
�Ɗ��҂����߂����t���q�ׂ��A���C��͏I�����܂����B
 |
 |
 |
�����E�����C��̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�����Q�T�N�x�e�N�m�l�b�g�v���Ē莞������J��
�@
�@�X���Q�S���A�����Q�T�N�x��P��e�N�m�l�b�g�v���ė�����A�莞����A�m�I���Y�t�H�[�����y�ь𗬉�J�Â�
��܂����B
�@�e�N�m�l�b�g�v���ĂƂ́A�v���č���ɂ��n��A�g�����̈�w�̋�����}��ړI�ō�N�P�O���ɔ��������g�D�ŁA
�������y�э��ꌧ�ɂ�����Y�Ƃ̍X�Ȃ锭�W��n��̐l�ނ̈琬����ڎw���Ă܂��B
�@�莞����ł́A�ΊۖΕv�e�N�m�l�b�g�v���ĉ�i���ăS���В��j�A��c�F�Z���̈��A�̌�A����c���ƂȂ�A
�����̑I�C�A�����Q�S�N�x���ƕi�āj�A�����Q�S�N�x���x�i�āj�y�щ�v�č����R�c����A���Ăǂ��菳�F
����܂����B�����āA����n���T�O���N�L�O���Ƃւ̋��͕��тɑ�P�X��V���|�W�E��in�v���Ăւ̋��͂��܂�
�����Q�T�N�x���ƌv��i�āj�y�ѕ����Q�T�N�x���x�\�Z�i�āj�̒�Ă�����A����������Ăǂ��菳�F����܂����B
�@�莞�����A���ƌv��̈�Ƃ��ĕ����Q�T�N�x�m�I���Y�t�H�[�������J�Â���܂����B�v�ێR���ٗ��m�A���M�C
�ٗ��m�A����G��ٗ��m�A�|�ۊދZ�p�m�̂S�����p�l���X�g�Ɍ}���A�u�m���̎����Ă悤�i���肠�鎖�Ɖ��Ɍ����āj�v
�Ƒ肵���ᔭ�\���s���A���̌㓡�c��r�Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[�����R�[�f�B�l�[�^�[�ƂȂ�A�p�l���X�g�ƎQ����
�Ƃ̈ӌ��������s���܂����B
�@�����ڂ��s��ꂽ�e�N�m�l�b�g�v���Č𗬉�ł́A�����Ƃ̑�\�҂Ƌv���č��ꋳ�E���Ƃ��ӌ��������s���A
����̒n��A�g�̑����ƂȂ�܂����B
 |
 |
 |
�e�N�m�l�b�g�莞����̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�Q�O�P�R����\�[���[�{�[�g���ŏ��D�����Z���֕�
�@
�@�W���R������W���S���ɂ����Ė���s�ŊJ�Â��ꂽ�Q�O�P�R����\�[���[�{�[�g���i���[�X�w���̕��j�ɋv����
���ꎩ�R�G�l���M�[�������D���Q�`�[�����o�ꂵ�A�����P�`�[�������D�����ʂ����܂����B
�@���̑��́A���z�G�l���M�[�̗L�����p�Ɛ��ӊ��̕ۑS��ڎw���A�P�W�N�O�ɃX�^�[�g���A���N�͊w���̕��ɋ�
�B�E�R������Q�V�`�[�����G���g���[���Ă��܂����B
�@�����́A�^�C���������\�I���[�X�łQ�ʂɂ��A�����A�\�I�������������`�[������ĂɃX�^�[�g���錈��
�ŋt�]�D����_���Ă��܂������A�c�O�Ȃ���A���������͈��V��̂��ߒ��~�ƂȂ�A�\�I���ʂ��ŏI���ʂƂȂ�܂����B
�D����_���Ă����Ö�啔���i�ޗ��H�w�ȂS�N�j�͌ږ�̌F�ی��j������H�w�ȏy�����ƂƂ��ɏ�c�F�Z����
��܂̕��s���A���N�����͂ƁA�\�z�E����������Ă��܂����B
 |
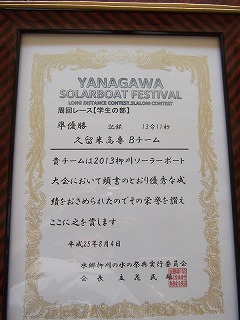 |
 |
���D���̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�������������R���ꍇ���w�Z��������J��
�@
�@�v���č���y�їL������A�k��B����̕��������̍����R���ꂪ�A�X���Q�W���i�y�j�ɁA�����s�̓V�_�r���ō���
�w�Z��������J�Â��܂����B
�@���̍����w�Z������́A���������̂R���ꂪ�A�g���āA�����s�y�ю��ӎs�����̒��w���A�ی�ҁA���w�Z�������A
��ΏۂɊJ�Â������̂ŁA���̒n��ɂ����鍂��̒m���x���A�b�v������ƂƂ��ɁA�u��Ҋm�ۂ�ړI�Ƃ��Ď��{��
��܂����B
�@�����́A��P�X�O���̎Q���҂��K��A�R����̍Z���A�����厖�ق����E�����o�Ȃ��A�S�̉�ō���S�ʂ̐�����
��������A�e����ɕ�����Čʂ̐������s���܂����B
�@�܂��A�����ł́A�F�{����E�����ۍ���E�s�鍂��E����������E���ꍂ��̋�B�n��̂T����ɉ����A���N��
�V���ɑ哇�E�L���E�|��̒����E�l���n��̂R���D���ꂩ����w�Z�Љ�u�[�X�̏o�W������A�Q���������w���̃A��
�P�[�g�ɂ́A�u�e����̏�����x�ɕ������Ƃ��ł��ėǂ������A����̓����𗝉��ł����v�Ȃǂ̈ӌ�����������
���܂����B
 |
 |
 |
�����w�Z������̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�O���l�u�t�ɂ��p��ł̐����Ƃ��J��
�@
�@�{�Z�ł́A�W���Q�X���i�j�E�R�O���i���j�̃T�}�[���N�`���[�ł̓��ʍu�`�y�тX���Q���i���j�̐����n���ƃg�s�b�N�X
�ɂ����āA�A�����J���O���E�Z���g���C�X�s����u�t�������A�p��ł̐����Ƃ��J�Â��܂����B
�@���ʍu�`�i�ΏہF��U�Ȋw���j�ł́ABiotechnology(DNA��Protein)International Edition��p���āAAnalysis of
Protein Structure Using RasMol��Analysis of DNA Structure Using RasMol�̂Q�͂̍u�`���s���A��u������U
�Ȋw������́u�p��ł̐����Ƃ��āA�v���Ă����قǓ���Ȃ��A���M�ɂȂ������B�v�Ƃ̃R�����g������
�����B
�@�܂��A�����n���ƃg�s�b�N�X�i�ΏہF�{�ȂR�N������T�N���j�ł́A�Z���g���C�X�s�ƃZ���g���C�X�R�~����e�B�[�J���b�W
�̏Љ��n�܂�A�o�C�I�x���`���[�̖u���ƈ�`�q�g�݊����H�i�ɂ��Ă̍u�`���s���܂����B�u�`�I����́A
�ʂ̎���Ɖ�b�Ƀ`�������W�����w�������l������A���̊O���l�u�t�ɂ��p��ł̎��ƂƂ������̎��݂ɂ��A
�w���̉p����Ƃɑ��郂�`�x�[�V�������オ�����悤�ł����B
 |
 |
 |
�O���l�u�t�ɂ����Ƃ̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
��P�X��X�[�p�[�R���s���[�e�B���O�R���e�X�g�iSuperCon2013�j�ł̗D�����Z���֕�
�@
�@�W���P�X���i���j����W���Q�R���i���j�ɂ����ĊJ�Â��ꂽ��19��X�[�p�[�R���s���[�e�B���O�R���e�X�g(SuperCon2013�A
��ÁF�����H�Ƒ�w�E����w�j�ɂ����āA�v���č����imishinn�`�[���i�D�z��l�N�A�v�ۓc�˕��N�A�g�c����N�N
�������������H�w�ȂQ�N�A�v���O���~���O���{���j���A���D�����ʂ����A��c�Z���Ɋ��т̕��s���܂����B
�@�{�R���e�X�g�́A�d�]�b�q���Ƃ��Ă�A�X�[�p�[�R���s���[�^��ōs�����Z���E���ꐶ(���Z�̑����w�N)�Ώۂ�
�v���O���~���O�R���e�X�g�ŁA�S������\�I��ʉ߂����Q�O�`�[�����{�I�֏o�ꂵ�܂����B
�@�{�I�ł́A�����H�Ƒ�w�Ƒ���w�̉����l�b�g���[�N�Ō��сA�����H�Ƒ�w�̒�����^�X�[�p�[�R���s���[�^
�V�X�e��TSUBAME2.0���A����ꂩ��g�p���ĔM�킪�J��L�����A�v���č���`�[���������O�̋Z�\�ƃ`�|����
�[�N�Ō������_�ɋP���܂����B
�@�Q�������w���́u�T���ԁA�R�l�̃`�[���ł��̑��Ɏ��g�ݔ��ɗǂ��o�����ł����B��ς��������y���������B�v
�ȂǂƊ��z���q�ׁA�u����̗D���ɖ��������A����v���R����p�\�R���b�q���A���I�����s�b�N�Ȃǂ̑��ł�����
���c���Ă��������B�v�ƍ���̕���������Ă��܂����B
 |
 |
 |
�D���y�ё����̗l�q
�@
����25�i2013�j�N�x
�@�B�E�d�C�V�X�e���H�w��U�Q�N�c���F���N���Z���֓����擾���
�@
�@�X���P�Q���i�j�A�c���F���N�i�@�B�E�d�C�V�X�e���H�w��U�Q�N�j���A�����u���s�⏕��v�ɂ���������擾��
���āA�w�������ɓ����������A���c�@�B�H�w�ȋ�����ƂƂ��ɁA��c�Z���֕��܂����B
�@�{�����́A�c���N����U�Ȃ̎��Ɓu�n���H�w�����v�̒��Ŕ��Đ��삵�A��������U�Ȃ̎��Ɓu�Y�ƍ��Y�����_�v
�̒��œ����o��������������̂ŁA�{�����ɂ�蕽���Q�S�N�x�p�e���g�R���e�X�g��w����œ����o��x���Ώێ�
�ɂ��I��A�ٗ��m�̎x���̂��ƂV���ɓ����o�^���������܂����B
�@��c�Z�����炨�j���̌��t��������ꂽ���ƁA��J�����_��q�˂�ꂽ�c���N�́A�A�C�f�A�ݏo���_�������A
���s�⏕��̃A�C�f�A�ɂ��ǂ蒅���܂łɁA�w�������搶�����Ă����A�C�f�A�����x���p�����ꂽ�G�s�\�[�h���
�I���Ă��܂����B
�@�p�e���g�R���e�X�g���҂œ����擾�����͖̂{�Z�ł͂R�l�ڂƂȂ�܂����B
 |
 |
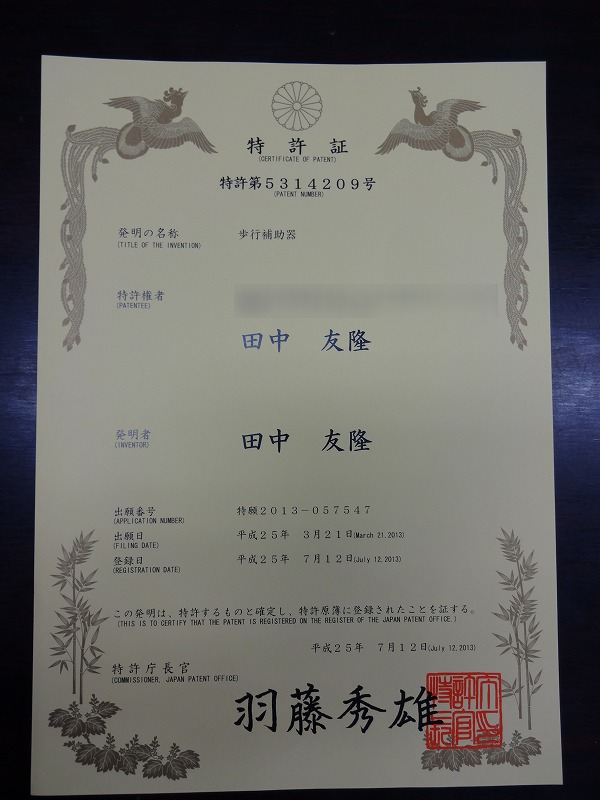 |
�����擾�����l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�C�m�x�[�V�����E�W���p���Q�O�P�R�ɎQ��
�@
�@�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�ƐV�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�i�m�d�c�n�j��ẪC�m�x�[�V�����E�W���p���Q�O�P�R
�`��w���{�s�`���A�W���Q�X���i�j�A�R�O���i���j�ɓ����r�b�O�T�C�g�ɂĊJ�Â���܂����B
�@���̃C�x���g�́A�䂪���̎Y�w�A�g�ɂ��C�m�x�[�V�����̑n�o�𐄐i���邽�߂ɁA���𓌋����ۃt�H�[��������
�瓌���r�b�O�T�C�g�Ɉڂ��A������w������S�O�O�����錤�����ʂ��W������A�����ő�K�͂̎Y�w�}�b�`���O
�̏�ƂȂ�܂����B
�@�v���č��ꂩ��́A�u�V���R�[���S��+�{�[���`���C�i���큁�V�e�[�u���E�F�A�yON THE TOPs�z�v�Ƃ����e�[�}��
���c��r�����i�@�B�H�w�ȁj���o�W���A�g�p���l�̍����V���R�[���S���̊J���ɂ��Đ��ʕ��ƃp�l�����g���ďЉ�
���܂����B
�@�܂��A���ł́A��Ƃ̏o�W�҂Ƃ��ĎQ���������Ɛ��ɉ����A���̃C�x���g�̏���m�������Ɛ��̎p������A����
������̋ߋ��Ƌ��Ɋ����ȏ����������s���܂����B
 |
 |
 |
�C�m�x�[�V�����W���p���Q�O�P�R�̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
����̌����w���J��
�@
�@�W���P�X���i���j�y�тQ�O���i�j�ɒ��w����ΏۂƂ����u����̌����w�v���J�Â��܂����B���̑̌����w�́A�����ʂ�
�ċv���č���̂T�w�ȋy�ш�ʉȖڂɊւ�������E���K��u�`�����ۂɑ̌����A�{�Z�ւ̗�����[�߂Ă���������
�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ŁA����ԂŌ����O�̂P�S�O�Z����T�X�T���̎Q���҂�����܂����B
�@�H�v���Â炵�����Ƃɑ��āA�Q���������w������́A�u���ꂪ�ǂ������Ƃ���Ȃ̂��m�邱�Ƃ��o�����B�v�A�u�搶
��ݍZ�������J�ɋ����Ă��ꂽ�̂ŁA������Ղ������B�v�A�u�ʔ������Ƃ���������������āA�������N�����B�v
�Ȃǂ̐���������A�D�]���܂����B
�@�܂��A�Z���ɐ݂����i�H���k�R�[�i�[�ł́A�ی�҂��狳���������̎��₪���A�ی�҂̕��X�ɂƂ��Ă�
�����ƒ��ڑΘb�ł���ǂ��@��ƂȂ�܂����B
 |
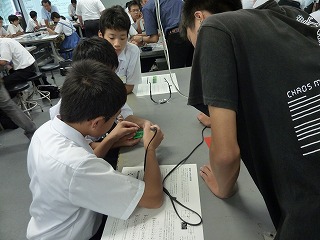 |
 |
�̌����Ƃ̗l�q
�@
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�w������S�ƂȂ��čZ�����|�����{
�@
�@7��26���i���j�A�w������S�ƂȂ��čZ�����|�������s���܂����B
�@�w������������v��x�Ɩ��t����ꂽ���̍s���ɂ́A�\�t�g�e�j�X���D��A�o���[�{�[�����A�o�h�~���g�����Ȃ�
�̃N���u����Q��������A�j�q�͒��֏�̐����E���|����u���]�Ԃ̓P���A���q�͏��q�X�ߎ��̐����E���|���s����
�����B�r���Œʂ�J�ɑ����Ȃǂ̃A�N�V�f���g������܂������A�������|�������I���܂����B
�@�Z�����|�����̒��S�ƂȂ����w����̌Ð�Ȉ�N�i�d�C�d�q�H�w��4�N�j����́u���̊�����ʂ��āA�����̊w�Z
�����������̎�ł��ꂢ�ɂ����т�m��܂����B���������������́A���Б����Ă��������Ǝv���܂��B�v�Ƃ̐�����
�����܂����B
 |
 |
 |
�Z�����|�̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�w�����ɂđ�S���u������J��
�@
�@�V���S���i�j�A�w�����ɂđ�S���u����u���w���I���ā`�C�O���w����w���Ɓv���J�Â��܂����B
�@�I�[�X�g�����A�̃L�����x����w�ł̖�P�N�Ԃ̌�w���w����A�������R�c�Y��N�i�����H�w��U�Q�N�j�A��P�O�J���Ԃ�
�A�����J�̌������Z�ւ̌������w�v���O�����ɎQ��������㗯������i������H�w�ȂR�N�j�ƕ����ʂ���i���R�N�j���A
���ꂼ��̗��w�̌������ƂɁA���t��ٕ��������ɋ�J�����o���ȂǁA���w��̎ʐ^�������Ȃ���u�����s���܂����B
�@�܂��A��N�W���ɁA�n���T�O���N�L�O���Ƃ̈�Ƃ��āA�I�[�X�g�����A�̃V�h�j�[��K�₵�����O�r�[���̊w�����A
���ێ�����X�|�[�c�����Ȃǂ��Љ����A�[�������u����ƂȂ�܂����B
 |
 |
 |
��S���u����̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�A�E���������Z�~�i�[���J��
�@
�@�V���P�V���i���j�A�{�Z�ł͕�������҂����ƃT�|�[�g�Z���^�[�̋��͂̉��A��ɖ{�ȂS�N����ΏۂƂ����u�A�E����
�����Z�~�i�[�v���J�Â��܂����B
�@���̃Z�~�i�|�́A�w���̏A�E�y�яA�E�����ɑ���ӎ������߂邱�Ƃ�ړI�ɁA���N�J�Â��Ă���A��P�Q�O����
�w�����Q�����܂����B
�@����͏A�E�����̈Ӗ��A���ȕ��͂Ɗ�ƕ��͂̏d�v���Ȃǂ̍u�b�̂ق��A�u�b�̓r���ɐ݂���ꂽ�u�����Ӗ��v��
�l���鎞�Ԃł́A�Q���Ҏ��炪�ӌ����܂Ƃ߁A�ق��̎Q���҂ƈӌ�����������Ȃǂ̔��\���s���܂����B
�@�P���ԂR�O���قǂ̎��Ԃł������A�Q�������w���͔M�S�Ƀ��������ȂǁA�ԋ߂ɔ������A�E�������ӎ����čŌ�
�܂Ő^���ȕ\��ōu�t�̘b�ɕ��������Ă��܂����B
 |
 |
 |
�A�E���������Z�~�i�[�̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�w�����ÂŃ��[�_�[���C����J��
�@
�@�U���Q�U���i���j�A�w�����Âɂ��A���[�_�[���C����J�Â��܂����B�i��i�s�͊w��������s�ψ���O�ǒ�
�ł�������m�N�i�d�C�d�q�H�w�ȂS�N�j�����߁A�u���ƃ��[�N�V���b�v�̓\���Ői�߂��܂����B
�@�܂��u���ł́A�{�Z�̗����y�������u���[�_�[�ɋ��߂��鎑���v�ɂ��āA�\�t�g�o���N�i�v���싅�j�̑I��̋N�p�@����
������A�}���\���̍����I�����Ă����o�ē�v���싅�̏���I�����Ă����ˍ��Z�̎R���ē̌��t�����p����Ȃ�
�킩��₷���u�`���s���܂����B
�@���ɊJ���ꂽ���[�N�V���b�v�ł́A�Q���ҁi�S�Q���j���Z�̔ǂɕ�����āA�u���[�_�[�ɕK�v�Ȃ��͉̂����H�v�A
�u���ꂪ�ł��郊�[�_�[�͑f���炵���v���e�[�}�ɔM���b�������A���ꂼ��̔ǂ��l���\���܂����B
�@�R�����Ƃ��āA��c�Z���A�a���厖���Q�����A�e�ǂ̔��\�ɑ��A���������D�����R�����g���q�ׂ��܂����B
 |
 |
 |
���[�_�[���C��̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�w�����ő吴�|�E�o�[�x�L���[�p�[�e�B�[���J��
�@
�@�U���R�O���i���j�A��������S�ƂȂ�A�w�K���◾����A�����A�L���A�K�i�A�S�~�u����ȂǗ��������̋��L�X�y�[�X
�̑吴�|���s���A�V�N�x���痭�܂��Ă����S�~��Еt���邱�Ƃ��o���܂����B
�@���|�I����́A�w�����H���ɂė����H�Ɩ����ϑ����Ă���(��)�������{�Ђ̋��͂āA�����ψ����̓��c�N
�i�@�B�H�w�ȂS�N�j�̎w���̉��A�o�[�x�L���[�p�[�e�B�[���J����A���w���ɂ��}���[�V�A���o�[�x�L���[��
�Љ���ȂǁA��P�S�O���̗������y�����ЂƎ����߂����܂����B
 |
 |
 |
�o�[�x�L���[�p�[�e�B�[�̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�w�����ɂđ�R���u������J��
�@
�@�U���Q�U���i���j�A��R���u����u���w���ɂ��ꍑ����`�ٕ��������̂��߂Ɂv���w�����ŊJ�Â��܂����B
�@�o���O���f�V���̗��w���C�������N�i�ޗ��H�w�ȂR�N�j�ƁA�����S���̗��w���i���T�[����i�������p���w�ȂS�N�j
����ꍑ�̕����ɂ��ďЉ����܂����B
�@��A�W�A�̃o���O���f�V���̂U�̋G�ߋ敪�i���{�̎l�G�ɔ~�J�A�ӏH��������j�⒆���A�W�A�̃����S���̗V�q��
�̐����Ȃǂ��Љ��A��P�Q�O���̎Q���҂���́A�����ٍ������̌�����[�߂邱�Ƃ��ł����Ƃ̐������A
�Q�l�̗��w���ɑ��āA�u�o�C�l�b�^�v�y�����S����Łu���肪�Ƃ��v�z�ȂǂƊ��ӂ̌��t���q�ׂ��܂����B
�@������@�Ɋw���ł̍��ی𗬂�����w�i�W���邱�Ƃ����҂���܂��B
 |
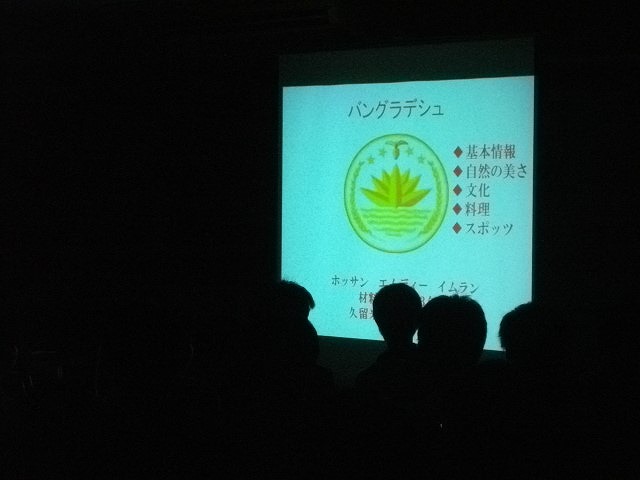 |
 |
�����u����̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�w�����ɂđ�Q���u������J��
�@
�@�U���P�X���i���j�A��Q���u����u���w���ɂ��ꍑ����`�ٕ��������̂��߂Ɂv���w�����ŊJ�Â��A�}���[�V�A�����
���w���T������i�@�B�H�w�ȂS�N�j�A�V���t�����N�i�d�C�d�q�H�w�ȂR�N�j�A�C���}���N�i�@�B�H�w�ȂR�N�j����ꍑ�̕�����
���Ă̏Љ����܂����B
�@��P�Q�O���̎Q���҂���́A�g�߂Ȉٕ���������[�߂邱�Ƃ��ł��A�܂��A��ϖʔ����A�L�Ӌ`�Ȏ��Ԃł��������Ƃɑ��āA
�R�l�̗��w���ɁA�u�e���}�J�V�v�y�}���[�V�A��Łu���肪�Ƃ��v�z�Ɗ��ӂ̌��t���q�ׂ��܂����B
 |
 |
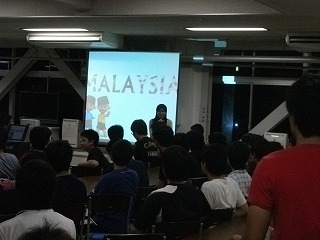 |
�����u����̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�w�����ɂăe�[�u���}�i�[�u�K����J��
�@
�@�U���P�U���i���j�A�w�����H���ɂė����H�Ɩ����ϑ����Ă���(��)�������{�Ђ̋��͂āA�m�H�̃R�[�X������
��{�I�ȍ�@�ɂ��Ẵe�[�u���}�i�[�u�K����J�Â��܂����B
�@�Q�������R�O���̗����i�}�����Q�W���A�����Q���j�́A�X�[�c�A�l�N�^�C���͊w�����𒅗p���A���Ȃ��痣�Ȃ܂ł�
��������J�e�����[�i�i�C�t�A�t�H�[�N�Ȃǁj�̎g�������K���Ȃ���A���̓T�[�����̃��j�G���A���̓|�[�N�\�e�[��
���S�Ƃ����{�i�I�ȃR�[�X���������������܂����B
 |
 |
 |
�e�[�u���}�i�[�u�K��̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
���؏܍�ƈ��������Y���v���č���}���ق}������
�@
�@���؏܍�Ƃł���v���č���̑��Ɛ��ł�����������Y�����{�Z�}���قɁA�T�C�����莩���R�R��i�S�O�����A
�T�����Ɋ���܂����B����́A���N�P���ɁA�����������y���R����̊G�t�E���J�쓙����`�������j�����w�����x��
���؏܂���܂������Ƃɔ����A�{�Z�w�������w�ɋ����������A�L������ƖL���ȋ��{��g�ɂ��邱�Ƃ��肢��
���ꂽ���̂ł��B
�@�{�Z�}���قɂ͈��������Y�R�[�i�[��ݒu���Ă���A���؏�ܑO��������ꂽ�{���܂߁A�R�[�i�[�ɔz�˂��ꂽ
�}���͂R�T��i�X�V���ƂȂ�܂����B
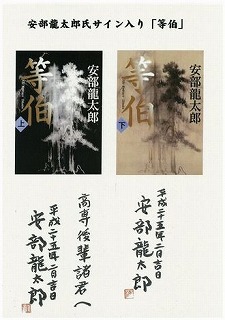 |
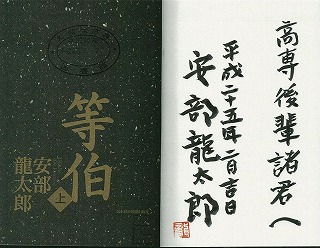 |
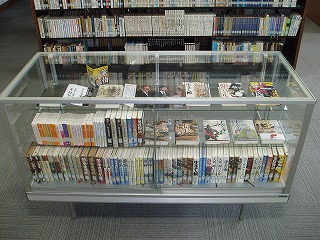 |
���ꂽ�{�Ɛ}���ٓ��ɂ�����������Y�R�[�i�[
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�����}�C�X�^�[�����w�Z�i�؍��j�Ƃ̊w�����ی𗬍s�����J��
�@
�@�T���Q�O���i���j�ߌ�A�����}�C�X�^�[�����w�Z�i�؍���c�s�j�̐��k�y�ш������E���̑����P�Q�U�l���{�Z��K��A�{
�Z�w���Ƙa�₩�Ɍ𗬂��s���܂����B����́A�����}�C�X�^�[�����w�Z�ɂ�����D�G�ȃO���[�o���Z�p�l�ނ̗{����
��Ƃ��čs���鍑�ی𗬍s���ŁA��N�x�Ɉ�����������łR��ڂƂȂ�܂����B
�@���E�Ŋ��邱�Ƃ����҂���Ă���{�Z�w���ɂƂ��Ă��A�H�ƋZ�p���w�ԓ�����̊C�O�̎�҂Ƃ̌𗬂͋M�d��
�̌��ƂȂ�܂����B
�@���ی𗬍s���́A�{�Z�w�����\�̏��Y�@�g����̎i��Ŏn�܂�A��c�Z������̊��}�̈��A�A�L�O�i�������s��
����A�|�����S���Ƀ��j���[�A�������}���فA���������̎{���w���s���܂����B���̌�A���Z�Q���ґ�\�ɂ��
�f���������Ă̊w�Z�Љ�s���A�̈�قł͖{�Z����_���X���ɂ��X�g���[�g�_���X�A�����}�C�X�^�[�����w�Z��
���k����̓_���X��̂̃p�t�H�[�}���X����I����܂����B�܂��A���Z�����̂S�`�[���ɕ�����Ă̍j�������s���A�e
�r��[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�Ō�ɁA�����}�C�X�^�[�����w�Z�C�E�X������������ӎ����q�ׂ��A���ی𗬎��Ƃ͏I�����܂����B
�@
|
|
|
|
�{���w�ƍj�����̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�n�k�ƉЂ�z�肵���h�Б����P�������{
�@
�@�{�Z�ł́A�T���Q�Q���i���j�ɋv���Ďs���h�����w���̉��A�k�x�T���̒n�k�ɔ����A�Ђ����������Ƃ̑z��Ŗh��
�����P�����s���܂����B���̌P���ł́A�n�k��������В��܂ł̈�A�̗�����V�~�����[�g���A�w���⋳�E����
�h�Ύv�z�̕��y����э��g��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ŁA�w���Ƌ��E�����킹�Ė�P�P�O�O�����Q�����܂����B
�@�P���ł́A�Җ{����������c���Ƃ����E���ɂ�鎩�q���h�c�����������ƂƂ��ɁA�����̗U���ɂ��w���̃O��
�E���h�ւ̔��v���ɍs���܂����B
�@���P���I����́A���h�����ɂ����Ί�̎g�p���@�i�s�m�L�I�����t�E�E�E�y�s�z�����C�y�m�z�Y�������C�y�L�z����
�i�����j��u���C���o�[���y�I�z�i���j���j�̐���������A�w���y�ы��E����\�҂ɂ����Ί푀��P�����s���܂����B
�@�Ō�ɏ��h�����ɂ��P���S�̂̍u�]�Ə�c�Z������̈��A�������āA�����I�����܂����B
�@
|
|
|
|
�h�Б����P���Ə��Ί푀��P���̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�v���čH�ƒZ����w��S�����Ɛ����{�Z��K��
�@
�@����T���Q�P���i�j�ɁA�{�Z�̑O�g�ł���v���čH�ƒZ����w�̋@�B�ȑ�S�����Ɛ��̂V�����{�Z��K��܂����B
�@����̖K��́A�Z�呲�ƌ�T�O�N���_�@�ɕ�Z��K�ꂽ���̂ŁA��s�́A�@�B�H�w�Ȓ��������A��Ï����̈ē���
���A�L�O�فA�@�B�H�w�Ȃ̊e�������A�V���ɉ��C���ꂽ�}���ق����w������A��c�Z�����犽�}���A�ƍ���̌���
�ɂ��Đ������s���܂����B���̌�̍��k�̒��ł́A�V�Ԏ��Ԃ��Ȃ��l�ߍ��܂ꂽ���̂��Ƃ�n���̍H�ꌩ�w��
�s�����ہA�����]�ƈ����犽�����オ�������ƂȂǂ��A����������I����܂����B���ɂ͂T�O�N�Ԃ�ɕ�Z��K�ꂽ����
�����A�����͎ʐ^�ł��������Ȃ��v���Ďs�⏬�X��n��̗l�q�ɉ����ߋ���Ǒz�����Ȃ���A�v���o�b�ɉԂ�
�炢�Ă��܂����B
�@
|
|
|
|
���k�̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�w�����ɂĕ����u������J��
�@
�@�w�����ł́A�T���P�T���i���j�Ƀ^�C�ɂ���L���O�����N�b�g�H�ȑ�w���J�o���Z���w���̃N���|�[���E�E�H�����p����
�����ɂ���P���u������J�Â��A��T�O���̗������Q�����܂����B
�@�N���|�[�������́A���؏y�����i������H�w�ȁj�Ƃ̔l�W�����q�����Ɛ�������Ԗ@��p�����^�C������
���̔F���Ɋւ��鋤�������̂��߁A�T���V���`�T���R�O���̊��ԁA��������Ă��܂��B
�@�����u����ł̓^�C�̔��������R�A�������@�≤�{�Ȃǂ̗��j�I�������A���̍ՓT��H���Ȃnj���̐������i�̃X
���C�h��A�L���O�����N�b�g�H�ȑ�w�j�l�h�s�̃r�f�I����f����A�p��ł̍u���⎿�^�������s���܂����B
�@�܂��A�N���|�[�������́A���P�U���i�j�ɍZ������K��A��c�Z���Ɉ��A�ƋL�O�i�̑�����s���܂����B
�@
|
|
|
|
�����u����̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�w�����ɂĕ�̓����Ӄf�[�����{
�@
�@�w�����ł́A�T���P�Q���i���j�ɁA��������������S�ƂȂ�A�����̐H����ی��q���̎w���A�e��u�K��ł̌�
�C�Ȃǂő�ς����b�ɂȂ��Ă���w�����H���̏]�ƈ��ɑ��āA�����̊��ӂ̋C������\�������������̉Ԃ�
�u�[�P�Ɗ����̐F�����v���[���g���܂����B
�@
|
|
|
|
|
|
|
|
��̓����Ӄf�[�̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�w�����ɂĕی��q���u�K��ƐH�����k����J��
�@
�@�w�����ł́A�T���X���i�j�Ɋ�����Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂ɂ��A�ی��q���u�K��J�Â���܂����B
�@�����P�K�̗��w���p�L�b�`���A�Q�K�̕�H���𒆐S�ɁA���~�e�X�^�[�Ƃ��������x�𑪒肷������g���A�q������
�����{���܂����B
�@�Ό��ɂ����̑O��ɂ����鐴���x���r�����f�[�^���ʂ������ꂽ�����B�́A������H���O�����łȂ��A�펞�A
�����ɂ��Ă������Ƃ̕K�v�����w�т܂����B
�@���ꂩ��C�����㏸���Ă����ɔ����A�H���ł̊댯�����������邱�Ƃ���A���܂߂Ȏ�Ƒ|���̗�s����ł�
��Ƃ̎w���E����������܂����B
�@���̌�A����������ƐH���W�҂̍��k����J�Â���A�e�[�u���}�i�[�u�K��̘b���������s���܂����B
�@
|
|
|
|
�ی��q���u�K��ƐH�����k��̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�w�����ɂăw���X�`�F�b�N�L�����y�[�����J��
�@
�@�w�����ł́A�T���X���i�j�Ɋ�����Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂ɂ��A�w���X�`�F�b�N�L�����y�[�����J�Â��܂�
���B
�@�Q������������S�T���ɑ��āA�������̑����A���̌��N�x�̑���A�����_�o�E�������_�o�̑���ɂ��X�g���X
�`�F�b�N�Ȃǂ̃e�X�g�����{����܂����B�܂��A���茋�ʂ܂��āA���N�|�h�����N�̏Љ��A�Ԉ�����_�C�G�b�g�Ȃ�
�ɂ������H�������ւ̒��ӂȂǁA�H���ƌ��N�ɂ��ẴA�h�o�C�X���܂����B
�@���x�Ђ̒S���҂���A�u�����̐H���ɂ��Ē��ӂ��邱�Ƃ����N�ւ̉����ł��B�v�Ƃ̌��t������A������͉��߂�
�H���ɂ�錒�N�̑�����w�т܂����B
�@
|
|
|
|
�w���X�`�F�b�N�L�����y�[���̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�w�����ɂďt�̗��Ղ��J��
�@
�@�S���Q�O���i�y�j�ɁA���c�����ψ����i�@�B�H�w�ȂS�N�j�𒆐S�Ƃ��������ψ��ɂ��A�w�����ɂďt�̗��Ղ��J�Â���
�����B
�@�}�����Ƃ�������A���w���y�ё̌����������܂߂ĂP�U�O���̗������Q�����܂����B�����ɂ��̉J�V�ƂȂ�܂���
���A�O���[�v�ɕ�����Ẵh�b�a�{�[�������s���A�[������́A�e���g�̒��Ńo�[�x�L���[�p�[�e�B�[���s���܂����B
�@���ʁA���ЁA�w�N��w�Ȃ̕ǂ����z���āA�y�����𗬂��s�����Ƃ��ł��A����w�e�r��[�߂闾�ՂƂȂ�܂����B
�@
|
|
|
|
���Ղ̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
��B��w�Z�p�E�����{�Z�@�B�H��H������w
�@
�@�S���P�W���i�j�ɁA��B��w��w�@�H�w�����@�@�B�H�w����̋Z�p�E���P�U���ɂ��{�Z�@�B�H��H��̌��w�K
�₪����܂����B
�@���̖K��́A����ɂ�������K�̌�������ш��S����ɂ��Ă̈ӌ���������ȖړI�Ƃ������̂ŁA���߂ɘa
�猤���x���������犽�}�̈��A�Ɩ{�Z�̊T�v��������������A�Ίۋ@�B�H�w�ȋ�����W�Z�p�E��������K
�H����̋@�����Ɠ��e���ɂ��Ă̐������s���܂����B
�@�K�₵���Z�p�E������A�u����̎��K�̏[���Ԃ�Ɋ��S���܂����B�S���E���̋Z�\�̍����ɂ������܂����B�v�Ȃǂ̊�
�z���q�ׂ��A�{�Z�̎��K���e���Ċm�F����ǂ��@��ƂȂ�܂����B
�@
|
|
|
|
�H��H������w������Z�p�E��
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�w�����Ζʎ����J��
�@
�@�{�Z�ł́A�S���X���i�j�Ɋw�����̑Ζʎ����J�Â��܂����B
�@��{�����厖����u��炵�₷�����ƂȂ�悤�A������l��l���A�K�������������𑗂邱�Ƃ����҂���B�v�Ƃ̈��A
������A�܂��A���ї�����i�d�C�d�q�H�w�ȂS�N�j����u����ł������v���č���Ɋ����悤�A������͊��ʼn���
�������B�v�Ƃ̃G�[���������܂����B���̌�A�V����������̎��ȏЉ�◾���厖���E�����E���Ȃǂ̏Љ�����
�����B
�@����ŁA�}�����̓}���[�V�A�̃C���}���i�@�B�H�w�ȂR�N�j�A�C�������i�ޗ��H�w�ȂR�N�j�̂Q���̗��w���������ĂP�S�X
���A�����͂Q�W���ƂȂ�A�S�̂łP�V�V���̗������ƂȂ�܂����B
�@
|
|
|
|
�Ζʎ��̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�����Q�T�N�x���w�������s
�@
�@�{�Z�́A�S���W���i���j�ɕ����Q�T�N�x���w�������s���A�V�����Q�O�W���A�ғ����Q���i�������w���Q���j�y�ѐ�U�Ȑ�
�R�P�����}������܂����B
�@���ł́A���o�A�ی�ҋy�ы��E��������钆�A�{�Ȑ��A�ғ����A��U�Ȑ��̏��Ɉ�l�����O���ǂݏグ��ꂽ
��A��c�Z�������w�������܂����B�����āA�e��\�����c�Z���Ɂu�H�w���C������Ƌ��ɎЉ�̊��҂ɂ������Ƃ�
�����܂��B�v�Ƃ̐������ǂݏグ���܂����B�Ō�ɁA��c�Z������u�Z���t�E�w���v�̐��_�ŁA����Ŏ���̉\��
�ɒ��킵�Ăق����B�v�Ƃ̊��҂����߂�ꂽ�������q�ׂ��܂����B
�@���I����A�̈�ّO�̃��C���X�g���[�g�ł̓T�[�N�����U�Ȃǂ��s���Ă���A�ْ����Ă����V�����B�̊��������
�Ί�ɕς���Ă����l�q���������܂����B
�@
|
|
|
|
�����Q�T�N�x���w���̗l�q
�@
�@
����25�i2013�j�N�x
�}���ي����L�O���T���J��
�@
�@�{�Z�ł́A�ϐk���C���܂߂��}���ى��C�H�����������A�S���T���i���j�Ɋ����L�O���T���тɃI�[�v�j���O���w���
�J�Â��܂����B
�@�I�[�v�j���O�Z�����j�[�Ƃ��āA��c�Z���A�Óc�}���ْ��A���ؑ������Z���^�[���A���Y�w����y�ђ������Q�T�N
�x�{�ȐV������\�A�c�������Q�T�N�x��U�ȐV������\�̂U�l�ɂ��e�[�v�J�b�g���s���A�{�����A�w�K���A�ϐk��
�ˁA�V���ɐݒu���ꂽ�{�Z���Ɛ��̒��؏܍�Ɓu���������Y���v�̃R�[�i�[��}���`���f�B�A�����Ȃǂ����w���܂����B
�@
|
|
|
|
�L�O���T�ƌ��w��̗l�q
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�{�Z�@�B�H�w�Ȃ���16����{�@�B�w���B�x���܂����
�@
�@�{�Z�@�B�H�w�Ȃ́A�����Q�T�N�R���P�R���i���j�ɁA��B�Y�Ƒ�w�H�w���ɂčs��ꂽ�A���{�@�B�w���B�x����U�U
������ɂāA��P�U����{�@�B�w���B�x���܂���܂��A�\�����܂����B
�@���{�@�B�w���B�x���܂́A��B�E����n��ɂ�����@�B�H�w�Ȃ�тɋ@�B�H�Ƃ̔��W�Ɏ�����ƂƂ��ɁA�x����
���̈�w�̊�������}�邽�߁A�����A����A�Z�p�A���ی𗬁A�x�������A�n��U���Ȃǂ̕���ɂ�����Ɛт�ʂ��āA
��B�E����n��̋@�B�H�w�Ȃ�тɋ@�B�H�Ƃ̔��W�Ɋ�^�����l�܂��͒c�̂ɑ��Ď��^����Ă��܂��B
�@����̎�܂́A�{�Z�@�B�H�w�ȂɂāA�u3D-CAD/CAE�v��p�����@�B�v�\�͌���̂��߂̊w��������p������
���i���Ă��邱�ƂƁA���J�u���u�C���e�O�����Z�~�i�[�v���J�Â���ȂǎЉ�l�����Z�p����ɐϋɓI�Ɏ��g��ł���
���Ƃ�]�����ꂽ���̂ł��B
�@
|
|
|
�\����ƕ\���|
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�����Q�S�N�x���Ǝ��A�C���������s
�@
�@�{�ȑ��Ǝ��A��U�ȏC�������R���P�T���i���j�ɖ{�Z���̈�قɂ����ċ��s���܂����B��c�Z������{�ȑ��Ɛ��P�X�U
���A��U�ȏC�����S�T���ɑ��Ə؏��y�яC���؏������^����A�Z�������A���o���A�Ƒ����A���͌��l�ȕ��͋C�̒��A
�I�����܂����B�������s��ꂽ�\�����ł́A�w�Ɛ��їD�G�Ȏғ��ɕ\�����^����܂����B���T�I����s�s��J
����A�{�ȑ��Ɛ��y�ѐ�U�ȏC�����̖�o���j���܂����B
�@
|
|
|
|
���Ǝ��E�C�����Ƒs�s��̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�w�����r�W�l�X�}�i�[�u�K����J��
�@
�@�Q���Q�O���i���j�ɂc�P�����ɂāA�S�N���Ɛ�U�ȂP�N����ΏۂɃr�W�l�X�}�i�[�u�K����J�Â��܂����B�w�����H�Ɩ�
���ϑ����Ă���(��)�������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂A���Ђ̓c�� �������u�t�Ɍ}���A�Љ�l�Ƃ��Ă̊�{�I�ȗ�V��
�@�ɂ��ču�K���܂����B����́A�����Ɍ��炸�ʊw���ɂ��Q�����Ăт����A�W�Q���̊w�����Q�����܂����B
�@�r�W�l�X�X�[�c�̒����A�����V�̎d���A�h��Ȃǂ̐��������t�g���A���ڎ��ł̍�@�ȂǁA�u�`�Ɖ��K�`���Ŋw�т�
�����B�Q���҂���́A�u���̎����ɑ���Ȃ����̂���łƂĂ����ɗ������v�u�����w���Ƃ�Y�ꂸ�ɁA�̗p�ʐڂŊ�
�p���Ă��������v�Ȃǂ̊��z�����܂����B
�@
|
|
|
|
�u�K��̗l�q
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�{�ZOB���������Y���i���j�����Ɓj����Z�ɒ��؏�܂��
�@
�@�Q���Q�R���i�y�j�ɁA�{�Z�@�B�H�w�ȑ��̗��j�����Ƃł�����������Y�����A���؏܂̎�ܕɖ{�Z��K��܂�
���B�O���Ɏ�����I�����������ɁA��c�Z���A���O�r�[���ږ�Ŗ{�Z���O�r�[��OB�̍]�藾���厖�A����������
���ƃ��O�r�[��OB���̍��X�ؕq��������A�Z�����ŏj�ӂ��\����܂����B���̌�A�������́A���O�r�[��OB
����̊ő̈�ى��ɐݒu����Ă���A�������쎌�ɂ�镔�́u�}��̓m�v�����܂ꂽ���O�r�[���n���T�O���N�L�O
������w���A�O���E���h�ŗ��K���Ă������O�r�[���������サ�܂����B�����L���v�e���̎��s���m�N�i�@�B�H�w�ȂS�N�j
����A��܂̂��j���ɕ�����Ŋ������������O�r�[�{�[�������悳��A�������������������͂�ŕ��̂�������
�܂����B
�@���Z�����w�����ܕɕ�Z��K�₵�����z�ɂ��Đq�˂�ꂽ�������́A�u���؏܂���܂������Ƃ��Z��
�����������Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B�����ʂł��B�v�Ɠ����Ă��܂����B
�@�{�Z�K���A�������͓茴�v���Ďs���ɕ\�h�K�₵�A�����Đ����p�ق�K��A���݊J�Â���Ă���u���t�E��t
�̎���W�v�ŁA������̊G����ӏ܂��܂����B
�@
|
|
|
|
�K��̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�w�����ɂĕ����Q�S�N�x�����s�`���x�����{
�@
�@�w�����ł́A�����Q�P�N�x��藾���s�`�iTeaching Assistant�j���x�����{���Ă���܂��B�����s�`���x�Ƃ����̂́A��
�w�ӎ�����E���̏K���Â��E��w�N�ł̊�b�w�͌����ړI�Ƃ��A�㋉�����A�P�A�Q�N���̉�������Ώۂɕ�����
���āA�w�K��̗����𑣐i����Ƃ������̂ł��B
�@�قږ��T���j���Ɩؗj���̌ߌ�X������P�O���̊ԁA�w�����H���ɂčs���Ă���܂��B���t���߂�㋉���́A��
��V�̃{�����e�B�A�Ƃ��ĉ������̖ʓ|���݂Ă��܂��B�����́A�w�K�m�ɒʂ�����A�ƒ닳�t�ɏK������Ȃǂ̋@���
�����߂ɁA�s�`�̂悤�ȁu�w���l�w���v�͂ƂĂ��������Ă��܂��B�����́A���̂悤�ȓ��X�̒n���Ȋ�����ʂ��ď�����
���̐��_�����ł���A���̂悤�Ȍo���́A�Љ�ɏo�Ă�����傢�ɖ𗧂ł��傤�B
�@
|
|
|
|
���ɗ�ޗ����̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�؍��E����@�B�H�ƍ��Z�̊w�����{�Z��K��
�@
�@�P���Q�S���i�j�ɁA����i�`�����i���j�@�B�H�ƍ��Z�i�؍��E��c�s�j����w���P�W���y�ы����R�����A�{�Z��K�₵�A
�w���̎{�݂���K�@�퓙�̌��w���s���܂����B
�@���̓x�̖K��́A���{��Ƃ̍H���E�Ɛ��w�Z���̋���ے��E�i�H�̑I�ѕ��Ȃǂ��w�Ԃ��Ƃ�ړI�Ƃ����A����
�@�B�H�ƍ��Z�̊C�O�̌��w�K�̈�Ƃ��ė����̍ہA�ȑO����{�Z�̋���v���O�������ɋ����E�S�������Z��
��]�ɂ������������̂ł��B
�@��s�͏��߂ɒÓc���厖�Ɣn�z�����厖����̊��}���A�Ɗw�Z�Љ������A�W�҂Ɉē�����āA�H��H
���}���A�@�B�v�f�v�������Ȃǂ����w���A���K�@��₻���ōs���Ă�����Ɠ��e���ɂ��Đ�������
�����B
�@�ʖ����Ă̐����ł������A�w���B�͈�l�ɐ[�������ɕ�������A�������������@�B�̑O�Ŏv���v���Ɏʐ^���B
�����莿��𓊂��������肷��ȂǁA����ꂽ���Ԃł������A�ϋɓI�Ɋw��ł��܂����B
�@
|
|
|
|
���w�̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�����Q�S�N�x�w�������l�����J��
�@
�@�P���P�O���i�j�ɕ����Q�S�N�x�w�������l�����J�Â��A�Q�T���i�������w���R���j�̐��l���j�����܂����B�������\
���ē�������������j��������A���̌�A�c��N�i������H�w�ȂT�N�j���V���l���\���Ďӎ����q�ׁA�܂��u����
���琬�l�Ƃ��Ă̎��o�������Ċ撣�肽���B�v�ƕ��������܂����B
�@�]�藾���厖����́A�V���l�ւ̂��j���Ƃ��āA���������܂Ƃ߂��c�u�c�̉f���ɏ悹�āA�T�b�N�X�̉��t���v���[
���g����܂����B��N�����A�b�g�z�[���ȐS���܂鐬�l���ƂȂ�܂����B
�@
|
|
|
|
���l���̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�w�����ɂė��Ղ��J��
�@
�@�w�����ł́A�P�Q���P�T���i�y�j�ɗ��Ղ��J�Â��A���w�����܂߂ĂP�P�U���̗������Q�����܂����B�����ɂ��̉J�V�ł���
���A����������𒆐S�ɌߑO���̖݂��A�ߌ�̃{�E�����O���A�[���̃o�[�x�L���[�p�[�e�B�[�Ɗ��C����P���Ƃ�
��܂����B�O��t�̗��Ոȍ~�ɓ������������i�S�����̖�Q���j�������A���w�N�A����ɂ͐�y�E��y�Ƃ̐e�r��[��
�܂����B
�@
|
|
|
|
���������̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�{�ZOB���������Y���i���j�����Ɓj����P�S�W�؏܂����
�@
�@��P�S�W��i�����Q�S�N�x�������j���؏܁i���{���w�U�����Áj�̑I�l��P���P�U���ɊJ����A�{�Z�@�B�H�w��
��P�Q���i���a�T�Q�N�R���j���Ɛ��A���������Y���̍�i�ŁA���R����̊G�t�A���J�쓙������l���Ƃ��ē��{�o�ϐV
���ɘA�ڂ��ꂽ�u�����v���I��܂����B�����͖{�Z���ƌ�A�����s��c�旧�}���قŎi���Ƃ��ē����T�玷�M������
�����A�R�R�̂Ƃ��ɖ{�i�I�Ƀf�r���[����܂����B���؏܌��ƂȂ�̂́A�Q��ڂŁA���n�o�g�̗��j�����ƂƂ���
�͈ٗ�̎�܂ƂȂ�܂����B���E���ꓯ�S���炨�j���\���グ�܂��B
�@���\�����閾�����{�Z�ɂ́A�s�u��ނ��邽�߂ɓ����̋��F�⓯�����������Ă������O�r�[���W�҂��W�܂�A
�������쎌�ɂ�镔�̂����܂ꂽ���O�r�[���n���T�O���N�L�O��̑O�ŁA��܂���т����܂����B
�@���掮�͂Q�����{�ɓs���ōs����\��ł��B
�@�Ȃ��A�������́A�����Q�Q�N�P�O���ɋv���Ďs���Z�c��}���يJ�ًL�O�u����̍u�t�Ƃ��āu�]�@�ŏo������{�v�Ƒ�
���ču�����s���A�{�Z�ɂ��K�₳��Ă��܂��B�i�K�₳�ꂽ�ۂ̋L�����������j
�@
|
|
|
�v���č��ꃉ�O�r�[���n���T�O���N�L�O��ƈ��������쎌����|�������O�r�[������
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�w�����ɂĘa�H��@�u�K����J��
�@
�@�P�Q���X���i���j�ɒ}�����Q�K��L�ԂɂāA�a�H��@�u�K����J�Â��܂����B�w�����H�Ɩ����ϑ����Ă���(��)������
�{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂A���Ђ̒��������u�t�Ƃ��Č}���A�{�i�I���Η����̊�{�I�ȍ�@�ɂ��ču�K����
�����B
�@��N�ɑ����āA�S��ڂ̃e�[�u���}�i�[�u�K��ł������A�P�X���̊w���i�j�q�w���P�V���A���q�w���Q���j���Q������
�����B�����̎������A��̈������͌����ɋy���A���Ȃ��痣�Ȃɂ�����܂ŁA�i�ʂ��鍂�ꐶ�Ƃ��Ă̍�@��������
���������܂����B
�@
|
|
|
|
�u�K��̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�w�����ɂăw���X�`�F�b�N�L�����y�[�����J��
�@
�@�P�Q���U���i�j�ɁA�w�����H���ɂ����āA��Q��w���X�`�F�b�N�L�����y�[�����J�Â��܂����B(��)�������{�Ћ�B�x
�Ђ̋��͂̉��A�����́A�����A�����A���N��̑���A�X�g���X�x�`�F�b�N�ɂ��A���N��Ԃ�S����c�����邱��
���ł��܂����B�܂��A�J�����[�����h�{�f�A���ޗ��Ȃǂ������H�i�T���v���������W������Ă���A�����̐H��
�Ɖh�{�Ɋւ��Ă̗�����[�߂܂����B�u�����̌��N�͎���Ǘ�����v�Ƃ����ӎ������܂������ƂƎv���܂��B
�@�w���X�`�F�b�N�L�����y�[����ɂ́A����������ƐH���Ƃ̍��k����J�Â���܂����B
�@
|
|
|
|
�w���X�`�F�b�N���闾��
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
����Ղɂē����}�C�X�^�[���Z�Ƃ̊w���𗬂����{
�@
�@�P�P���Q������T���܂ŁA�����}�C�X�^�[���Z�i�؍���c�j�̂X���̐��k���}�����ɏh�����A����ՂɎQ�����܂����B
�@�Q���̑O��Ղ́A�@��𒅂đ��܂𗚂��A�_�`������̌����A�R���̕����Ղł́A�l�X�ȃC�x���g���y����ł��܂�
���B�T���̑̈�Ղł́A�{�Z�̐�U�Ȑ��ƃ`�[����g��Łu�݂�ȋ����_���v�̋��Z�ɎQ�����A���������R�n��̋�
�Z���������Ċ������Ă��܂����B
�@�{�Z�w���Ƃ����{������ɘb���A�y�����𗬂��Ă��܂����B�Z���Ԃł������A���Z�̊w���ɂƂ��Ďv���o�[�����ی�
���ɂȂ�܂����B
�@
|
|
|
|
����ՂɎQ�����铌���}�C�X�^�[���Z��
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
JIDA-KIGS�w���f�U�C���R���y�u�����������炵���f�U�C������v�ɂčŗD�G�܂����
�@
�@�@���{�C���_�X�g���A���f�U�C�i�[����iJIDA�j�Ɩk��B�C�m�x�[�V�����M�������[����w���⍂�ꐶ�Ȃǂ̊w�����
�ۂɎ��{�����w���f�U�C���R���y�u�����������炵���f�U�C������v�ɂ����āA�{�Z���琼�c �������A�u�� ��M����A
�|�V�� ᩍG����i�@�B�H�w�ȂT�N�j�̍�i�upita�v���ŗD�G�܂ɑI��܂����B
�@�P�P���P�V���i�y�j�ɖk��B�C�m�x�[�V�����M�������[�ōs��ꂽ�\�����ŕ\����ƃg���t�B�[�Ȃǂ������A��܂����R
�l���A�N�؊w���厖�Ǝw�������ł��铡�c�����i�@�B�H�w�ȁj�ƂƂ��ɏ�c�Z���֎�܂̕��s���܂����B
�@���̃R���y�e�B�V�����́u���ꂩ��́g�����������炵�h�Ƃ͉����H���炵���ʂ�g�����������́h�̂�����v�ɂ��Ă��炵
���ʂ�g���́h�̃f�U�C�����W�������̂ŁA�����ɉ��債���ʍ�i�uORIGAMI�v�����I���܂����B
�@��܍�i�͂P�Q���Q�U���i���j�܂Ŗk��B�C�m�x�[�V�����M�������[�ɓW������Ă��܂��B
�@
|
|
|
��܂̕��s�����c����A�u�Ȃ���A�|������
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�����Q�S�N�x�i�N�Α��\���������s
�@
�@�{�Z�ł́A�P�P���Q�O���i�j�ɍZ�����ɂ����ĕ����Q�S�N�x�i�N�Α��\���������s���܂����B
�@�\�����ł́A�c���T�ꋳ���A����N�狳���A��؍N�O�{�W���A�y�i�m��Z�p���E���̂S���ɑ��ď�c�Z��
����\����n����A�Q�O�N�̋ΘJ�ւ̎ӎ����q�ׂ��܂����B
�@�Ō�ɔ�\���҂��\���A�c����������u���S�ɋA���Ċ撣�肽���v�|�̓������q�ׂ��A���������ȕ��͋C�̒��A
�\�������I�����܂����B
�@
|
|
|
�\�����̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�����������J��
�@
�@�P�P���P�V���i�y�j�ɁA������ΏۂɁA�H�ɑ���ӎ������ړI�Ƃ��āA�{�Z�w�����̐H���ɂāA������Ћ������{
�Ћ�B�x�Ђ̋��͂ɂ��A�����������J�Â��A�P�Q�����Q�����܂����B
�@�������{�Ћ�B�x�Ђ̍������A�����A�c�������u�t�Ƃ��Č}���A�u�d�q�����W���g�����ȒP�����v���e�[�}�ɁA�P�`
���b�v���C�X�A�o���̏d�ˏ����A���₵�t�J�`���v�`�F�A�킩�߃X�[�v�̍����ɂ��ču�K���܂����B�Q���҂́A
���������Œ������������Ŋy������H���Ă��܂����B
�@
|
|
|
|
���������̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�w�����ɂĖh�Д��P���Ɣ��H�V�~�����[�V���������{
�@
�@�{�Z�w�����ł́A�P�O���P�V�� (��)�ɏH�̖h�Д��P�������{���A�����P�T�P���i�������w���V���j���Q�����܂����B��
��͋v���ď��h���̋��͂̂��ƁA�����P���Ə��Ί�ɂ�鏉�����̕��@�ɂ��Ďw�����܂����B
�@�I����h�����i�������p���w�ȂS�N�j�̉Д����̍��}�ƂƂ��ɌP�����J�n���A���O��ɔ��シ���ɎQ���ґS��
�̓_�Ă��s���܂����B���ɁA�}�����R�K�w�K��������Ђ��C���[�W���������P�����s���A�Q�����������͏��z�[
�X�ɂ����鐅���̋����ɂт����肵�Ă��܂����B�Ō�ɁA���ԏ�Ɉړ����A���Ί�̎g�p���@�ɂ��Ďw�����܂�
���B
�@�܂��A�w�����H�Ɩ����ϑ����Ă���i���j�������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂ŁA���H���ɔ�펞�̐H����̌�������H
�V�~�����[�V�������s���A�ЊQ�p�̃��g���g�ۑ��H��H�ׂ邱�Ƃ�ʂ��Ėh�Ђɑ���ӎ������߂܂����B
�@
|
|
|
|
�h�Д��P���Ɣ��H�V�~�����[�V�����̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�����Q�S�N�x�@�v���Ďs���P�ʌ݊�����Z�ɂ��u�����u�`�v���J�u
�@
�@�{�Z�ł́A�v���Ďs���̂T��w���Ƃ̊ԂŒ������Ă���P�ʌ݊�����̈�Ƃ��āA�e��w���̌�����F��
�������u�`���s���u�����u�`�v���A�u�v���Ă̐����Ɗ��v���e�[�}�Ƃ��ĊJ�Â��Ă��܂��B
�@�P�O���P�Q���i���j�ɋ��؏y�����i�������p���w�ȁj�ɂ��u��������p�������v�ƁA�P�P���P�R���i�j�ɒ����y
�����i�@�B�H�w�ȁj�ɂ��u�X�}�[�g���Z�p�Ƃ��̓W�]�v�̂Q�̍u�`���s���A�A�g�Z�̊w����S�O������u���܂����B
�@
|
|
|
�����u�`�̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�w���W����in����߂肠�Z�b��Ɋw�����o�W
�@
�@�P�O���Q�T���i�j����Q�W���i���j�ɂ����āA��������R���\�[�V�A���v���Ď�Â̊w���W����in����߂肠�Z�b�傪
�J�Â���܂����B���̃C�x���g�́A�v���Ďs���̍�������@�ւ��݂��ɘA�g���A���Ȍn�̕������E�T�[�N���̊�����
�ʂ\����@��𑝂₷���ƂŁA�n��̕��X�ւ̔F�m�x�����コ����ƂƂ��ɁA���Z�ƌ𗬂��s���A�����̎����
�K�͂��L���邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ł��B
�@�v���đ�w�A�v���čH�Ƒ�w�y�і{�Z�̍��v�P�O�̕��E�T�[�N�����Q�����A�{�Z����́A�v���O���~���O���{���E��
�{�R�����E�ē��D��E�ʐ^���D��̂S�̃N���u���Q�����āA�e�u�[�X�ɂēW�����s���A����҂ɕ��i�ǂ̂悤�Ȋ���
�����Ă��邩��A�W�����̏ڂ������������s���܂����B
�@
|
|
|
|
|
|
|
|
�w���W����̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�w�Z������E���w����J��
�@
�@�{�Z�ł́A�w�Z������E���w����P�O���P�R���i�y�j�ɊJ�Â��A�R�O�O�����钆�w���A�ی�҂��͂��߁A�����̕��X
���{�Z��K��܂����B
�@������ł͏�c�Z������w�Z�T�v�������A���䋳���厖�₩��e�w�Ȃ̏Љ�╽���Q�T�N�x���w�������ɂ�
���Ă̐������s���܂����B���ł́A�M�S�Ƀ��������p�����������Ō����܂����B���̌�̌ʑ��k��ł́A�e
�厖��e�w�Ȓ��֑��ƌ�̐i�H���Ɋւ��鎿�₪�������Ă��܂����B
�@�܂��A�����čs��ꂽ���w��ł́A�{�Z�̓��F��w���{�݂Ȃǂɂ��ė�����[�߂Ă��炤���߁A�\���ɏ�������
�R�S�����̌��w�X�|�b�g�ɂ����āA������ݍZ���ɂ������ݔ��̏Љ�A���J�����A�W�������s���܂����B
�@�Q���������w������́A�u���ۂɎg�p���Ă�������@���ڂ̓�����ɂ��A��w����ւ̋������N�����B�v�A�u����
��ݍZ���̐�����������₷���A�Q�����ėǂ������B�v���̈ӌ����A�����̂����ɏI�����܂����B
�@
|
|
|
|
�ʑ��k��ƌ��w��̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�����Q�S�N�x�v���Ďs�H�琄�i�c�̕\�������
�@
�@�v���Ďs�H�琄�i��c�ł́A�s�������ɂ��H��̐��i��ړI�ɁA�v���Ďs���̗l�X�ȏ�ʂŎ��H����Ă���D
�ꂽ�H��̎��g�݂�\�����Ă���A���̂��і{�Z�w�����̊������F�߂��A�X���Q�X���i�y�j�ɕ\�����܂����B
�@�w�����ł͗����́u�H���Ɖh�{�v�Ɋւ���ӎ������コ���A���X�̐����K�������P���邱�Ƃ�ړI�Ɂu���Q���N����
���͂�v�𗾂̔N�x�ڕW�Ƃ��č��肵�A�H���Ǝҁi������Ћ������{�Ћ�B�x�Ёj�Ƌ��͂��Ȃ���v��I�ɐH�犈��
��W�J���Ă��܂��B�H���Ǘ��ɉ����āA�w���X�`�F�b�N�L�����y�[����e�[�u���}�i�[�u�K��A�H�i�q���u�K��A����
�����ȂǁA�l�X�ȐH�琄�i���������{���Ă���A�w���́A�h�{�o�����X�̂Ƃꂽ�H���������N�̊�{�ƂȂ邱�Ƃ���
�łȂ��A�����^���R���f�B�V�����̈ێ�����ɂ��s���ł��邱�Ƃ��ĔF�����A���H�̋i�H���̌���ȂǁA�����K���S��
�����������ƂŋK���������������Ɍ��������P�Ɍq���Ă��܂��B
�@
|
|
|
|
�\��������^�����]�藾���厖
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�y�v���č���E�L������E�k��B����z�������������R���ꍇ���w�Z��������J��
�@
�@�����s�̓V�_�r���łX���Q�X���i�y�j�ɁA�����w�Z��������J�Â��܂����B
�@���̍����w�Z������́A�{�Z�A�L������A�k��B����̕��������̂R���ꂪ�A�g���āA�����s�y�ю��ӎs������
���w���A�ی�ҁA���w�Z�����A�w�K�m�W�҂�ΏۂɊJ�Â������̂ŁA���̒n��ɂ����鍂��̒m���x���A�b�v����
��ƂƂ��ɁA�u��Ҋm�ۂ�ړI�Ƃ��Ď��{�������̂ł��B
�@�����́A�Q�O�O������Q���҂��K��A�R����̍Z���A�����厖�ق����E�����o�Ȃ��A�S�̉�ō���S�ʂ̐���
����������A�e����ɕ�����Čʂ̐������s���܂����B
�@�܂��A�R����ɉ����A�F�{����E�����ۍ���E�s�鍂��E���������ꂩ����w�Z�Љ�u�[�X�̏o�W������A�Q������
���w���̃A���P�[�g�ɂ́A�e����̓���������x�ɕ������Ƃ��ł��Ă悩�����A����̓����𗝉��ł����Ȃǂ̈�
�����������܂����B
�@
|
|
|
������ƌʑ��k�R�[�i�[�̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�e�}�Z�N�E�|���e�N�j�N�̊w�����{�Z��K��
�@
�@��B�E����n��̂X����́A�V���K�|�[���̍H�Ȍn��������@�ւ̂R�Z�ƌ𗬋����������Ă���A����A���̒���
�P�Z�ł���e�}�Z�N�E�|���e�N�j�N�Z�̊w���S�R���Ƌ����Q�����A�k����B�ւ̏C�w���s�̍��Ԃ𗘗p���A����X���Q�V��
�i�j�A�{�Z��K�₵�w���𗬂��s���܂����B
�@���Z�v�V�����ł͏�c�Z�����犽�}�̈��A�̌�A����y�����i��ʉȖڕ��ȁj����w�Z�Љ�s���܂����B�����āA
�ǂɕ�����Ē��H�����݁A���{�����̌��Ƃ��Đ܂莆����{�̗V�тȂǂ�ʂ��Đe����[�߂܂����B�w�������͗\��
�̎��Ԃ��߂���̂��Y���قǁA�ʐ^���B�肠������A�M�S�Ɍ�荇�����肵�A�L�Ӌ`�Ȏ��Ԃ��߂����܂����B�Z������
�ł������ٕ����𗬂�ʂ��āA�݂��̕����≿�l�ςւ̋�����S���[�܂�܂����B
�@
|
|
|
|
�e����[�߂�w������
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
����̌����w���J��
�@
�@�{�Z�ł́A�W���Q�O���i���j�y�тQ�P���i�j�ɒ��w����ΏۂɁA�����ʂ��ē��Z�̂T�w�ȋy�ш�ʉȖڂ̎��Ƃ�̌�
���Ă��炤���Ƃ�ړI�Ƃ����u����̌����w�v���J�Â��܂����B����ԂłT�V�O���̎Q���҂�����A���x�݂ɂ͍݊w��
�ɂ��w�Z�s���̐������s���܂����B�܂��A�Z���ɐ݂����i�H���k���ł́A�ی�҂��狳���֑����̎��₪��
��A���ڑΘb�ł���悢�@��ƂȂ�܂����B
�@�Q���������w������́A�e�w�Ȃ��ʉȖڋ����̍H�v���Â炵�����ƂɁu����ƕ��ʍ��Z�̈Ⴂ�����������B�v�A�u��
�w���̐����ɍD�����������B�v�A�u��̓I�Ȏ������ł��ꂼ��̊w�Ȃ̓��������������B�v�A�u���������������ǁA��
���������B�v�Ȃǂ̐���������D�]���܂����B
�@
|
|
|
|
�̌����ƂŎ������s�����w��
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�����Ȋw�ȓ�����勳��ے����{�Z�����@
�@
�@�����Ȋw�ȍ�������ǂ̓����q���勳��ے��Ǝ��ʉ��q��勳��ۍ������w�Z�W�����A�V���P�V���i�j�ߑO
���ɁA�{�Z��K�₵�܂����B��c�F�Z������w�Z�T�v����������A������L�O�قɂĖ{�Z�̉��v�ɂ��āA�@�B
�v�f�v�������ŕ����Q�O�`�Q�Q�N�x�����Ȋw�ȋ���f�o�ɍ̑����ꂽ���e���X�ɔ��W�E�[�������A��P�S��i�����Q�R
�N�x�j��B�H�w���狦��܂���܂����u�f�W�^���G���W�j�A�����O��p�����V���ȋ@�B�H�w����y�ы���f�o�Ɋ֘A��
���A�̎�g�݁v�ɂ��Ă��ꂼ��������A�w�������K���s���@�B�H��H���@�B�����������@���܂����B
�@
|
|
|
|
���@�̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�m�I���Y�t�H�[����in�v����2012�Ɋw�����Q��
�@
�@�V���P�P���i���j�ɋv���Ďs�A�i���j�v���ăr�W�l�X�v���U�A�v���Ēm�I���L���Z���^�[����Â���m�I���Y�t�H�[����
in�v����2012�u�m���ō�������I�m�I���Y �őO���I�I�v���J�Â���A�z�㐻�ي�����ЎR����ɂ�鍑�ێ��x
�̌����A�m�I���Y�̊O���o��ɂ��Ă̊�u����A�g�߂ȁu�H�v���e�[�}�ɂ������ᔭ�\���s���܂����B
�@�{�Z����́u�Y�ƍ��Y�����_�v�̎��Ƃ̈�Ƃ��āA��U�ȂP�N����R�O�����Q�����A���i�̎��ƂƂ͈Ⴄ�A��Ƃ̖�
���ł̔��\��^���Ƀ��������Ȃ��璮�u���Ă��܂����B�܂��A�u�V�R������p�����V�K�H�i�̕ۑ�������Ɋւ��錤
���v�Ƃ����e�[�}�ŋ��؏y�����i�������p���w�ȁj�����ᔭ�\���s���A���уp���̐���E���ǂƕۑ�������̐��ʂɂ�
���Đ������܂����B
�@
|
|
|
|
�t�H�[�����̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�w�����ɂđ�2���u����Ƒ��Ɛ��ɂ��u������J��
�@
�@�w�����ł́A�U���Q�W���i�j�A�V���R���i�j�̓���ԁA��Q���u����u���w���ɂ��ꍑ����`�ٕ��������̂�
�߂Ɂv���J�Â��܂����B
�@��Q���u����́A���w���Ɠ��{�l�w���Ƃ̌𗬂̂��������Â���Ƃ��ĊJ�Â���A�T�O���ȏ�̗������Q�����܂�
���B
�@���w���̃}���[�V�A�̃T������i�@�B�H�w�ȂR�N�j�A�V���t�����N�i�d�C�d�q�H�w�ȂR�N�j�A�����S���̃i���T�[����i��
�����p���w�ȂR�N�j�A���I�X�̃����l���N�i�ޗ��H�w�ȂS�N�j�A�C���h�l�V�A�̃J���J���N�i�ޗ��H�w�ȂS�N�j���A���ꂼ��
�̕ꍑ�̕����ɂ��ăp���[�|�C���g�ʼn����������A�����ߑ����I�����肵�A�ٕ���������[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B
������@�Ɋw���ł̍��ی𗬂��i�ނ��Ƃ����҂��܂��B
�@�܂��A�V���R���̕����u�����ɂ́A�{�Z�d�C�H�w�ȑ��Ɛ��ŃV�X�e���G���W�j�A�̍������L���ɂ��u������J
�Â��A�R���s���[�^�v���O���}�[�Ƃ��Ă̎d���ɂ��ďڂ����b�����Ƃ��ł��܂����B
�@
|
|
|
|
�u����̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�w�����e�[�u���}�i�[�u�K����J��
�@
�@�{�Z�w�����ł́A�U���P�V���i���j�ɁA�w�����H���ɂāA�e�[�u���}�i�[�u�K����J�Â��܂����B��������H�����
���Ă��銔����Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂A���Ђ̓c��@�������u�t�Ƃ��Č}���A�m�H�R�[�X�����̊�{�I
�ȍ�@�ɂ��ču�K���܂����B
�@��N�ɑ����A�R��ڂ̃e�[�u���}�i�[�u�K��ł������A�Q�X���̊w���i�j�q�w���Q�V���A���q�w���Q���j���Q�����A�D
�]���܂����B�J�e�����[�i�i�C�t�A�t�H�[�N�Ȃǁj�̎g�����͌����ɋy���A���Ȃ��痣�Ȃɂ�����܂ŁA���f�B�A�W�F
���g���}���ɂӂ��킵���e�[�u���}�i�[�������܂����B
�@
|
|
|
|
�e�[�u���}�i�[�u�K��̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
���w����ΏۂƂ����w�����̐H�i�q���u�K����J��
�@
�@�{�Z�w�����ł́A�U���P�S���i�j�A�w�����H���Ɨ�����̍��k���ɁA���w����ΏۂƂ��A�H�i�q���u�K����J��
���܂����B
�@������Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂āA���Ђ̖k�쎁�A��������A�c������A������A�~�J�̎����ɓ���
���ӂ��K�v�ƂȂ�H���ł̊�b�m���E�댯���ɂ��Ă̍u�K��A������ƐH��̐����x�̃`�F�b�N���A�����O
��̏��ŁA�������̐��A�����O�H�ނ̕ۊǕ��@�A�������̊댯�A�H�c���̕ۊǂ⏈�����@�ȂǁA�ו��ɂ킽
���Ďw�����s���܂����B
�@�U���P�V���i���j�ɂ́A���w�������ƂɁA���w���p������ƐH��̑�|�����s���܂����B
�@����A��N��ʂ��āA�q���ʂ̃��x�����グ�Ă��������Ǝv���܂��B
�@
|
|
|
|
�H�i�q���u�K��̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�n�k�ƉЂ�z�肵���h�Б����P�������{
�@
�@�{�Z�ł́A�U���P�R���i���j�ɋv���Ďs���h��������̌��A�k�x�T���̒n�k�ɂ��Д�����z�肵���h�Б���
�P�����s���܂����B�h�Б����P���́A�n�k��������В��܂ł̈�A�̗�����V�~�����[�g���A�w���⋳�E���֖h
�Ύv�z�̕��y����э��g��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ŁA�w���Ƌ��E�����킹�Ė�P�P�O�O�����Q�����܂����B
�@�P���ł͏�c�Z������{�����Ƃ����E���ɂ�鎩�q���h�c����������A�v���ɔ��s���܂����B
�@���I����́A���h�����ɂ����Ί�̎g�p���@�̐������A�R�N���A�S�N���A�T�N���A���E���̏��ɏ��Ί푀
��P�����s���A���h�������P���S�̂̍u�]���s���܂����B
�@�Ō�ɏ�c�Z������̈��A�������āA�����I�����܂����B
�@
|
|
|
|
�h�Б����P���̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
����24�N�x�i�t�G�j�����������w�Z��B����n��Z���E����������c���J��
�@
�@�����Q�S�N�x�i�t�G�j�����������w�Z��B����n��Z���E����������c���A�U���V���i�j�E�W���i���j�̗����A�{�Z
�ԍZ�Ƃ��āA��������@�\����ؒJ�����A�O�Y�����ے����}���A�J�Â���܂����B
�@��c�Z���̊J��̈��A�A�ؒJ��������@�\�̋ߋ����܂߂Ĉ��A������A�S�̉�c�ŁA��o���ꂽ���c��y�ѕ�
�����ɂ��ē��c���A�ؒJ��������@�\�{���Ƃ��Ă̈ӌ��⏕���������A�����Ȉӌ��������s���܂����B���������A
�Z����c�y�ю���������c�ɕ�����A�e�Z�����ʂ��铖�ʂ̏��ۑ蓙�ɂ��Ĉӌ������킳��܂����B
�@���A�W���i���j�́A�Z���{���w���s���A�H��H���@�B�v�f�v���������n�߂Ƃ���������A��N�x����������
�q���Ȃǂ����@���܂����B
�@
�@
|
|
|
��c�Ǝ��@�̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�����}�C�X�^�[�����w�Z�i�؍��j�Ƃ̊w�����ی𗬍s�����J��
�@
�@�T���Q�R���i���j�ߌ�A(��)�؍��l�ށE�Z�p���͋@�\�̎�ǂɂ��A�����}�C�X�^�[�����w�Z�i�؍���c�s�j�̊w���y��
�������E���̑����P�P�P�l���A�{�Z��K��A�`���Z��ʂ��Ė{�Z�w���P�P�O�l�Ƙa�₩�Ɍ𗬂��s���܂����B����͓�
���}�C�X�^�[�����w�Z�̓��{���C�̈�Ƃ��āA�C�O�̐�i�E�Ƌ���@�ւ�K�₵�̌���ʂ��ăO���[�o���}�C���h
���琬���邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ŁA��N�x�Ɉ�����������łQ��ڂƂȂ�܂����B
�@���E�Ŋ��邱�Ƃ����҂���Ă��鍂�ꐶ�ɂƂ��Ă��A�H�ƋZ�p���w�ԓ�����̊C�O�̎�҂Ƃ̌𗬂͋M�d�ȑ�
���ƂȂ�܂����B
�@��c�Z�����犽�}�̈��A�A�����}�C�X�^�[���Z�̃C�E�X�����Z�Ă��瓚��̈��A���s��ꂽ��A���ƁA������{��
���w���s���܂����B�r���A���Ƃ�����ɔ�ѓ���Q�������ʂ�����A���̂��錩�w�ƂȂ�܂����B���̌�A�̈�ق�
�ړ����A�{�Z�w�����悵���𗬍s�������{����܂����B���Z�w����\�ɂ��f���������Ă̊w�Z�Љ�Ɏn�܂�A
�؍�������i���^�i���Łj�A�e�L�������A�܂��{�Z����̓_���X���ɂ��X�g���[�g�_���X����I����܂����B�����ė��Z
�����̂W�`�[���ɕ�����Ă̑�꒵�т��s���A�𗬁A�e�r��[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B������̉�ƑI��̓���
���X���[�Y�ɍs������J�����ʂ�����܂������A�����ɏ]���𑽂����ׂ�悤�ɂȂ�ƁA�F�l�̉������M����
���i�Ɛ������傫���Ȃ��Ă����܂����B
�@�y�������Ԃ͂����Ƃ����Ԃɉ߂��A�o���̊w���B�́A�������E�Ŋ���Z�p�҂Ƃ��čĉ�邱�Ƃ�B�v���v
���ɋL�O�B�e���s���ȂǁA�o���ʂ��ɂ��݂Ȃ���A�����}�C�X�^�[�����w�Z��s�͖{�Z����ɂ��܂����B
�@
�@
|
|
|
|
|
|
���ۓI�ȋZ�p�҂Ƃ��Ă̊���𐾂������Ȃ���A�L�O�B�e�ɔ[�܂闼�Z�w���y�ы��E��
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�w�����ɂĕ����u������J��
�@
�@�w�����ł͂T���X���i���j�ɗ��̐H���ɂāAdiBec�i�C�O��w���{�����ǁj��\�̑��c���m�����u�t�Ƃ��Č}���A����
�����u������J�Â��܂����B
�@�u����ł́A���c���̃A�����J���w�ƍ��ۃr�W�l�X�̌o����ʂ��āA�Љ�狁�߂��Ă���l�����A�C�O�����̌�
�̂����߁A�C�O���w�̎������@�A�C�O�̑�w�E��w�@�ւ̐i�w�ɂ��ĂȂǏڂ�������������܂����B
�@�u���ꂩ��̓��{��S���Ă�����҂����ɂ́A�O���[�o���Ȏ���������ė~�����A���ɍH�ƍ��ꑲ�Ɛ��̂悤�ȍH��
�Z�p�҂́A�p��Ƃ����R�~���j�P�[�V�����̂��߂̓���i�c�[���j�̃X�L����g�ɂ��Ă����A���{�����łȂ����E��
�傢�ɔ��@�����B�v�Ɖp��̏d�v���ɂ��Č���A�u�����_�ł̉p��̔\�͖͂��Ȃ��A�C�O���w�̕�
�����{�����ł̐i�w����p�������Ȃ邱�Ƃ�����v�ƁA�p�ꂪ���Ȋw���ւ̃A�h�o�C�X������܂����B
�@
�@
|
|
|
|
�u����̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�w�����ɂăw���X�`�F�b�N�L�����y�[���Ɨ����������J��
�@
�@�T���X���i���j�A������Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂̉��A�w���X�`�F�b�N�L�����y�[�����J�Â��܂����B�w���X�`�F�b
�N�ł́A�����A�����A���N��̑����X�g���X�x�`�F�b�N�ɂ��A�����̌��N��Ԃ�c�����܂����B
�@���N�͋v���Ďs�ی�������S���̐E�������Z����A�t�[�h���f�����g���[�Ɏ��A��ɏ悹�邾���Őێ�J�����[��h
�{�o�����X���v�Z�ł���u�H��r�`�s�V�X�e���v�Ƃ����H���f�f�V�X�e���ɂ�錒�N���i�̂��߂̐H��w�����܂����B
�@�����̏��q�w������v�]�̂����������������A�����L�b�`���ɂĊJ�Â��܂����B���̗��������́A�������{
�Ћ�B�x�Ђ̑������Ɩ��c�����u�t�Ƃ��Č}���A���َq���i�������啟�A�����P�[�L�j�ƃt���[�c�J�b�e�B���O�ɂ�
�ču�K���܂����B�u�K��̃A���P�[�g�ł́A�u���̂悤�ɁA�������łȂ��F�X�Ȃ��Ƃ��w�ׂ�@������Ƃ����
���Ǝv���B�v�ȂǍ�����C�x���g��]�ސ�������܂����B
�@�܂��A�w���X�`�F�b�N�L�����y�[���Ɨ���������ɂ́A����������ƐH���Ƃ̍��k����J�Â���܂����B
�@
�@
|
|
|
|
�w���X�`�F�b�N�L�����y�[���Ɨ��������̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�w�����ɂďt�̗��Ղ��J��
�@
�@�w�����ł́A�S���Q�P���i�y�j�ɏt�̗��Ղ��J�Â��܂����B���Ղ́A���N�x��菗�q�����������A��N�x�܂łƂ͈�
�����͋C�ƂȂ�܂������A�̌����������܂߂Ė�P�T�O���̗������Q�����A�X�|�[�c���ƃo�[�x�L���[�p�[�e�B�[���s
���܂����B
�@�X�|�[�c���i�T�b�J�[�A�h�b�W�{�[���j�ł́A���ʂ⍑�ЁA�w�N�A�w�ȂȂNJW�Ȃ��A�O���[�v�ɕ�����Ď������s
���A�V�����l�ԊW����邱�Ƃ��o���܂����B
�@�܂��A�[���̃o�[�x�L���[�p�[�e�B�[�ł́A�O���[�v���ɉ��O�ɒ������e���g�œ����Ă��A�k�������Ȃ���H�������A
�����ʂ��Đe�r��[�߂����Ă��܂����B
�@
�@
|
|
|
|
���Ղ̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�w�����ɂăr�W�l�X�}�i�[�u�K����J��
�@
�@�{�Z�ł́A�S���P�T���i���j�Ɋw�����̐H���ɂăr�W�l�X�}�i�[�u�K����J�Â��܂����B
�@������Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂A���Ђ̓c�썄�����u�t�Ƃ��Č}���A�P�Q���̊w�����Љ�l�Ƃ��Ă̊�{
�I�ȗ�V��@�ɂ��ču�K���܂����B
�@�u�K�ł́A�r�W�l�X�X�[�c�̒����₨���V�̎d���A���h�����̕��@�A�h��Ȃǂ̐��������t�g���A�d�b�ł̉��}
�i�[�A���ڎ��ł̍�@�Ȃǂ��u�`�Ɖ��K�`���Ŋw�сA���������̉��l�ςɊ�Â����Ƃ�悪��̌�����T�ނ��ƁA����
�āA���͂ɕs������^���Ȃ������A���͂ւ̋C�z�肱�����A�Љ�l�Ƃ��Ẵ}�i�[�̊�{�ł��邱�Ƃ�F������ǂ��@
��ƂȂ�܂����B
�@
�@
|
|
|
|
�r�W�l�X�}�i�[�u�K��̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�w�����ɂđΖʎ������{
�@
�@�S���U���i���j�ɖ{�Z�w�����H���ɂ����āA�ݗ����ƐV�������̑Ζʎ����s���܂����B
�@���N�x�́A�����i���q���j�V�y�ђj�q���̐��������P�ɂ���āA���������̏�i���V�F�A�n�E�X�j��������
��A���j���[�A�������H���ŐV�������S�X���i�j�q�R�Q���A���q�P�V���j����l���������ւ̎v�����q�ׂ܂����B
�@���̌�A�]�藾���厖����A�R���s�e���V�[���x���Ƃ����]����̊T��������A�����ɑ��������g�Ń��x���A�b
�v���A����̍��ꐶ���A����ɑ��ƌ�̐l�����ė~�����Ɗ��҂����܂����B���ɁA�R���̗����厖�₩
��A�V�����Z�L�����e�B�[�V�X�e���y�ї������ɂ��Ă̏����ӂ�����A���������y�����A���L�Ӌ`�Ȃ��̂ɂ��邽��
�ɁA�S���ŋ��͂��đf���炵���������グ�Ă������Ɛ錾������A�����Q�S�N�x�v���č���w�������X�^�[�g���܂����B
�@
�@
|
|
|
|
�w�����Ζʎ��̗l�q
�@
�@
�@
����24�i2012�j�N�x
�����Q�S�N�x���w�������s
�@
�@�{�Z�́A�����Q�S�N�x���w�����S���T���i�j�ɐV�����Q�O�S���A�ғ����S���i�������w���R���j�y�ѐ�U�Ȑ��R�Q�����}
�����s���܂����B
�@���ł́A���o�A�ی�ҋy�ы��E��������钆�A�{�Ȑ��A�ғ����A��U�Ȑ��̏��Ɉ�l�����O���Ă�A��c�Z��
������w��������܂����B�����āA�e�V������\���o�d��������ǂݏグ�A���ꂩ��n�܂鍂�ꐶ���̕������q��
�܂����B
�@���w���I����A�V�����͍���ࣖ��ȃ��C���X�g���[�g�ŏ㋉�����畔�����U���܂����B
�@ �����Q�S�N�x���w���̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
���q���u�����v�v�H�������s �@
�@���q���u�����v�̏v�H�����R���Q�W���i���j�ɋ��s���܂����B
�@�{�Z���t�y���̉��t�Ɏn�܂�A��c�Z���A�Õ��������A�����āu�����v�Ŕ����|���Ă��������܂������莁
�i���H��P�����j�̈��A�̌�A��c�Z�����珗�q�������҂̕\��������܂����B��҂���́A�v���Ďs�̎s�ԂƂȂ���
����u�v���Ă��v�ւ̎v���⏗�q���ւ̊��҂��q�ׂ��܂����B���ɁA��������\���āA�����������i�d�C�d�q�H
�w�ȂR�N�j�Ə��앛�����i�ޗ��H�w�ȂR�N�j����A�W�҂ւ̊��ӂƐV���ȋv���č���w������z���Ă����������q�ׂ�
��܂����B�t���̒��A��c�Z�����͂��߂U���ɂ��e�[�v�J�b�g�A���t�y���t�@���t�@�[���y�ї���������ɂ��N���b�J�[
���˂Ƒ����A�v�H���͏I�����܂����B
�@����A���q�����w����s���A�V�������͊��҂ɖ������\��ŏ��q�������w���܂����B �@ �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�����Q�R�N�x���Ǝ��A�C���������s �@
�@�{�ȑ��Ǝ��A��U�ȏC�������R���P�U���i���j�ɖ{�Z���̈�قɂ����ċ��s���܂����B
�@���l�ȕ��͋C�̒��A��c�Z������{�ȑ��Ɛ��Q�O�S���A��U�ȏC�����S�P���ɑ��Ə؏��y�яC���؏������^����A
�Z�������A���o���A�̌�A�������s��ꂽ�\�����ł́A�w�Ɛ��їD�G�Ȏғ��ɕ\�����^����܂����B
�@���T�I����A���̈�قős�s����J�Â��A�{�ȑ��Ɛ��y�ѐ�U�ȏC�����̖�o���j���܂����B �@
���Ə؏����^�̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
���c�����y�ы����y��������P�S���B�H�w���狦��܂���� �@
�@�{�Z�@�B�H�w�Ȃ̓��c��r�����Ƌ����^���y�����́u�f�W�^���G���W�j�A�����O��p�����V���ȋ@�B�H�w����y
�ы���f�o�Ɋ֘A�����A�̎�g�݁v����P�S��i�����Q�R�N�x�j��B�H�w���狦��܂���܂��܂����B
�@���̏܂́A�H�w�E�H�w����Ɋւ���V�������ʓI�ȋ�����@�A��i���āE���H�������Ƃ�]�����ꂽ���̂ŁA�\��
���͕����Q�S�N�Q���V���i�j�ɋ�B��w�H�w���ɓs�L�����p�X�ɂčs���܂����B �@
��܂������c�����i�E��j�Ƌ����y�����i�E���j �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
��Q�Q��S���������w�Z�v���O���~���O�R���e�X�g���Z����D���`�[�����茴�v���Ďs����\�h�K�� �@
�@�����Q�S�N�Q���Q�Q���i���j�ɁA�u��Q�Q��S�Z�������w�Z�v���O���~���O�R���e�X�g�v�̋��Z����D���`�[���i�v���O���~
���O���{���j���A��c�Z���ƃv���O���~���O���ږ�̍��؏y�����i������H�w�ȁj�ƂƂ��ɓ茴�����v���Ďs����\�h
�K�₵�܂����B
�@�D���`�[���̍�c�S���N�i������H�w�ȂR�N�j�A���ו��N�i������H�w�ȂS�N�j�A���i���N�i������H�w�ȂS
�N�j�̂R���́A�����Q�R�N�P�Q���Q�Q���i�j�A�Q�R���i���j�̂Q���Ԃɂ킽���ċ��s�{���ߎs����������قɂčs��ꂽ�R��
�e�X�g�ŗD�����A�����Ȋw��b�܂���܂������Ƃ���܂����B�����̍�c�N�́u���̃v���R�����D���ł���悤�撣��
�����B�v�Ɨ��N�x�Ɍ����Ă̈ӋC���݂�����Ă��܂����B
�@�S�Z�������w�Z�v���O���~���O�R���e�X�g�̋��Z����́A���N�قȂ������Z���[���̂��ƁA�e�`�[���̎���������v
���O�����̑��x�A���x�Ɋ�Â��ď��s�����߂���̂ŁA��Q�Q��́u��݂�����A���E��Y�v���e�[�}�ɍs���܂����B�S
���̍���U�O�`�[���̂ق��A�n�m�C���Ƒ�w�A�����S���ȋZ��w�ȂǁA�C�O�̂S��w������Q��������܂����B �@ �\�h�K��̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�O���]���ψ�����J�� �@
�@�{�Z�ł́A����A�������Ɋւ����ȓ_���E�]�����s���A�w�O�̗L���҂ɋq�ϓI�Ɍ����������A����A�������̉��P
�Ɏ����邽�ߕ]���A��ړI�ŁA����P���R�P���i�j�ɊO���]���ψ�����J�Â��܂����B
�@���̈ψ���ɂ́A��B��w��w�@�������H�w�����@���y�эH�w�����@���A�v���đ�w���A�v���čH�Ƒ�w���A�v
���Ďs���s���A�v���Ďs���w�Z�����y�ђn���Ƃ���̗L���҂������A�{�Z����́A��c�Z�����͂��߁A�e�厖�E
�w�Ȓ���P�V�����o�Ȃ��܂����B
�@�ψ���͏�c�Z���̈��A�Ɏn�܂�A�n�z�����厖����u�v���č���̋���̌���Ɖ��P�����v�y�ѓ��c�Y�w���A�g
�e�N�m�Z���^�[������u�v���č���ɂ�����G���W�j�A�����O�f�U�C������ƎY�w���A�g�v�ɂ��āA���ꂼ��������s
��ꂽ��A�{����B��w��w�@�������H�w�����@���̋c���i�s�̂��ƁA�����Ȉӌ��������s���A�n��A�g�̐��i
�ȂǑ����̒����܂����B
�@�Ō�ɏ�c�Z������A�Q�������ψ�����̋M�d�Ȉӌ��ɑ��A����̊w�Z�^�c�Ɋ������Ă��������Ǝӎ����q�ׂ��A
��܂����B �@ �ψ���̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�����Q�R�N�x�w�������l�����J�� �@
�@�}����������́A�P���P�P���i���j�ɕ����Q�R�N�x�w�������l�����J�Â��A�V���l�ƂȂ��������P�U���i�������w���P���j
���j�����܂����B
�@�]�藾���厖����V���l�ւ̏j���ƋL�O�i�̑��悪�s���A���ɗ������\���ēc�藾������j��������܂����B
���̌�A�V���l���\���A������H�w�ȂT�N�̋g�c�O�������ӎ����q�ׁA�u���܂ł����b�ɂȂ����Ƒ��A�搶�A�F�l
�Ɋ��ӂ̈ӂ�\���ƂƂ��ɁA���ꂩ�琬�l�҂Ƃ��Ă̎��o�������Ċ撣�肽���B�v�ƕ��������܂����B�ӎ��̒��ŁA�V��
�l�S���ő䎌�������ȂǁA�T�N�Ԃ̗������Ŕ|�������M�ƒ��ԂƂ̂Ȃ�����ĔF�������ƂȂ�܂����B �@ ���̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
��U��b�h�l�r�t�H�[�������J�� �@
�@�{�Z�ł́A�����Ȋw�ȋ���f�o�ɕ����Q�O�`�Q�Q�N�x�ō̑����ꂽ�uCIMS�����p�����@�B�v�f����ƎY�w�A�g�v�̎�
��g�݂̃t�H���[�A�b�v�����̈�Ƃ��āA�@�B�H�w�ȂQ�`�T�N������ѐ�U�ȋ@�B�R�[�X�P�N����ΏۂƂ��A�P�Q���Q�Q
���i�j�Ɂu���Ɛ�����̃��b�Z�[�W�`���ꑲ�Ƒ�w���̃����b�g�A�f�����b�g�`�v�Ƒ肵���b�h�l�r�t�H�[�������J�Â��܂����B
�u�t�Ƃ��āA�{�Z�̑��Ɛ��V���������A�u����ɂ͂P�T�W���̊w���y�ы��E�����Q�����܂����B
�@����̃t�H�[�����ł́A�����̋Z�p�ҁA�w���A�ِF����Ŋ��鑲�Ɛ��Ȃǂ��ꂼ��̗��ꂩ��A�����o������
�Ƃɍu�����s���A�w������Ɏ��g�ނׂ��ۑ��A�E��̐S�\���ȂǁA�i�H�I���ɂ�����b�ɁA�Q�������w���͐^��
�Ȋ፷���Ŏ����X���Ă��܂����B �@ �u����̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
��L���Z�p�Ȋw��w���ɂ����ʍu������J�� �@
�@�L���Z�p�Ȋw��w�̍�w�����A�P�Q���P�U���i���j�ɖ{�Z��K�₵�A�������k��y�ѓ��ʍu������s���܂����B����
���k��ł́A���ꋳ��y�іL���Z�ȑ�̋���ɂ��Ė{�Z�̋����ƍ��k���s���A���̌�̓��ʍu����ł́A�u����
�̓��{��S���F����ց`�Z�p�ҁE�Ȋw�҂Ɋ��҂������́`�v�Ƒ肵�A�{�Z�̊w���Q�S�O���ɍu�����s���܂����B
�@�u����ł́A���{����芪���A���߂���l�ނ̕ω���A�V���ȉȊw�I�����̎��Ⴉ�疢�m�ւ̍D��S�E�T��
�S�A�Љ�̏��ۑ�ɒ���I�Ɏ��g�ލs���͂������Ƃ̑���Ȃǂɂ��ĔM�̂��������������s���A�w���ɂ�
���ĉȊw�ւ̋����S���X�ɐ[�߂�@��ƂȂ�܂����B �@ �u��������w���ƍu����̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�}�����ɂĘa�H��@�u�K����J�� �@
�@�}�����ł́A�P�Q���P�W���i���j�Ɋw�����H�Ɩ����ϑ����Ă���i���j�������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂̉��A�a�H��@�u�K
����J�Â��܂����B���߂Ă̎��g�݂ŁA�S�A�T�N�̗�����ΏۂɁA�a�H��@��g�ɂ���@���������̂�
���B
�@�����́A�u�t����A���̉^�ѕ����̈��������ɍ��z�c�̍�������A�l�X�ȐH���̍�@�������܂����B�܂��A�u��
�����H�ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��ꍇ�͂ǂ̂悤�ɂ���̂ł����B�v���̎���ɂ����J�ɓ����Ă��������A�敍���琅���܂�
�̂P�R�i���Q���Ԃ����ĉ��y���Ȃ��犬�\���܂����B�u�t����A��g�ݎp�����@�̏�B�̑����������]������A
�u�₪�ĎЉ�l�ɂȂ����Ƃ��ɁA�����Ŋw���Ƃ��v���o���Ă��������B�v�ƍu�]������A�i�ʂ���N�Ƃ��Ēp��������
�Ȃ���@��g�ɂ��܂����B
�@ �u�K��̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�����Q�R�N�x��B����n�捑���������w�Z���������W����J�� �@
�@�{�Z�ł́A�P�P���Q�S���i�j�A�Q�T���i���j�̓���Ԃɂ킽��A�����Q�R�N�x��B����n�捑���������w�Z��������
�W����J�Â��܂����B���̌����W��́A��N�A��B����n��̊e���ꂩ�狳�����W�܂�A�e����̌����ۑ�ɂ�
���ċ��c������̂ŁA����́u����ɂ�����G���W�j�A�����O�f�U�C������A��������݂̍���ɂ��āv���e�[�}�ɁA
��B����n��̂X���ꂩ��Q�R���̋������Q�����܂����B
�@�P���ڂ́A�x�R����@�B�V�X�e���H�w�Ȗ{�]�N�s�������u��������ɂ�����G���W�j�A�����O�f�U�C���\�͈琬
�̌���Ɖۑ�v�A���썂��@�B�H�w�Ȍ���q�Əy�������u�R�[�I�v����̊T�O�ƈ��썂��ɂ�����Y�w���������
���H�ɂ��āv�Ƒ肵�����ʍu�����s��ꂽ��A�v���č���A�k��B����A�F�{����i����L�����p�X�j����e�Z�ł�
���g�݂ɂ��Ď�����s���܂����B
�@�Q���ڂ́A����̃e�[�}�ɂ�����e����̌��ɂ��Ċ����Ȉӌ��������s���܂����B �@ �Q���҂̏W���ʐ^�Ɩ{�]�����i�����j�y�ь���y�����i�E�j �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�؍������}�C�X�^�[�����w�Z�Ƃ̊w�����ی𗬍s�����J�� �@
�@����P�P���P�X���i�y�j�ƂQ�O���i���j�̂Q���ɂ킽��A�؍���c�i�e�W�����j�s�ɂ��铌���}�C�X�^�[�����w�Z�̃C�E�\���E�N
�Z���A�������E���y�ѐ��k�P�W�S�l���{�Z��K��A�{�Z�w���P�O�V�l�A�k��B���ꐶ�S�O�l�ƌ𗬍s�����s���܂����B
�@�P���ڂ́A�J��Ŗ{�Z��c�Z���A�k��B������c�����厖�A�����}�C�X�^�[���Z�C�E�E���\�N�Z���̈��A�A������
�؍����̎��كW�����E�M���q�������̎��A�v���Ďs���i���H�ό��J�����ό��E���ۉۓc���劲��ǁj�̗������o��\��
���j�����q�ׂ��A�����ĎO�Z�̊w����\����A�v���W�F�N�^�[�ɂ��f�����g�p���Ȃ���e�Z�̊T�v�Љ�s���
�܂����B�ߌォ��́A�؍��́i�Ёj�ؓ��l�ދZ�p���͋@�\�̊��ɂ��A�Q�V���̓��؍����`�[���ɕ�����A�`�[������
�ɑ��k���ăf�U�C���ɍH�v���Â炵�ăh�~�m�|�����s���܂����B�[���ɂ͊w���̐e����[�߂�ӂ����Â���A
�Q���ґ��݂ɂ��v���[���g������{�Z�u���X�o���h���ɂ����{�Ɗ؍��̋Ȃ��A�����W�������h���[�̔�I�Ȃǂ�����A
���t�̕ǂ����������Ȃ��قǁA�ł����������͋C�̊y������ƂȂ�܂����B
�@�Q���ڂ́A�{�Z�̗��Ղƌ��˂āA���Z������̊��ɂ��݂��A�܂莆�A�~�E���܂�Ȃǂ̓��{�����̌����꒵
�сA�T�b�J�[��ʂ��āA�{�Z�Ɠ����}�C�X�^�[���Z�ƂŌ𗬊������s��ꂽ�ق��A�O���E���h�Ŗ{�Z�w���ɂ�鉞����
���̔�I�Ȃǂ�����A�\�莞�����߂��Ă��ʂ��ɂ��ފw�������̌������������܂����B
�@�O���ōH�ƋZ�p���w�ԓ�����̎�҂Ƃ̍���̌𗬂́A���E�Ŋ��邱�Ƃ����҂���Ă��鍂�ꐶ�ɂƂ��āA��
�������̂Ȃ��M�d�ȑ̌��ƂȂ�܂����B �@ �𗬉�̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�i�N�Α��\���������s �@
�@�{�Z�ł́A�P�P���Q�P���ɍZ�����ɂ����ĉi�N�Α��\���������s���܂����B
�@�\�����ł́A�z�n�����A���y�����A�����y�����̂R���ɑ��ď�c�Z������\����n����A�i�N�̋ΘJ�Ɋ���
����j�����q�ׂ��܂����B�Ō�ɔ�\���҂��\���A�z�n��������u���S�ɋA���Ċ撣�肽���v�|�̓������q�ׂ��A
�����ȕ��͋C�̒��\�������I�����܂����B �@ �\�����̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
���������X��܂�ʼn����������I �@
�@�}��������T�T�����A�P�P���U��(��)�ɏ��X��܂�ő̈�Ղ̉����������I���܂����B����́A�V�������������
�X�쎩�����N�x�n���A�̂��ߖK�₵���ہA����������Ă��ꂽ���̂ŁA���߂Ă̎Q���ƂȂ�܂����B
�@������́A�������ԂR�O�����R�ǁi�@�B�H�w�ȁA������H�w�ȁA�������p���w�ȁj�ɕ����A�܂�p�ɃA�����W����
������{�ԓ��l�ɔ�I���܂����B���J���~��V��ɂ͌b�܂�܂���ł������A�����̔M�ӂ����ɓ`���A�܂�͐�
���̂����ɏI�����܂����B
�@���݁A�����́A�e�����痣�ꓯ���ゾ���̐����𑗂��Ă��܂��B���X��܂�ɎQ�����A�n��̕��X�Ɖ�b����
�钆�ŁA���X��ɏZ��ł��邱�Ƃ�F������Ɠ����ɎЉ�̈���ł��邱�Ƃ��������܂����B �@ ���������̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�����Q�R�N�x�@�v���Ďs���P�ʌ݊�����Z�ɂ��u�����u�`�v���J�u �@
�@�{�Z�ł́A�v���Ďs���̂T��w���Ƃ̊ԂŒ������Ă���P�ʌ݊�����̈�Ƃ��āA�e��w���̌�����F��
�����u�`���s���u�����u�`�v���A�u�v���Ă̐����Ɗ��v���e�[�}�Ƃ��ĊJ�Â��Ă��܂��B
�@�P�O���ɓ��c�����i�@�B�H�w�ȁj�ɂ��u���E�G�l���M�[�Ƃ܂��Â���̃f�U�C���v�ƁA�P�P���ɒ��������i�������p��
�w�ȁj�ɂ��u���̒��̒n�ߗނƂ��̍H�ƓI���p�v�̂Q�̍u�`���s���܂����B �@ �u�`���s�����c�����i���j�ƒ��������i�E�j�̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�R���\�[�V�A���v���ĘA�g���J�u���u�����ɂ�����r�W�l�X�̐i�ߕ��v���J�u �@
�@�{�Z�ł́A�P�O���Q�W���i���j�ɁA��������R���\�[�V�A���v���ĂƂ̋��ÂŁu�����ɂ�����r�W�l�X�̐i�ߕ��@�`����
�����r�W�l�X�}������̒`�v�Ƒ肵�����J�u�����A��������R���\�[�V�A���v���ăT�e���C�g�E�L�����p�X�ɂĊJ��
���܂����B
�@�u���́A�n���Ƃ�w���𒆐S�Ƃ�����ʎs����ΏۂɁA���������W�𑱂��钆���̌���ƁA���{�ƒ����̃r�W�l
�X�̐i�ߕ��̈Ⴂ��m���Ă��炤���Ƃ�ړI�Ƃ������̂ŁA�Z�F�d��������Ђ̍H���a�������u�t�Ƃ��ď����A�u�}��
�ɔ��W���钆���Y�Ƃ̎��ԁv��A�u�����ňꏏ�Ɏd��������ۂɋC��t���邱�Ɓv�A�u�A�E�������s���w���ւ̃A�h�o�C
�X�v���ɂ��ču�`���s���܂����B
�@�u�`��ɂ͎Q���҂��瑽���̎��₪���A�����ɂ��Ă��ڂ����m��悢�@��ƂȂ�܂����B �@ �H���u�t�ɂ��u�`�̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�^�C�����̊w�����{�Z��K�� �@
�@�Ɨ��s���@�l�������N����U���@�\�����{����u�����Q�R�N�x�����Ȋw�Ȉϑ����Ɓw���N����{�݂����p����
�𗬎��Ɓx�^�C�������Z�����ٌ𗬎��Ɓv�̈�Ƃ��āA�P�O���Q�U���i���j�ɓ��{����Q�O����Ƃ��Ċw�K����^�C��
���Z���Q�T���ƈ����������A�����Ƃ��^�c���鍑����{�������N���R�̉Ƃ̋{�쏊���ق��S���E���ƂƂ��ɋv��
�č����K�₵�A�{�Z�w���Ƃ̌𗬉���s���܂����B
�𗬉�ł́A��c�Z�����犽�}�̈��A�ɑ����A�o���̊w����\�҂ɂ��w�Z�Љ���{��ōs��ꂽ��A�O���[�v
�ɕ�����Č𗬂��܂����B
�@�܂��A�w�����w���s���A�w���B�͒Z�����Ԃł������A�L�Ӌ`�Ȏ��Ԃ��߂����ƂƂ��ɁA���{����w�ԃ^�C�̍��Z��
�Ƃ̌𗬂�ʂ��A�݂��̕����≿�l�ςւ̋�����S�����߂Ă����悤�ł����B �@ �𗬉�Ɗw�Z���w��̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
��B�E����n�捑������@�V�Z�p�}�b�`���O�t�F�A�ɎQ�� �@
�@��B�E����n�捑������@�V�Z�p�}�b�`���O�t�F�A���A�P�O���Q�U���i���j�Ƀ��m�Â���t�F�A�Q�O�P�P�i�}�������b�Z�����j��
�ĊJ�Â���܂����B
�@���̃C�x���g�͋�B�E����n��X���ꂪ�ۗL���関���J������JST���ƍ̑��Č����A�����ҁi�Z�p�ۗL�ҁj���g����
�ƊW�҂�ΏۂɁA���p����W�]�����Z�p�������s���A�L�����{��ƁE�����p�[�g�i�[���W���邱�Ƃ�ړI�Ƃ�������
�ŁA�{�Z����́A�����Q�P�N�xJST���ƍ̑��Č��ł���u�V�R������p�����V�K�H�i�̕ۑ�������Ɋւ��錤���v�Ƃ�
���e�[�}�ŋ��؏y�����i�������p���w�ȁj���u�����s���A���уp���̐���ƕۑ�������̐��ʂɂ��Đ������܂����B �@ �u�����s�����؏y�����Ɖ��E��B�E����n�捑������̃u�[�X �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�����w���������{�Z�ɂču������J�� �@
�@�{�Z�ł́A�P�N������R�N���̊w����ΏۂɁu�����̖���������Ȋw�v�Ƒ肵�������w�������u������P�O���P�X��
�i���j�ɑ�P�̈�قŊJ�Â��܂����B
�@�u����ł́A��c�Z�����痝���w�������ɊJ�Â̂��炪�q�ׂ�ꂽ��A���������̏�؍G�����C�ږ�̌䈥�A��
�����āA�����̌����҂R���ɂ��A�Ő�[�Ȋw�Ɋւ���u�����s���܂����B���F�m�E�m�ȉ����팤���Z���^�[��C
����������́A�u�������͂ǂ����痈���̂��HRI�r�[���t�@�N�g���[�ŒT��F���̐i���v�A��X�k�E�d�����������ˌ���
�w���������Z���^�[���Z���^�[������́A�uSPring-8�Ń^���p�N���́u�`�v������B�u����v�Ɖ����킩��H�v�A���K���E
���������C����������́A�u�i�m�e�N�m���W�[�ŊJ�������̃G���N�g���j�N�X�v�Ƒ肵�āA���ꂼ��̐�啪��ɂ�
�āA�v���W�F�N�^�[�ɂ��X���C�h��p���ĕ�����₷���ʔ����b������܂����B
�@�u����͊w�����瑽���̎��₪���A�U�O�O�l����w�������́A���i������@��̏��Ȃ��M�d�Șb�ɉȊw
�ւ̋���������ɐ[�߂��悤�ł����B �@ ��������u�t�A��u�t�A���u�t �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�}�����ɂĔ��P���Ɣ��H�V�~�����[�V���������{ �@
�@�}�����ł́A�P�O���P�X�� (��)�ɐ��Q��z�肵�����P���Ɣ��H�V�~�����[�V���������{���܂����B����́A���N��
���Ȕ�Q�������炵���䕗�P�Q���N���X�̑䕗�������n���ɐڋ߂��A�{�Z���݂̏��X��n��ɔ��������߂��ꂽ
���Ƃ�z�肵�A�P�D�Vkm���ꂽ�R���w�Z�ւ̔����s���܂����B
�@�������h������擪�ɁA���������͐��R�ƈړ����A���߂�`���闾����������R�O����ɂ͎R���w�Z�őS��
�̖������m�F����܂����B
�@�����{��k�Ђ̌��ŁA�u�n�k��̒Ôg��z�肵�čs���������H�v�ɂ���Đ����������ꂽ�ƕ��Ă��܂��B��
��̌P���Ŕ����m�F�������Ƃɂ��A��펖�ԂɊׂ������A��ÂȔ��f�Ɣ��˓I�ɍs�����鎩�M�����܂����B
�@�܂��A�w�����H�Ɩ����ϑ����Ă���i���j�������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂ŁA���H���ɔ��H�V�~�����[�V�������s���A
��펞�̐H����̌����A�h�Ђɑ���ӎ������߂܂����B �@ ���P���̗l�q�Ɣ��H��H�ׂ闾���̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�}�����ɂĐH����������k����J�� �@
�@�}�����ł́A�w�����H�Ɩ����ϑ����Ă���i���j�������{�Ћ�B�x�ЂƗ�����Œ���I�ɍ��k����J�Â��Ă��܂��B
�@����́A�@�ً}�ЊQ����z�肵�����H�V�~�����[�V�����̎��{�A�A�̌������A�B���Ղł̃C�x���g���e�A�C�a�H��
�@�u�K��̊J�Â��e�[�}�ɘb���������s���A�H���̒����łȂ��u�H��v������ɓ��ꂽ�����ɂ��Ċ����Ȉ�
�����o�܂����B
�@�����́A�����𒆐S�Ƃ��āu�H�v���y���݂Ȃ���m�����L���悤�Ƃ��Ă���A����ǂ̂悤�Ȓ�Ă����邩�y���݂ł��B
�@�܂��A�]���p�b�N�Œ��Ă������ݕ����A�s�b�`���[�����ɕύX���A�S�~�y�ш��ݎc�������炷��g�݂��s���Ă���
���B �@ �����W�ҁA�H���W�҂Ɨ�����Ƃ̍��k��i�Ƃ���܂ł̎�g�� �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�w�Z������E���w����J�� �@
�@�{�Z�ł́A�w�Z������E���w����P�O���P�T���i�y�j�ɊJ�Â��A�R�O�O������A���w����]���钆�w���Ƃ��̕ی��
���{�Z��K��܂����B
�@������ł͏�c�F�Z������w�Z�T�v�ɂ��Ă̐������s��ꂽ��A�e�w�Ȃ̏Љ�╽���Q�S�N�x���w�����ɂ�
�Ă̐����y�ьʑ��k��s���܂����B
�@���������s��ꂽ���w��ł́A�\���S�̂łR�R�����̌��w�X�|�b�g���݂����A�e�w�Ȃ̎����ݔ��A�W��������w
���̗l�X�Ȏ{�݂����J����܂����B
�@�Q���������w���͋�����ݍZ���̐����ɖڂ��P�����Ȃ���M�S�ɕ��������Ă��܂����B �@ ������̗l�q ���w��̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�S�����H�Z�p�Ґl�ވ琬�u���u�S���̎��H�Z�p�u���v�����{ �@
�@�S�����H�Z�p�Ґl�ވ琬�u���ł́A�S�����H�Z�p�Ɋւ��A�z���v������H�E�����E�g���u����܂őΉ��\�Ȏ�
�H�I�m����L���鍂�x�l�ނ��琬���A�n���Ƃ̎����ԎY�Ƃւ̐V�K�Q���y�юg����x�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ�
�Ă���A�ŐV�̏��������ꂽ���H�I�ȍu���̊J�Â��s���Ă��܂��B
�@�{�Z�ł́A�X���P�U���i���j�A�Q�X���i�j�A�R�O���i���j�̂R���Ԃɂ킽��A�S�����H�Z�p�Ґl�ވ琬�u���̂P�ł���A�S
���̎��H�Z�p�u���ɂāA���Z���L����ݔ���m�E�n�E�����p���āA�u�����h�S���̉��������̕]���ƃJ�[�{���t�B���[
�̈Ⴂ�ɂ��⋭���ʂ̕]���̎��K���s���܂����B
�@���K�ɂ͂S���̎Љ�l���Q�����A�u�����⑪��Ȃǂ̎��K�����S�ŁA�����ł͑̌��ł��Ȃ������ł����ɂȂ����B�v
�u�����E�����ȊO�ɂ����u�⑪��@�ɂ��Đ���������A�m�����L�������B�v�Ȃǂ̊��z�����܂����B �@ ���K���s���Q���҂̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�������������R���ꍇ���w�Z��������J�� �@
�@�{�Z�A�L������A�k��B����͂P�O���P���i�y�j�ɁA���������̂R���ꂪ�A�g���āA���N�x���߂ĕ����s�̓V�_�r��
�����w�Z��������J�Â��܂����B
�@���̍����w�Z������́A�����s�y�ю��ӎs�����̒��w���A�ی�ҁA���w�Z�����A�w�K�m�W�҂�ΏۂɊJ�Â���
���̂ŁA���̒n��ɂ����鍂��̒m���x���A�b�v������ƂƂ��ɁA�u��Ҋm�ۂ�ړI�Ƃ��Ď��{�������̂ł��B
�@�����́A�Q�O�O���߂��̎Q���҂��K��A�R����̍Z���A�����厖�A���������ق����E�����o�Ȃ��A�n�߂ɑS�̉�ō�
��S�ʂ̐�������������A�e����ɕ�����Čʂ̐�����s���܂����B
�@�܂��A�R����ɉ����A�F�{����E�s�鍂��E���������ꂩ����w�Z�Љ�u�[�X�̏o�W������A�Q���������w���̃A��
�P�[�g�ɂ́A�e����̓���������x�ɕ������Ƃ��ł��Ă悩�����Ȃǂ̈ӌ����������܂����B �@ �S�̐�����̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�e�}�Z�N�E�|���e�N�j�N�̊w�����{�Z��K�� �@
�@��B�E����n��̂X����́A�V���K�|�[���̍H�Ȍn��������@�ւ̂R�Z�ƌ𗬋����������Ă���A����A���̒���
�P�Z�ł���e�}�Z�N�E�|���e�N�j�N�Z�̊w���S�S���Ƌ����Q�����A�k����B�ւ̏C�w���s���A�w�Z�Ԍ𗬂̈�Ƃ���
�P�O���R���i���j�ɖ{�Z��K�₵�܂����B
��c�Z���̊w�Z�Љ�̌�A�e�}�Z�N�E�|���e�N�j�N�Z�̊w���ƃL�����p�X�c�A�[���s���܂����B�c�A�[�ł͖{�Z�̊w��
���p��Ŏ{�݂̈ē����s���A�ϋɓI�ȃR�~���j�P�[�V�������}���Ă��܂����B�c�A�[��̃e�B�[�p�[�e�B�[�ł͗\���
���Ԃ��߂��Ă��ʐ^���B�肠������A�b������ł����肷��p�������A�L�Ӌ`�Ȏ��Ԃ��߂����ƂƂ��ɁA�قȂ镶����
���w���Ƃ̌𗬂�ʂ��A�݂��̕����≿�l�ςւ̋�����S�����߂Ă����悤�ł����B �@ �e�}�Z�N�E�|���e�N�j�N�Z�̊w���Ƌ��ɋL�O�B�e �L�����p�X�c�A�[�E�e�B�[�p�[�e�B�[�̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
��10��3D-CAD���J�u���`3D-CAD���p�Ɋւ����b�u����`���J�� �@
�@�{�Z�ł́A��P�O��R�c�|�b�`�c���J�u���`�R�c�|�b�`�c���p�Ɋւ����b�u�K��`���X���Q�V���i�j�ƂQ�W���i���j�̂Q
���Ԃɂ킽��J�Â��܂����B
�@�R�c�|�b�`�c���S�҂����ƂŊ��p���Ă�������o���҂܂ŕ��L����u�҂���\�����݂�����A�X�����Q�����܂����B
�@�P���ڂ́A�R�c�|�b�`�c�̑�\�I�ȃf�W�^���E�G���W�j�A�����O�\�t�g�ł��颃\���b�h�E���[�N�X��̑���ƁA���̊��p���@
�𗝉����邱�Ƃ�����ɓ���A�R�c���f���̍쐬����A���`�F�b�N�A����V�~�����[�V�������A��A�̊�{������s���A
�Q���ڂ́A�R�c���f������̐��@�\����Q�c�}�ʂ̍쐬�A�b�`�d�\����͓��A�����ʓI�ɂR�c�|�b�`�c���g�����Ȃ�����
�̉��p���쓙���s���܂����B��u�҂͊w���s�`�̕⏕���Ȃ���A�M�S�ɉۑ�Ɏ��g��ł��܂����B �@ �M�S�ɑ�����s����u�� �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�����Q�S�N�x�Ȋw������⏕����������J�� �@
�@�{�Z�ł́A�X���Q�Q���i�j�ɊO�������l�����i�̈�Ƃ��āA�����Q�S�N�x�Ȋw������⏕�����Ƃɂ��Ă̐���
����J�Â��A�{�Z�̋����R�P�����Q�����܂����B
�@������ł́A�u�t�Ƃ��āi�Ɓj���{�w�p�U����w�p�V�X�e�������Z���^�[�v���O�����I�t�B�T�[�̎R�c�~���������A
�ŋ߂̉Ȍ���̓�������A�傫���ύX�̂������ӏ��E�\�����쐬�̗��ӎ������ɂ��Đ���������܂����B
�@�o�Ȃ�����������́A�\���ɂ������Ă̑����̎��₪���܂����B �@ �Ȋw������⏕��������̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�}�����̐��������P�����{ �@
�@�}�����ł́A�W���R�P���i���j�̊J���ɍ��킹�ė�g�[�G�A�R����S���̋����ɐݒu���܂����B����́A�ߔN�̒n����
�g���ɂ��C���㏸�y�щƒ�ł̐����X�^�C���̕ω��ɑΉ��������̂ŁA�g�p���Ԃ��ꕔ�������Ă�����̂́A���
���K�Ȑ������ƂȂ�܂����B
�@�܂��A�����{��k�Ђɂ��d�͋�������Ԃ܂�钆�A�G�A�R���ݒu�ɂ��d�͏���������ł��}���邽�߁A���O��
�͑S���ő�|�����s���A���ɐߓd�i�K���X�j�����̔�U�h�~�j�t�B������\�铙�A�ߓd��ɂ���g��ł��܂��B �@ �{�H�O �{�H�� �G�A�R���ݒu��̋��� �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
����@�\�ؒJ�������{�Z�����@ �@
�@�Ɨ��s���@�l�����������w�Z�@�\�̖ؒJ��l�������A�X���P�U���i���j�ɖ{�Z��K�₵�܂����B
�@��c�F�Z������w�Z�T�v����������A�@�B�v�f�v�������łR�N�Ԃɂ킽�镶���Ȋw�ȋ���GP�̎�g�ɂ�
���Ă̐���������A���̌���K�H��A���q�����ݗ\��n�A�}���فA�Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[�y�ѓ�����L�O�ق���
�@���܂����B�܂��A��U�Ȑ��̌����_�����\��Ŋw���̔��\�����ق��A�s���̂���߂肠�Z�c��ɂ���A�{�Z����
�ދv���Ďs���T�̍�������@�ւɂ��\������u��������R���\�[�V�A���v���āv�̃T�e���C�g�E�L�����p�X�����@��
�܂����B �@ ���@���s���ؒJ���� �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�����Q�R�N�x�����n��R���ꎖ���E���i��C���j���C����J�� �@
�@�����n��R����̘A�g���ƂƂ��āA�����Q�R�N�x�����n��R���ꎖ���E���i��C���j���C��A�L�����������
�X���P�R���i�j�ɊJ�Â���܂����B
�@�{���C�́A�����E���i��C���j��ΏۂɁA�R�~���j�P�[�V�����\�͂̌���ƍ���Ԃ̌𗬂�}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A�L��
����A�k��B����y�і{�Z�̎�C�P�O�����Q�����܂����B
�@���C�ł́A�{�Z�̏������ꎖ�������ɂ��u�����E���̎��ȓ_���E���ȕ]���ɂ��āv�̍u���Ɓu���X�N�}�l�W����
�g�v���e�[�}�Ƃ����O���[�v���[�N���s���A�E��ɂ����郊�X�N�}�l�W�����g�̏d�v���ɂ��Ď�C�Ƃ��Ă̔F����[
�߂�ƂƂ��ɁA���i���܂�ڐG���邱�Ƃ̂Ȃ��R����̐E�����ӌ������������ɍs���܂����B �@ ���C��̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
����̌����w���J�� �@
�@�{�Z�ł́A�W���P�V���i���j�y�тP�W���i�j�ɒ��w����ΏۂɁA������l�X�Ȏ����������A�����ʂ��Ė{�Z�̂T�w
�ȋy�ш�ʉȖڂ̎��Ƃ�̌����Ă��炤���Ƃ�ړI�Ƃ����u����̌����w�v���J�Â��܂����B����ԂłT�W�W���̎Q����
������A���x�݂ɂ͍݊w���ɂ��w�Z�s���̐������s���܂����B�܂��A�Z���ɐ݂����i�H���k���ł́A�ی��
���狳���֑����̎��₪���A���ڑΘb�ł���悢�@��ƂȂ�܂����B
�@�Q���������w������́A�u�݊w���̐����ɍD�����������B�v�A�u��̓I�Ȏ������ł��ꂼ��̊w�Ȃ̓������킩�����B�v�A
�u����ƕ��ʍ��Z�̈Ⴂ���킩�����B�v�Ȃǂ̐���������D�]���܂����B �@ �������y���ޒ��w���̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�����Q�R�N�x��U�ȃT�}�[���N�`���[�����{ �@
�@�{�Z�ł́A�W���Q�Q���i���j����W���Q�U���i���j�ɂ����ċ@�B�H�w�̊�b�m��������U�ȂP�A�Q�N����ΏۂƂ��A�@�d
�n�T�}�[���N�`���[�u���̂Â���̌��ꂩ��v�����{���܂����B
�@�@�����N�`���[�́A���ۂ̂��̂Â���̌����ʂ����u���A���K�A���K�A���w����J�Â��A��U�Ȑ��Ƃ��Ă̎����̌�
���}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ł��B����͖{�Z����̂P�S���ȊO�ɍ����ۍ��ꂩ����Q���̎Q���҂�����A�w�Z�̘g
���Č𗬂�[�߂܂����B
�@�P���ڂ͓����N�`���[�̎Q���҂̂ق��ɐ�[�H�w���_�̗��C�҂Q�R���������A�u���̂Â���Ɋւ���u���v�Ƃ��āA��
����ЎO���̍����q���A�E������Г������쏊�̏����q�����E���V�o�����@�튔����Ђ̔�i�_�L���̂R���̍u
�t�����ۂ̂��̂Â���̌���Ƃ��ꂩ��̓W�]�ɂ��Č���܂����B
�@�Q�A�R���ڂ́u���̂Â��艉�K�v�ł͊�����Ѓg���^�v���_�N�V�����G���W�j�A�����O�ɂăG���W������g���ĂɊւ���u
�`���A���K���s���܂����B
�@�S���ڂ́u�H�ꌩ�w�v�ł́A���b�N�X������ЂƓ��{���b�|������ЂɂāA���[�^���[�W���C���g�┭�d�@�̃��[�^��
�ǂ̐�����������w���܂����B
�@�ŏI���ɂ͋ߔN�̂��̂Â���v���Z�X�ŕ��y���Ă���RD�\CAD���g���A�����v�ɂ��Ċw�т܂����B
�@��T�Ԃɓn��u���ł������A��u������U�Ȑ�����́u�ƂĂ��g�ɂ����Ƃ���ŁA�{���ɏ[���������̂ł����B�v��
�̊��z���悹���܂����B �@ ���̂Â���Ɋւ���u���i��i�j�ƂRD-CAD���K�i���i�j�̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
��P�P�����s�c��c����@�c�����C��ɂē��c��r�������u�� �@
�@�W���Q�S���i���j�ɐ������z�[���ɂđ�P�P�����s�c��c����@�c�����C��s���A�{�Z���瓡�c��r��
���i�@�B�H�w�ȁj���u�t�Ƃ��ĎQ�����A�u���u���E�G�l���M�[�Ƃ܂��Â���̃f�U�C���v���s���܂����B
�@�u���ł́A�Z�p�̐i���ɂ�萶�������コ����u���́v�A�R���p�N�g�Ȃ܂��Â���ɂ��V�����c�݂�U������u���Ɓv�A
�s���E��ƂȂǗl�X�ȗ���ʼn��P�Ɏ��g�ށu�ЂƁv�̂R�_����݂��܂��Â���̐����⎖��Љ���s���܂����B �@ �u�����s�����c���� �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
��������R���\�[�V�A���v���Ď�Á@��Q�w�Z�����������K�u�����J�� �@
�@�{�Z�ł́A���Z���܂ދv���Ďs���T�̍�������@�ւɂ��\������u��������R���\�[�V�A���v���āv���Ƃ̈�
�Ƃ��āA��N�x�̕��ː��u���Ɉ��������A��Q�w�Z�����������K�u���u�}���̐����ɂ��Ċw�ڂ� -���R
���Ɛ����p�ɂ��Ă̍u�`�Ǝ��K-�v���W���W���i���j�ɊJ�Â��܂����B
�@�u���ɂ͎s���̒��w�Z���ȋ����S�T�����Q�����A�}���h�Ў{�݁w����߃E�X�x�̐쓇�r�Ȏ����u�}���ł̊�
����v�ɂ��āA��������L�搅����ƒc�̏��{���v�{�ݕ������u�}���̐������̗��p�]�������̐����Ɛ��]�v
�ɂ��ču�`���s��ꂽ��A�{�Z���猤���x�����̌����L�F���Z�p���y�ё�O�Z�p�O���[�v�̋Z�p���E���̎w
���ɂ�鐅�̕��͎��K���s���܂����B
�@���̕��͎��K�ł́A�}���㗬�����̎悵������s�̂̃~�l�����E�H�[�^�[��p���āA���̍d�x���L���[�g�H��@
�ɂ�苁�߂܂����B
�@�����ɖ��ڂɊW���Ă���}���̐������ނƂ����u���Ƃ������ƂŁA�Q���҂���́u�}���̊��ɂ��ď�
�߂ĕ����b�����������[�������v�A�u�����Ǘ����ǂ̂悤�ɍs���Ă��邩���ɂȂ����v�A�u�d�x�̎��Ӗ���������
��̓I�ɗ����ł����v���̊��z���悹���܂����B �@ �u���ƕ��͎��K�̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�Љ�l�Z�p�Ҍ������ԉ��H���K�����{ �@
�@�{�Z�ł́A��B��w�������j�l�ށi�R�A�E���[�_�[�j�琬�v���O�����u���Ԑ����R�[�X�v�J���L�������y�ѓ��{���ԍH
�Ɖ��JGMA�M���J���b�W�u�}�X�^�[�R�[�X�v�i��b�R�[�X�j�̈�ł��鎕�ԉ��H���K���W���S���E�T���̂Q���Ԃɂ킽
��S�����čs���܂����B
�@�����K�́A���Ԑ����ɂ������ՋZ�p��m�E�n�E���K�����A����ɐ�[�Z�p�Ƃ̗Z�������ʂ����Ԑv�Z�p�҂̈�
����ڎw�����̂ŁA���K�ɂ͎Љ�l�R�S�����Q�����A���ԉ��H���K�Ƃ��āA�n�C�X�z�u��E���d�z�u��E���ԑ��蓙
�̉��H���K���s���܂����B
�@�Q���҂͔M�S�ɍu�t�̐������ƍH��������������ȂǁA���Ȍ��s�ɗ��ł��܂����B �@ �u�t�̐����ɔM�S�Ɏ����X����Љ�l�Z�p�� �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
��X��S������e�N�m�t�H�[�����ɎQ�� �@
�@�@�S���̍���̎Y�w���A�g�S���҂��ꓰ�ɉ�čs����u��X��S������e�N�m�t�H�[�����v�������Q�R�N�W���S��
�i�j�ɁA�����̊w�p�����Z���^�[�ɂ����Ċ֓��M�z�n�捂�ꂪ�S�����ĊJ�Â���A�{�Z���Q�������܂����B
�@���̃t�H�[�����ɂ́A�{�Z���琧����H�w�Ȃ̏����������u�N���[���f�B�[�[���ԊJ���̂��߂̂R���������q�g��
�O���t�B�@�̊J���v�Ɓu�ԍڃJ�����ɂ�����R���s���[�^�r�W�����Z�p�Ɋւ��錤���v�̂Q�̃e�[�}�ɂ��āA�|�X�^�[��
�W�����A�u�[�X��K�ꂽ����̌����҂��ƊW�ғ��ɑ��ĔM�S�ɐ������s���Ă��܂����B �@ �p�l�����g���������s���������� �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
���w�������̌��J�u���u�\�[���[�J�[����낤�I�v���J�� �@
�@�{�Z�ł́A���w�������̌��J�u���u�\�[���[�J�[����낤�I�v���W���S���A�T���̂Q���Ԃɂ킽��J�Â��܂����B
�@���u���ɂ́A�v���Ďs���y�ыߍx�̒��w���Q�O�����Q�����A�P���ڂɂ͑��z�d�r�̎d�g�݂�\�[���[�J�[�̃V�X�e
���ɂ��Đ���������A�u�t��w��TA�ɋ����Ȃ���ԑ̖{�̂̐v�Ɛ��}���s���A�Q���ڂɂ͐v�����}��
����ɃX�`�����{�[�h�����H���ă\�[���[�J�[�삵�A�X�^�[�g����S�[���܂ł̑����������X�s�[�h�R���e�X�g�ƌ�����
�̊i�D�悳�������f�U�C���R���y�e�B�V�������s���܂����B
�@�Q���҂́A�����̎v���`�����\�[���[�J�[�����A���ۂɓ������Ă݂邱�Ƃł��̂Â���̓����ʔ������w��ł�
�܂����B �@ �}�ʂ���Ƀ\�[���[�J�[���쐻���Ă���l�q�ƃR���e�X�g�̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
���w�������̌��J�u���u�G���N�g���j�N�X�T�}�[�X�N�[���v���J�� �@
�@�{�Z�ł́A���w�������̌��J�u���u�G���N�g���j�N�X�T�}�[�X�N�[���v���W���Q���A�R���̂Q���Ԃɂ킽��J�Â��܂����B
�@���u���ɂ́A�v���Ďs���y�ыߍx�̒��w���Q�T�����Q�����A�P���ڂɂ͍u�t��w��TA�ɃT�|�[�g����Ȃ��烉�C���g
���[�X�J�[��g�ݗ��āA�X�^�b�t�����̓���R�[�X�𑖔j����^�C���g���C�A���Ŋ����x��`���[�j���O�̐��ʂ�����
�܂����B�Q���ڂɂ̓u���b�h�{�[�h���g�����d�q�I���S�[���삵�A�d�q�I���S�[�������t�҂Ɗy���̖������}�C�N��
�R���s���[�^�Ŏ������Ă��邱�Ƃ��w�т܂����B�܂��A�G���N�g���j�N�X�̊�{�ƂȂ�A���̓}�O�l�b�g��R���f���T���g��
���d�C�⎥�C���ۂ̃f�����X�g���[�V�����͐V�N�ȋ����̑̌��ł����B
�@�Q���҂́A��H�̒����Ɠ���e�X�g�̌J��Ԃ��ɋ�킵�Ă��A�g���[�X�J�[���v���悤�ɓ��삷��Ƒf���Ȋ����āA
�d�q�Z�p���邱�Ƃ̖ʔ������w��ł��܂����B �@ ���C���g���[�X�J�[�̒����Ɠ���e�X�g���s�����w������ �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
���w�������̌��J�u���u���Ȃ�������T�C�G���e�B�X�g�v���J�� �@
�@�{�Z�ł́A���w�������̌��J�u���u���Ȃ�������T�C�G���e�B�X�g�v���V���Q�V������Q�X���̂R���Ԃɂ킽��J�Â���
�����B�Q�V���ɂ͐��w�R�[�X�Ƃ��āu�̌��I���w�����_�[�����h�v�A�Q�W�`�Q�X���ɂ͗��Ȏ����R�[�X�Ƃ��ĕ����p�[�g�u�G
�R���W�[���W�I�i�d�r�̂���Ȃ����W�I�j������Ă݂悤�v�Ɖ��w�p�[�g�u�����I�I�Ƌ����s�v�c�Ȍ��ۂ�̌����悤�v�̂Q
�̃p�[�g���J����A���ꂼ��̍u���ɋv���Ďs���y�ыߍx�̒��w���Q�O�����Q�����܂����B
�@�Q���������w���B�́A���w�R�[�X�ł́A�}�`�������Ƃ͈Ⴄ���_����̑������ŃO���[�v����������A�O�����̒�
�����g���ăs�^�S���X���ɂ��Ċw��A�������̊J�����ɂ��Ċw�т܂����B���Ȏ����R�[�X�ł͕��i�͂��܂�g
�����Ƃ̂Ȃ���ނɈ���ꓬ���Ȃ�����A���W�I�삵����A�l�X�ȉ��w�����������ő̌������肵�܂����B���w�◝
�Ȃɂ��Ă̋����E�S�����߂Ȃ���u�����y����ł��܂����B
�@ �u���̗l�q�i�����琔�w�R�[�X�A���Ȏ����R�[�X�����p�[�g�A���Ȏ����R�[�X���w�p�[�g�j �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
���C�@�֎Ԑ��`�i�����͌^�j��V�̓��c�����قɂēW�� �@
�@���c�s���c���̓V�̓��c�����قɂ����āA�V���Q�R������u�Ȃ����̕��i�E�}��O���W�v�Ƒ肵�����W���J�Â���
�Ă���A���̊��W�ɁA�����ق���˗����A�{�Z�����삵���u���炭��V�E�q��v�̏��C�@�֎Ԑ��`�̕����͌^��
�W������Ă��܂��B
�@���ɂ��吳���ォ�珺�a���߂܂ŕ������v���Ďs�|�啪�����c�s���c����S�H�Ō��}��O���̓����̎ʐ^
�⎑���A�╨�Ȃǂ�W������R�[�i�[��A���̃N���C�A�[�e�B�X�g�E�Y�c�e�q����ɂ���i�W�uClay Trains�v��JR
�v��{���̎ʐ^�W���W������A�������̓W���i������ł��܂��B
�@�V���R�P���ɂ͊֘A�C�x���g�Ƃ��āA�{�Z�̓c����y�����E�R���F�A���Z�p���炪�W�����Ă�����C�@�֎Ԑ��`���g
������������C�@�֎Ԃ̎d�g�݂ɂ��Ẳ�����s���܂����B�C�x���g�ɖK�ꂽ�ό��q��n���̕��X�́A��������
����Ȃ�����͋��������@�֎Ԃ�M�S�Ɍ��w���Ă��܂����B
�@�Ȃ��A���̊��W�͂W���R�P���܂ŊJ�Â���Ă��܂��B �@ �u���炭��V�E�q��v�̏��C�@�֎Ԑ��`�̎����̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�m�I���Y�t�H�[����in�v����2011�Ɋw�����Q�� �@
�@�V���P�R���i���j�ɋv���Ďs�A�i���j�v���ăr�W�l�X�v���U�A�v���Ēm�I���L���Z���^�[����Â���m�I���Y�t�H�[����
in�v����2011���J�Â���A�{�Z����́u��[�H�w���_�v�̎��Ƃ̈�Ƃ��āA��U�ȂP�N����R�O�����Q�����܂����B
�@��U�Ȑ��́A���i�̎��ƂƂ͈Ⴄ�A��Ƃ���̖ڐ��ł̔��\��^���Ƀ��������Ȃ��璮�u���Ă��܂����B
�@���̃t�H�[�����ł́A�}���Ȍo�ϔ��W�𑱂��钆���ɑ�����{��Ƃ̍���̉ۑ�ɂ��Ă̍u����A�v���Ă̒n
����Ƃ̒m�I���Y�̌��ʓI�Ȋ��p���@��C�O�W�J�헪�̎��ᔭ�\������܂����B �@ �t�H�[�����̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�}�����ɂăe�[�u���}�i�[�u�K����J�� �@
�@�}�����ł́A�U���Q�U���i���j�̒��H���Ԃɗ��̐H���ɂăe�[�u���}�i�[�u�K����J�Â��܂����B
�@���N�x����V���ɐH�猎�Ԃ̎�g�݂̈�Ƃ��āA�w�����H�Ɩ����ϑ����Ă���i���j�������{�Ћ�B�x�Ђ̋���
�̉��A�e�[�u���}�i�[�Ɩ]�܂����H�K���̒m�����K�����A�H��ʂ����R�~���j�P�[�V�����𑣐i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�S�A
�T�N���̗�����ΏۂɊJ�Â������̂ł��B
�@�u�K��p�ɃZ�b�e�B���O���ꂽ�e�[�u���A�N���V�b�N��BGM�������Ƃ͈Ⴄ���͋C�̒��ŁA�Q�S�������m�����̃t��
�R�[�X�����\���܂����B
�@�u�K����A�ْ��̂��܂�u����H�ׂ����킩��Ȃ��B�v�Ƃ�������������܂������A�i�i���鍂�ꐶ�Ƃ��Ẵ}�i�[
��g�ɂ���悢�@��ƂȂ�܂����B
�@����͘a�H�̍�@�ɂ��Ă��s�����Ƃ��������Ă��܂��B �@ �e�[�u���}�i�[�ɂ��Ċw�ԗ����B �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�}����TA���x�����{ �@
�@�}�����ł͕����Q�P�N�x��藾��TA(Teaching Assistant)���x��݂��Ă��܂��B
�@������i�\�����F���w�������j�����S�ƂȂ��Ď����I�Ɏn�߂����x�ŁA���T���j���̌ߌ�X������P�O���܂ł̖�P��
�ԁA���̐H���ɏ㋉��������TA�ƂP�N���S�����W�܂�A�w�ӎ�����E���̏K���Â��E��w�N�ł̊�b�w�͌����
�ړI�Ƃ��A�㋉�����牺�����֏����E�A�h�o�C�X�Ȃǂ��������������Ă��܂��B �@ �^���Ɏ��g�ޗ����B �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�}�����ɂē��k�����L�����y�[�������{ �@
�@�{�Z�ł́A�w�����H�Ɩ����ϑ����Ă���i���j�������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂ŁA�U���P�S���i�j�ɓ����{��k�Е����x
���Ƃ��āu���k�����L�����y�[���v�����{���܂����B
�@���̎�g�݂́A�u�H�ׂĉ������悤�I����낤���k�I�I�v�Ƒ肵�A���S�ȁu�ЂƂ߂ڂ�i�������Y�j�v�Ɓu���݂��i�{��
���Y�j�v���g�������H�𗾐��ɒ������̂ł��B���k�n���Ő��Y���ꂽ�H�ނ�L�����p���邱�Ƃɂ��A�������Вn
����������\��ł��B
�@�܂��A��k�Ђ⌴�����̂����������ɕK�v�ƂȂ�\���̍����ď�̓d�͕s����̈ӎ��t�������˂āA���̘L��
�̌u�����̔�����P�����܂����B��N�x���A�ߓd��Ƃ��ĘL���̏�铔��LED�d���Ɏ��ւ��Ă���A���킹�ĔN��
�Ŗ�3��kWh�i�d�C���� ��3���~�ACO2�r�o�� ��1�g���j��ߓd�ł����v�Z�ɂȂ�܂��B�Ȃ��A���̐ߓd�ʂ́A���̔N��
�d�͎g�p�ʂ̖�3���ɑ������܂��B �@ �}�����̐H���Ŕ�Вn�̐H�ނ��g�������H���Ƃ闾���̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
����@�\�ї��������{�Z�����@ �@
�@�Ɨ��s���@�l�����������w�Z�@�\�̗їE��Y�������́A����U���W���ɖ{�Z�����@���܂����B
�@�{�Z�ł́A��c�Z������w�Z�T�v����������A���ȏȋ���f�o�ɍ̑����ꂽ�u�b�h�l�r�����p�����@�B�v�f�v��
�Y�w�A�g�v�̎�g����K�H��A�Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[�A�}���ًy�ѓ�����L�O�ق�M�S�Ɏ��@���܂����B
�@���@��A�ї������͖{�Z���E����ΏۂɁA�u����̍��x�����l����|�Ȋw�E�Z�p�ɑ���ӔC����|�v�Ƒ肵�āA�n
��\�N���}�������ꐧ�x�̎Љ�̕ω��ɑΉ���������݂̍���ɂ��ču�b���s���܂����B��\�l���鋳
�E�����o�Ȃ��A���i���ڕ�����@��̏��Ȃ��������̔M�ӂ̂��������b�ɕ��������Ă��܂����B���@�ɂ͋@�\�{����
�{�q���ے������s���܂����B �@ ���@�ƍu�b���s����ї����� �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�����Q�R�N�x�̑O�����Ղ��J�Â��܂��� �@
�@�}�����ł́A�T���Q�W���i�y�j�ɕ����Q�R�N�x�̑O�����Ղ��J�Â��܂����B
�@���Ղ́A�����Ԃ̐e�r��[�߁A��薾�邭�A�܂��c���͂̂��闾�֔��W�����邽�߂ɁA���N�t�ƏH�ɊJ�Â��Ă���A
����̓{�E�����O���ƃo�[�x�L���[���s���܂����B
�@�����͂����ɂ��̑�J�ł������A70�l���̗������Q�����A�R�Q�[���̃X�R�A���������M�����������J��L����ꂽ��
�ʁA������U�ȂQ�N�̐A�����D�����܂����B
�@�{�E�����O���ł͊J�n���x�ꂽ��A�o�[�x�L���[�ł͐H���ɉ����[��������ƃn�v�j���O������܂������A������
���傢�ɐ�����A�e�r��[�߂Ă��܂����B
�@�y���Ղ̔�p�́A�����̂��ݕ��ʉ���O��ɂ��A�팸���ꂽ��������Ƃɍs���Ă��܂��B�z �@ �O�����Ղ̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�g�c�w�p����U����w�p������̑�����܂��� �@
�@�S���P���Ɍ��v���c�@�l�g�c�w�p����U����w�p������̑��悪�Z�����ōs���܂����B�{�N�͓����{��k�Ђ�
�ӂ݁A�ꓰ�ɉ�Ă̑��掮�͍s�킸�A�Ώې��K��Čʂɑ��悳��Ă���Ƃ̂��Ƃł����B
�@�{�N�x�́A�{�Z�ł͍ޗ��H�w�Ȃ̉��R�����E��ʉȖځi�����j�̎R���y�����E�d�C�d�q�H�w�Ȃ̑��y�����̂R��
�ɂ��u�M�d�E���d�G�l���M�[�ϊ������������n�C�u���b�h�ޗ��̊J���v���I�l����A�g�c�w�p����U����̋g�c����
�����������\�҂ł���ޗ��H�w�Ȃ̉��R�����Ɍ���ʒm���Ɩژ^���������܂����B����ɂ́A���U����̑���
���q�����ǒ������s����܂����B
�@�g�c�w�p����U����́A���ɋ�B�d���i���݂̑�d������Ёj��ݗ�����āA�d���ƊE�̔��W�͂��Ƃ��A �q��
���ʎ��ƂȂǍL���Y�Ƃ̐U���ɑ���̌��т����ꂽ�̋g�c���厁���A���a60�N�Ɏ����𓊂��đn�݂������v���c�@
�l�ŁA���������ʼnȊw�Z�p�̐�i�I�Ȍ����Ɏ��g�ސV�i�C�s�̌����҂ւ̊w�p������A�������k�̖L���Ȑl��
������ދ���Ɏ��g�ފw�Z�̓��F����w�K�����ɑ���U�����������͂��߁A���w���A�}�����̑���Ȃǂ̊���
���s���Ă����܂��B �@ �g�c�������ɂ��w�p������̑��� �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�d�グ��Ǝ��Z�u�K����J�u �@
�@�{�Z�ł́A�d�グ��Ǝ��Z�u�K����T���P�S���ɊJ�u���܂����B
�@���̍u�K��͎d�グ��ƂɕK�v�Ȋ�{�I�ȋZ�p���K������ƂƂ��ɁA�@�B�g�ݗ��Ďd�グ�Z�\���莎���i�Q���j����
�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ĊJ�u���ꂽ���̂ŁA�Z�\���莎�����i��ڎw���Љ�l�E��ƋZ�p�҂���u����܂����B
�@�u�K��ł́A�n�z���猤���x�������̈��A�̂��ƁA���猤���x�����̍���Z�p���E�������Z�������A��u
�҂̋Z�\���x����i����c�����Ȃ���A�ʂɂ��ߍׂ₩�Ȏw�����s���܂����B
�@���̍u�K��́A�Z�\���莎�����O�̂V���Q�R���܂őS�U��ɓn���ĊJ�Â���܂��B �@ �d�グ��Ǝ��Z�u�K��̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
�n�k�ƉЂ�z�肵���h�Б����P�������{ �@
�@�{�Z�ł́A�T���Q�T���ɋv���Ďs���h��������̌��A�k�x�T���̒n�k�ɂ��Д�����z�肵���h�Б����P����
�s���܂����B�h�Б����P���́A�n�k��������В��܂ł̈�A�̗�����V�~�����[�g���A�w���⋳�E���֖h�Ύv�z
�̕��y����э��g��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ŁA�w���Ƌ��E�����킹�Ė�P�P�O�O�����Q�����܂����B
�@�P���ł͏�c�Z������{�����Ƃ����E���ɂ�鎩�q���h�c����������A���{�v�̂ɉ����Ĕ��s���܂����B
�@���I����́A���h�����ɂ����Ί�̎g�p���@�̐������A3�N���A4�N���A5�N���A���E���̏��ɏ��Ί푀
��P�����s���A���h�������P���S�̂̍u�]���s���܂����B
�@�Ō�ɏ�c�Z������̂������������āA�����I�����܂����B �@ �h�Б����P���̗l�q �@ �@
�@ ����23�i2011�j�N�x
���_�����̍����^�������s �@
�@�{�Z�ł́A�T���Q�S���ɍZ�����ɂ����Ė��_�����̍����^�������s���܂����B
�@���^���ł́A�R���R�P���t���Ŗ{�Z��ސE���ꂽ�������Y�������ɑ��Ė��_�����̏̍������^����A��c�Z����
��؏�����n����܂����B
�@���^���̌�ɂ́A��c�Z�����獡�܂ł̂����J�ɑ��Ă̎ӈӂ��q�ׂ���ȂǁA�I�n�a�₩�ȕ��͋C�̒��ʼn�b
���e��ł��܂����B
�@�y�����搶�A���N�ɂ킽��{�Z�̂��߂ɂ��s�͂�������A���肪�Ƃ��������܂����B�z ���_�����̍����^���̗l�q �@ �@ �@ ����23�i2011�j�N�x
�w�����ɂ����ăw���X�`�F�b�N�����{
�@���̊��́A�����̐H�������`�F�b�N����ƂƂ��ɁA���X�̓��̓I�E���_�I�ȃX�g���X�ɑ��āA�K���������H����ۂ�
���Ƃ̑�����[�����邽�߂ɁA�w�����H�Ɩ����ϑ����Ă���i���j�������{�Ћ�B�x�Ђƃ^�C�A�b�v���čs��ꂽ����
�ŁA�w���X�`�F�b�N�ɂ͒��H���I���������̊O�A��c�Z����]�藾���厖���͂��߂Ƃ��鋳�E�����Q�����A�r���s���
�ł���ȂǑ傢�ɐ���オ��܂����B
�@����̃w���X�`�F�b�N�ł́A�����g�@��p�������̌��N�`�F�b�N�ƁA�w��̖����̕ω�������̓I�E���_�I�X�g���X�x
������E�������_�o�̋@�\��ԁA���ǔN��Ȃǂׂ鐄�茌�ǔN��X�g���X�`�F�b�N�̂Q�킪�s���A����������
�`�F�b�N���I������ɐ��̉h�{�m��������E�w�����Ă��܂����B �@
�w���X�`�F�b�N�̗l�q �@ �@ ����23�i2011�j�N�x
�����Q�R�N�x���w�������s
�߂��V�����Q�P�R���A���w���Q���y�ѐ�U�Ȑ��S�W�����}���{�Z���̈�قŋ��s���܂����B
�@���J�̍��̉��A�䗈�o�̎R��㉇����͂��ߌ㉇������̕��X��V�����̕ی�ҕ��тɖ{�Z���E�����Q��
�钆�A���ł͐V�����A���w���A��U�Ȑ��ЂƂ�ЂƂ�̖��O���Ăяグ���A��c�Z�������w�����܂����B
�@�V�����ْ͋������ʎ����ł������A���ꂩ��̍��ꐶ���Ɋ�]��c��܂��Ă��܂����B �@
���w���̗l�q �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
�����Q�R�N�x�`�|�r�s�d�o��W��������J��
������J�Â��܂����B
�@������ł́A�u�t�Ƃ��Ăi�r�s�C�m�x�[�V�����v���U�����̌������s���������A�S�̂̊T�v����A�\�����쐬�̗��ӎ�
���A���̑��̌��咆���Ƃ̏Љ�ɂ��Đ���������܂����B���i�Ȃ��Ȃ��Ȃ��R�����s��������̈ӌ����@��
�ɁA�o�Ȃ�����������́A�\���ɂ������Ă̑����̎��₪���܂����B
�@�܂��A�������ɂ͌ʑ��k���s���A�\���������ۂɌ��ăA�h�o�C�X�����ƂĂ��L�Ӌ`�Ȃ��̂ƂȂ�܂����B �@
������̗l�q �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
��R��e�c��c�u�L�����p�X�n���X�����g�̖h�~�ɂ��āv���J��
�X�n���X�����g�̖h�~�ɂ��āv�Ƒ肵���u������J�Â��܂����B
�@�u���ł́A�ٔ��ł̎���������A�n���X�����g�ɂ��Ă̊�b�m����A�ǂ̂悤�Ȍ������n���X�����g�ɂȂ肤�邩
���̏ڂ���������A�h�o�C�X���s���܂����B
�@���̍u����ɂ͂T�V���̋��E�����Q�����A�E�����A�w���w���̂�����Ȃǂ��������ǂ��@��ƂȂ����Ƃ̈ӌ���
�������A�L�Ӌ`�Ȃ��̂ƂȂ�܂����B �@
�u�����s�����a��ٌ�m �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
���C�@�֎Ԑ��`�i�����͌^�j���v���Ďs��������j�����قɂēW��
��A���̊��W�ɁA�����ق���˗����A�v���č��ꂪ���삵���u���炭��V�E�q��v�̏��C�@�֎Ԑ��`�̕����͌^
���W������Ă��܂��B
�@���̊��W�́A��B�V�����J�Ƃɕ����ĊJ�Â��ꂽ���̂ŁA�W���R�[�i�[�ɂ́A����������珺�a�����ɂ����ċv
���Ďs���܂ޒ}��n��𒆐S�ɉ^�s���Ă����O����S���̗��j�ɂ��ďЉ��R�[�i�[��A�u���炭��V�E�q��v��
�Ă�A��ɓ��ł�n�݂������y�̐�B�ł���c���v�d�������삵�����{���̏��C�@�֎Ԑ��`���Љ���R�[�i�[
�����݂����A���Z�̕����͌^�ɂ��Ă��w�|���̏ڂ������������Ƃ��ł��܂��B
�@�����ق�K�ꂽ���َ҂́A�����Ɏ����X���Ȃ��瓯�Z�̕����͌^�������[�����߂Ă��܂����B
�@�Ȃ��A���̊��W�͂T���P�T���܂ŊJ�Â���Ă��܂��B �@
�W���̗l�q�Ƒ�����j������ �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
����f�o�ŏI���ʕ���J��
�v�ƎY�w�A�g�v�̂R�N�Ԃɂ킽���g�̍ŏI���ʕ���A����O����\����ɓ��Z�ŊJ�Â��܂����B
�@����́A��܉�f�o�t�H�[�����Ƃ��Ĉʒu�t�����A��c�F�Z���̊J��A�ɑ����A�@�B�H�w�ȋ�������A
�S�̓I�Ȏ�g�̐��ʂ�e�S�������̋�̓I�Ȏ��{���e�ɂ��Ă��ꂼ����������ق��A�F�{�������w�Z��
�c���T��y�����A�����Z�p�Ȋw��w�̋{���K�Y�y�����ɂ��A���ꂼ��̍���E��w�ɂ�����@�B�v���̂Â��苳
��̌���Ȃǂɂ��Ă̍u�����s���܂����B
�Q��������\���̊w�����ƊW�҂���́A�u��������̂悤�Ȏ�g�𑱂��ė~�����v�A�u�Y�w�A�g�ł��̂Â����
��グ�����v���̈ӌ������A�D�]���܂����B �@
��T��f�o�t�H�[�����̗l�q �@ ����22�i2010�j�N�x
��S�U��{�ȑ��Ǝ��A��P�V���U�ȏC���������s
���n�k�̋]���҂ɑ���ٓ��̌�A���l�ȕ��͋C�̒��A��c�Z������{�ȑ��Ɛ��P�X�O���A��U�ȏC�����R�T���ɑ�
�Ə؏��������^����A�������A�\�����ɂ����Ċw�Ɛ��їD�G�Ȏғ��ɕ\�����^����܂����B���T�I����ɂ͑s
�s��J����A�{�ȑ��Ɛ��y�ѐ�U�ȏC�����̖�o���j���܂����B �@
���Ə؏����^�̗l�q �@ ����22�i2010�j�N�x
�u����E�p�l�����_��u�d�C�E�G�l���M�[����Ŋ��鍂�ꑲ�Ɛ��v���J��
�Ɛ��v���R���V���ɋ�B�p���[�A�J�f�~�[�Ƃ̋��ÂŊJ�Â��܂����B
�@�u����ł́A��B��w��w�@�V�X�e�����Ȋw�����@�������y�����i�����P�P�N�x���j���u�i�w�Ƃ����I�����]
����E��U�Ȃ����w�E��w�@�ց]�v�A��B�d�́i���j���c�������i�����Q�P�N�x���j���u�A�E�`�Љ�l�ɂȂ�ɂ�����
�ā`�v�ƍ��ꂩ��̐i�w�ƏA�E���ꂼ��̖ڐ����u�����s���܂����B
�@�p�l�����_��ł́A��B��w��w�@�V�X�e�����Ȋw�����@���̑�C����Y���A���J��^�玁�A�������L����
�R�����������T���̍u�t�ƏA�E��C�ł���v���č���d�C�d�q�H�w�ȋ{��_��y�������A���ꂩ��̐i�H�����
�ۂ��ėL�v�ȏ����������A�Q�������w������́A��ϗǂ���悾�����A���ɗ��������̊��z���������܂����B �@ �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
���X��Z��܂��Â���^�c���c��A�Z����N�琬���c��A���X�쏬�w�Z�������K
���X�쏬�w�Z ���X�؉��Z�����A�{�Z �Z����K�₳��܂����B
�@�{�Z ���㕔 ��\�ږ�̐ԒˍN����y�ї��㕔�̊w�����A�P�����{�����P�����ɂ킽��A���X�쏬�w�Z��
�q�ǂ������̋v���Ďs���N���S�琬�w�`���Ɍ��������K�̎w���ɋ��͂������Ƃɑ��邨�炪�q�ׂ��܂����B
�@�w��������Q�O�l�̏��X�쏬�w�Z�T�E�U�N���̑I�肽���͔������āA�Q���Q�O���ɊJ���ꂽ�w�`���ł́u�^
�C�����i�܁v����܂��A���ʂ���N����傢�ɖ��i���ꂽ�����ŁA��ϊ��ł����A���N���܂����肢������
�|�̗v�]������܂����B �@
�ʐ^�́A���X�쏬�w�Z�̎����ƒS�C�̐搶������̎莆��͂��ɖ{�Z��K�ꂽ�Ƃ��̗l�q �@ ����22�i2010�j�N�x
����f�o�]���ψ�����J��
�����@�B�v�f�v�ƎY�w�A�g�v�̍ŏI�N�x�ɂ�����A�{��g�̐��ʂɂ��ĊO���̗L���҂������A�]���Ə�����
���߂̋���f�o�]���ψ�����Q���P�S���ɊJ�Â��܂����B
�@���ψ���ł́A��c�Z���ɂ�鈥�A�̌�A�ψ����ɑI�o���ꂽ���͋�B��w��w�@�y�����ɂ��c�����i�߂��A
��g���ƐӔC�҂ł���@�B�H�w�Ȃ̓��c��������A�{��g�̖ڕW�ł���u�R�c-�b�`�c��p�����@�B�v�f�v������
�S�Ƃ����@�B�H�w����̉��P�v�ɑ����g�̒B����ʁA����ɔ������J�u�����̎Y�w�A�g�����ɂ��Ă�
�������s���܂����B
�@�o�Ȃ����ψ�����́A�{�Z�̎��H�I�Ȑv�Z�p�҂��琬���邽�߂̎�g�ɑ���A�����]���ƍ���Ɍ����Ă̋M
�d�Ȉӌ������܂����B �@
����f�o�]���ψ���̗l�q �@ ����22�i2010�j�N�x
�m�I���Y�Ɋւ���u�K����J��
�B�l�[�^���u�t�Ɍ}���A�m�I���Y�Ɋւ���u�K����J�Â��܂����B���̍u�K��ɂ́A���E���S�W�����Q�����A�������{
������������{�������̐��ڂƍ�������@�\�̌���A�o�肩������o�^�܂ł̊�{�I�ȗ���A�_�����\�ɂė�O
�K�����ۂ̗��ӎ�����A�m�I�n���T�C�N���̔��W�������������������̌_��Ȃǂɂ��Đ���������A�܂�
�u�K��ɂ͌ʑ��k����݂����܂����B����̍u�K�́A�����o�肾���łȂ��������{���̊l���ɂ��Ă��l�����
���@��ƂȂ�܂����B �@
�u�K���s������������R�[�f�B�l�[�^ �@ ����22�i2010�j�N�x
�u�_���H�e�N�m�u���b�W�Q�O�P�Oin�v���āv�ɂ����Č����V�[�Y�\
�b�`�����A���i�J����V�����r�W�l�X�W�J�����邽�߂̓����r�W�l�X�s�ł���u�_���H�e�N�m�u���b�W�Q�O�P�Oin�v���āv
�ɂ����āA�{�Z�̌����V�[�Y���\���s���܂����B
�@���̔��\��́A���������B�o�ώY�Ƌǂ���Â������̂ŁA�{�Z����͐������p���w�Ȃ̈ɓ��`���������u�I�]
���[�U�p�E�`�i�t���[�]���j�v�ɂ��āA����܂ł̐��ʂ�i���Ɏ���o�ܓ��\���܂����B�������ʂ�W�������u
�[�X�ł́A�����̊�ƒS���҂���E�ۗ͂̋����I�]���𗘗p�����N�x�ێ��Z�p�Ȃǂɂ��Ď��₪�������܂����B �@
���\���s���ɓ��`�������i�������p���w�ȁj �@ ����22�i2010�j�N�x
�{�Z�Ɋ؍�����Q�c�̂̋������@�c���K��
�@�{�Z�ւ́A�{���w�y�ъw���𗬂Ȃǂɂ��Ĉӌ��������邽�ߖK�ꂽ���̂ł��B
�@�܂��A�����̌ߌ�ɂ͊؍�����Ȋw�Z�p���̎x���ɂ���i���̋���E�Y�Ƃ����@����C�O���C�̃v���O������
��Ƃ��āA�\�E����w�Z�̋����̈����Ŋ؍����̕��ʍ��Z�E�H�ƌn�E���ƌn�E�_�ƌn���Z�̋����S�S�����{�Z��K
�₵�܂����B�{�Z�ւ́A�T�N��ы���Ŏ��H�I�Z�p�҂̈琬���s���Ă��鍑���H�ƍ������w�Z�̋��猻������@
���邽�ߖK�ꂽ���̂ł��B
�@�ߑO�A�ߌ㋤�ɏ�c�F�Z���̈��A�ɑ����A�n�z�����厖�A�Óc���厖����J���L��������A�E�Ȃǂ̐���
���s������A���Ƃ�@�B�v�f�v�������A�@�B�H��H�ꓙ��ŐV�̋��猤�����s���{�݂����w���܂����B�؍��ɂ�
�Ȃ����ꐧ�x�ւ̊S�������A�J���L�������ȂǂɔM�S�Ȏ��₪���܂����B �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
�����Q�Q�N�x�u��w������v�v���O���������t�H�[�����v�|�X�^�[�W����ɏo�W
���Q�S���ƂQ�T���̂Q���Ԃɂ킽��A�L�o�E�X�N�G�A�����Ӊ��ɂ����ĊJ�Â���܂����B
�@�{�Z�ł́A�����Q�O�N�x�ɑI�肳�ꂽ���̍�����w���琄�i�v���O�����i����f�o�j�u�b�h�l�r�����p�����@�B�v�f����
�ƎY�w�A�g�v�Ƃ��ă|�X�^�[��W�����A��g�₻�̐��ʂɂ��ĉ�����s���܂����B �@
�{�Z�̎�g�ɂ��ĉ�����s�������^���y�����i�@�B�H�w�ȁj �@ ����22�i2010�j�N�x
��S��b�h�l�r�t�H�[�������J��
�ƎY�w�A�g�v�̈�Ƃ��āA��S��b�h�l�r�t�H�[�������P�Q���W���ɊJ�Â��܂����B
�@����́A�u���Ɛ�����̃��b�Z�[�W�`����͐��E�ց`�Z�p�҂�����t�B�[���h�v�Ƒ肵�A�_�C�L���H�Ɓi���j����s
�u���A�O�H�d�H�R���v���b�T�i���j�i�������A�����Ȋw�Z�p��w��w�@��Sujatanond Supamard���A��B��w��w
�@���ؑ�����Y���̂S���̍u�t���A�C�O�Ŋ������邽�߂ɉ����K�v�Ƃ���Ă��邩�A�w���ł���Ԃɉ������ׂ���
�Ȃǂ̍u�����s���A�Q�������w������͊C�O�ł̃R�~���j�P�[�V������l�����̈Ⴂ�ɂ��Ă̎��₪����
�����B �@
��S��b�h�l�r�t�H�[�����̗l�q �@ ����22�i2010�j�N�x
�{�Z�Z��ɂ����ʍu������J��
�ɂ����ʍu����u�v�t���ɔ��ǂ��鐸�_��Q�v���J�Â��܂����B
�@���̓��ʍu����́A�P�U����Q�Q�܂ł̊w�����w�ԋ���@�ւƂ��āA���E�����w���̐��_��Q�Ɋւ��鋤�ʗ�
����[�߁A���_��Q�ǂ���w���ɑΉ��ł���悤�ɂȂ邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ŁA�Q���������E���́A������܂�
���l�X�Ȏ����̗v����Ǐ�̐f�f��A���Ö@�Ȃǂ̐����ɔM�S�ɕ��������Ă��܂����B �@
������t�ɂ��u���̗l�q �@ ����22�i2010�j�N�x
�v���Ďs���T��w���A�g�ɂ��s�����J�u�����J�u
�C�g�E�L�����p�X�ɂ����āA�u�R���\�[�V�A���v���Ă��甭�M����v�Ƒ肵���A�s�����J�u�����J�Â���Ă���A�P�P���Q�S
���i���j�ɖ{�Z�̓c����y�����i�@�B�H�w�ȁj�ɂ��u���u���W����V�����̗����� �`���ꂢ�Ȑ������߂Ȃ��l�X�`�v
���s���܂����B
�@�u���ł́A���E�̐�����⏫���̐����A�C����W����������_���ɂ��Đ���������A�Q���҂͐������̉�
�l�ɂ��čĔF�����Ă��܂����B �@
�c���y�����ɂ��u�`�̗l�q �@ ����22�i2010�j�N�x
�u��P�T��}�i�r�B�����h�v�Ɂu�ӂꂠ�����H�w�W�v���o�W
�Ă���u�}�i�r�B�����h�E���ǂ��t�F�X�e�B�o���v�Ɂu�ӂꂠ�����H�w�W�v���o�W���܂����B
�@�����w���y�ш�ʎs���́u���H�w�v�ւ̊S��[�߁A���̖ʔ����A�s�v�c�����̌��ł���悤�A�̌��E�����R�[�i�[
��݂��A���{�b�g�̋��Z�E���J�������s���܂����B
�@���̍Â��́u�v���Đ��U�w�K�t�F�X�e�B�o���Q�O�P�O�v�̃��C�����ƂƂ��āA��ʎs����ΏۂƂ��ĊJ�Â��A�s���̐��U
�w�K�ւ̈ӗ~�ƊS�����߂�Ƌ��ɁA�s�����݂̐�������𗬂�[�߂�ǂ��@��ƂȂ��Ă��܂��B���N�́A����
�w���𒆐S�ɖ�P�C�Q�O�O�����闈��҂�����܂����B �@
�̌��E�����R�[�i�[���y���ޗ���҂̗l�q �@ ����22�i2010�j�N�x
�w�Z������E���w����J��
�����B
�@������ł͏�c�Z������T�v�������s��ꂽ��A�e�w�Ȃ̏Љ�╽���Q�R�N�x�̓��w�����ɂ��Đ���������A
�������^�������钆�w���ɑ��āA���Z���悭�������Ă��炨���Ɗw�ȋ����ɂ��ʖʒk���s���܂����B
�@���������s��ꂽ���w��ł́A�e�w�Ȃ̎����ݔ���W�����������J����A�܂��̈�قł͍��ꃍ�{�R���ɏo�ꂵ
�����{�b�g�̃f�����s����ȂǁA�Q���������w���͋�����ݍZ���̐����ɖڂ��P�����Ȃ���M�S�ɕ��������Ă���
�����B �@
���w���Ƃ��̕ی�҂ɑ��ĊT�v�������s����c�Z��
�w�Ȃ̌��w��̗l�q �@ ����22�i2010�j�N�x
���{�S���H�Ɖ����ƈψ�������̕�����J��
�P�P���T���ɓ��Z�ɂ����ĊJ�Â��܂����B
����ɂ́A�S���e�n����W�܂����S������������ƂP�O�ЁA�P�V���̌o�c�҂��Q�����A���Z�̏�c�Z���̈��A�̌�A
�������p���w�Ȃ̐X��������A�u�S���̉��������̐i�s��Ԃ�d�C�I�ɑ��肷����@�v�A�d�C�d�q�H�w�Ȃ̕��싳
������u�e���w���c���ԗ̈敪���@�̃S���̕��́E�]���ւ̉��p�v�ƂQ�̌�������ɂ��ču�`���s���܂����B
�@�܂��A�������E�����ݔ��̌��w�E�������s���A�Q�������o�c�҂̕��X�́A�^���Ɏ����X���A������J��Ԃ��Ă���
�����B �@
����ɂ����Ĉ��A�������c�Z��
�@ ����22�i2010�j�N�x
�w�����ɂ����ăw���X�`�F�b�N�����{
�@���̊��́A�����̐H�������`�F�b�N����ƂƂ��ɁA���X�̓��̓I�E���_�I�ȃX�g���X�ɑ��āA�K���������H����ۂ�
���Ƃ̑�����[�ւ��邽�߂ɁA�w�����H�Ɩ����ϑ����Ă���i���j�������{�Ћ�B�x�Ђƃ^�C�A�b�v���čs��ꂽ����
�ŁA�w���X�`�F�b�N�ɂ͒��H���I���������̊O�ɁA�����厖�E�厖����Q�����܂����B�{�f�B�`�F�b�J�[�ɂ́A���̓I�E��
�_�I�X�g���X�x������E�������_�o�̋@�\��ԓ��̂ق��A���ǔN��Ȃǂ��\������A�`�F�b�N���I���������̒��ɂ́A
����J����҂�����A�����͐_���Ȗʎ����Ő��̉h�{�m����̐����E�w�����Ă��܂����B �@
�w���X�`�F�b�N���闾���̗l�q �@ ����22�i2010�j�N�x
���������Y���i���j�����Ɓj���{�Z��K��
�Z��K��܂����B
�@�������́A�Z�����ŏ�c�Z���A�]�苳���A���莖�������ƍ��k���A�����ɒ�������ʼnɈ���ꓬ�����Ƃ��̂�
�ƂŌ���Ȃǂ̍ݍZ���̉��������G�s�\�[�h���Љ�ꂽ�ق��A����̎�҂ɂ��Ĉӌ��������s���܂����B
�@���̌�A�n�a�ł��郉�O�r�[���̗��K�����w���A���������サ�܂����B �@
�����́A�����A����߂肠�Z�c��U�K�̍�������R���\�[�V�A���v���Ăɂ����ĊJ�Â��ꂽ�v���Ďs���Z�c��}��
�يJ�ًL�O�u����̍u�t�Ƃ��āA�����̈�ʎs���⋳�E���A�{�Z���O�r�[�������������钆�A�u�]�@�ŏo������{�v
�Ƃ�������ŁA�݊w�����̂��Ƃ��ӂ�Ԃ�Ȃ���u�����s���A�u���̍Ō�ł́A�����̍쎌�ɂ��{�Z���O�r�[������
�́u�}��̓m�v���������O�r�[�����ɂ���I����܂����B �@
�{�Z��K�ꂽ��Ƃ̈��������Y���i������Q�Ԗځj �@ ����22�i2010�j�N�x
����22�N�x�@�v���Ďs���P�ʌ݊�����Z�ɂ��u�����u�`�v���J�u
�����u�`���s���u�����u�`�v���A���N�̃e�[�}���u�v���Ă̐����Ɗ��v�Ƃ��ĊJ�Â��܂����B
�@���Z�ł͂P�O���ɓ��c�����i�@�B�H�w�ȁj�ɂ��u�s�s�ƃ��r���e�B�E�v���Ďs�̌�����ʂ��l����v�ƒ��������i����
���p���w�ȁj�ɂ��u���̒��̒n�ߗނƂ��̍H�ƓI���p�v�̂Q�̍u�`���s���܂����B
�@�Q���w���̒��ɂ͑���w�̕��n���Ìn�̊w��������A���i�Ƃ͎�̈Ⴄ�u�`�ɒ��������Ă��܂����B �@
�u�`�̗l�q �@ ����22�i2010�j�N�x
�A�C�f�A�Ό��E�S���������w�Z���{�b�g�R���e�X�g2010��B����n������J��
���̈�قɂĊJ�Â���܂����B
�@��B����n��ł́A�X����Q�O�`�[�����Q�����A�l�X�ȃA�C�f�A��Z�p����g���č��ꂽ���{�b�g�B�����M�����킢
���J��L���A����傢�ɐ���グ�Ă��܂����B
�@�D�������������H�ƍ������w�Z�a�`�[���w�q�������@�q�������i���[�Y���[�h�j�x�Ə��D���̑啪�H�ƍ������w�Z�a�`�[
���w���_�`�ς�����f�n�i�I�~�R�V�p�b�`���S�E�j�x�A�Z�p�܂Ɠ��ʏ܂���܂����F�{�������w�Z�i����L�����p�X�j�`�`
�[���w�X�`�[�������i�[�x�y�іk��B�H�ƍ������w�Z�a�`�[���wTech-Cha!!�i�e�N�b�`���j�x���P�P���Q�P���ɓ�������
�̍��Z�قŊJ�Â����S�����ɏo�ꂷ�邱�ƂƂȂ�܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@���Z���[�����ɂ��āF���ꃍ�{�R���z�[���y�[�W
�@�@�@�@�����\����F�P�P���P�R���i�y�j�ߌ�R���T���`�T�X���i�m�g�j�����e���r�E��B����n���j �@
�J��̗l�q
�v���č���`�`�[���i�����j�Ƃa�`�[���i���j�E�D����������������a�`�[���i�E�j �@ ����22�i2010�j�N�x
��B�E����n�捑������@�V�Z�p�}�b�`���O�t�F�A�ɎQ��
�Â���܂����B
�@���̃C�x���g�͋�B�E����n��X���ꂪ�ۗL��������i�����J�����܂ށj�⌤���V�[�Y���A�����ҁi�Z�p�ۗL�ҁj���g
����ƊW�҂�ΏۂɁA���p����W�]�����Z�p�������s���A�L�����{��ƁE�����p�[�g�i�[���W���邱�Ƃ�ړI�Ƃ�
�����̂ł��B
�@�v���č��ꂩ��́A�w���̗͂ŏ������A�C���≘���������������鑕�u�x�Ƃ����e�[�}�Œ����y�����i�@�B�H�w�ȁj
���u�����s���A�K�ꂽ��ƊW�҂�w���͋����[�����ɘb���Ă��܂����B �@
�u�����s�������y���� �@ ����22�i2010�j�N�x
�e�}�Z�N�E�|���e�N�j�N�̊w�����{�Z��K��
�P�Z�ł���e�}�Z�N�E�|���e�N�j�N�Z�̊w���S�T���Ƌ����Q�����A�k����B�ւ̏C�w���s���A�w�Z�Ԍ𗬂̈�Ƃ��ĂP�O
���W���ɖ{�Z��K�₵�܂����B
�@��c�Z���̊w�Z�Љ�̌�A�e�}�Z�N�E�|���e�N�j�N�Z�̊w���͊w���̎{�݂���Ƃ����w���A�w���𗬉�Ƃ��Ė{�Z��
�w���Ɖp��̎��ƂɎQ�����܂����B
�@����ꂽ�؍ݎ��Ԃł��������A�w���B�͂����ɑł����������A���H��ɂ͂��݂��̃��[���A�h���X������������A��
�^�B�e��������ȂǁA�L�Ӌ`�Ȏ��Ԃ��߂����ƂƂ��ɁA�قȂ镶�������w���Ƃ̌𗬂�ʂ��A�݂��̕����≿�l�ς�
�̋�����S�����߂Ă����悤�ł����B �@
�{�Z�̏Љ���s����c�Z��
�𗬉�̗l�q �@ ����22�i2010�j�N�x
����߂肠�Z�c��u�T�e���C�g�E�L�����p�X�v�O�����h�I�[�v���L�O�C�x���g�Ƃ��Ēm�I���Y�Z�~�i�[���J��
�̍�������@�ցi�v���đ�E�v���čH�Ƒ�E���}���A�w�@��E�v���ĐM�����w�@�Z��E�v���č���j�ɂ��\����
���u��������R���\�[�V�A���v���āv�̋��_�ƂȂ�T�e���C�g�E�L�����p�X�ł́A�����A�O�����h�I�[�v���L�O�C�x���g
�̂P�Ƃ��āATOTO������Вm�I���Y���̎R��G���u�t�Ƃ��Ă��������A��������R���\�[�V�A���v����SD
���C��u�m�I���Y�Z�~�i�[�v�i��ÁF�o�ώY�Əȁ@��B�o�ώY�ƋǁE��B�m�I���Y���c��j���J�Â���܂����B
�@���Z�~�i�[�ł́A�m�I���Y���x�̊T�v��������x�̈Ӌ`�A��Ƃ��猩����w���ɂ�����m�I���Y�헪�̖����E
�d�v����A��ƂƋ�������������ۂ̗��ӓ_�Ȃǂ̐�����������₷����̗�������Ȃ���s���A�Q���҂͔M
�S�Ɏ����X���Ă��܂����B �@
�Z�~�i�[���s���R��G�� �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
�@�B�H�w�ȑ�P�����Ɛ����{�Z��K�� �@���Ɛ��́A��c�Z��
�ƍ��k�̌�A���i�@�B�H�w�Ȓ��̈ē��̂��Ɗw�������w���܂����B
�ȂǁA���w���A�̘b�ɉԂ��炩���Ȃ���A�I�n�a�₩�ȕ��͋C�ʼn�b���e��ł��܂����B �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
�����n��R���ꎖ���E���i�W�����j���C����J��
���B
�@�{���C�́A�����E���i�W�����j��ΏۂɁA�E���̐��s�ɕK�v�ȐE�Ɛl�I������t�^���A�����̌����}�邱�Ƃ��
�I�Ƃ��A�L������A�k��B���ꂨ��ыv���č���̌W���P�S�����Q�����܂����B
�@���C�ł́A�v���č���Y�ƈ�̖k�������ɂ��u�X�g���X�Ƃ�����E���炾�v�A�{�Z�̏������������ɂ��u�E��
�l�Ƃ��Ă̊�{�p���v�̂Q�̍u������сu�w���̎��A�̎d���v���e�[�}�Ƃ����Q���҂ɂ��O���[�v���c��
�s���A���C��I����A�Q���҂���g�E���̗p��̑����i�K�ɂ��̌��C�����������B�h�g���̌��C���e��
���N�x�ȍ~�̗p�����l�̂��߂ɑ����Ă����Ăق����B�h�Ȃǂ̊��z���q�ׂ��܂����B �@ �@ �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
�����Q�Q�N�x�v���čL�揤�k��ɎY�w�A�g�R�[�i�[�Ƃ��ĎQ��
�u�v���čL�揤�k��v���J�Â���܂����B
���͉��ׂP�P�O�ЁA�������͋@�B���������Ƃ̂Q�U�Ђ̒n���Ƃ��Q�����A�M�S�ɏ��k���s���Ă��܂����B
�@�Y�w�A�g�R�[�i�[�ɂ́A�v���đ�w�E�v���čH�Ƒ�w�E�����w�E�����w�E�{�Z�����ꂼ��u�[�X��ݒu���A�{�Z
�ɂ����ẮA�u�[�X�ɖK�ꂽ�n�ꒆ����Ƃɑ��ăV�[�Y�̐�����Z�p���k�̈ē����s���܂����B �@ �@ �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
����̌����w���J��
���Ē��w����ΏۂɈ���̌����w���J�Â��A����ԂłT�W�T���̎Q�����������B���x�݂ɂ͍݊w���ɂ��w�Z�s����
��܂����B
�@�Q���������w������͍���̎��Ƃ��悭�m�邱�Ƃ��o�����A�w�Ȃ̈Ⴂ���킩�����A�������y���������Ȃǂ̊��z
��������܂����B
�Ȃ��A���ڂ����{�Z�̐����ɂ��Ă͂P�P���P�R���A���Z�ɂĊw�Z������E���w��J�Â����\��ƂȂ��Ă��܂��B �@
�̌����ƂŎ������s�����w�� �@ �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
��������R���\�[�V�A���v���Ď�Á@���w�Z���������̕��ː��u�����J��
���w�Z���������̕��ː��u�����W���X���ɊJ�Â��܂����B
�@���ɂ��u�`��v���č���̉z�n�y�����ɂ����K���s���܂����B
�@�u�`�ł́A��������������ː��ɂ��Ă̊�b�m����A���ː��������ɂǂ̂悤�Ɋւ���Ă��邩�A���ː��̉e��
�ɂ��ĂȂǂ̘b����������A�y����������w�I�ȕ��ː��̊��p�ɂ��ċ�̓I�Ȏ���������Ȃ���������s���܂�
���B
�@���K�ł́A���ː��v�����u�u�͂��邭��v��p���āA�g�߂ɕ��ː������邱�Ƃ�A���ː��̋����Ƌ����̊W�A����
���̓��ߐ��ɂ��Ē��ׂ���A���葚�����g���ĕ��ː��̔�Ղ��ώ@���܂����B
�@�Q���҂͍u�`�̍��Ԃɂ������ӌ��������s���ȂǁA�Ō�̎��K���I���܂ŐϋɓI�Ɋw��ł��܂����B �@
�v�����u��p���Ď��K���s�����w�Z�̋����Ǝw�����s���z�n�y���� �@ �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
��������R���\�[�V�A���v���āu�T�e���C�g�E�L�����p�X�v�ɂăI�[�v�j���O�C�x���g���J��
���ċv���čH�Ƒ�w�̈��G�M�y�����ɂ��u���u���炭��V�E�q��@�G���W�j�A�E�c���v�d�i���őn�Ǝҁj�v�Ɩ{�Z
�@�u���ł͓c���v�d�̌o����A��Ȕ����̏Љ�Ȃǂ��s���A�����ł͖{�Z���쐻�����c���v�d�̏��C�@�֎Ԃ�
���v���J����������܂����B
�C�x���g�ɂ́A�Q���ԂŖ�P�T�O���̗���҂�����A�u�����l��@�֎Ԃ����Ċ�Ԏq���B�̎p�Ȃǂő傢�ɓ����
�Ă��܂����B �@
�I�[�v�j���O�C�x���g�ɂ�������C�@�֎ԉ^�]�̗l�q �@ �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
��������R���\�[�V�A���v���āu�T�e���C�g�E�L�����p�X�v�J���������s
�Z��j�ɂ��\�������u��������R���\�[�V�A���v���āv�̋��_�ƂȂ�T�e���C�g�E�L�����p�X������W���U���A�s����
�@���ɂ́A�R���\�[�V�A�������ł���{�Z�̏�c�Z���͂��߁A��藘���v���Ďs����A�g���Ă����w�̊W�҂�
���o�Ȃ��A�R���\�[�V�A���̗������ł���v���đ�w�̖�t�������w���́u�������S���l�ވ琬�̂��ߒm�̌�
���_�Ƃ��A�n��̊������ɂȂ������v�Ȃǂƈ��A���A�R���\�[�V�A���̗����ł��铯�s���́u��҂̊��͂��܂��Â���
�ɐ����������v�ȂǂƏq�ׁA�e��������@�ւ̑�\�҂Ɠ��s���ɂ��e�[�v�J�b�g���s���A�J�����j���܂����B �@
�e�[�v�J�b�g���s����c�Z���i�ʐ^�E�[�j�Ɗe�@�ւ̑�\�� �@ �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
��B��w�������j�l�ވ琬�v���O�����u���Ԑ����R�[�X�v���ԉ��H���K���J��
�ԉ��H���K���W���R������W���U���̂S���Ԃɂ킽��S�����čs���܂����B���R�[�X�́A���Ԑ����ɂ������ՋZ�p��
���Q�����A�W���R������W���S���̂Q���Ԃł́A���ԉ��H�P�Ƃ��āA�n�C�X�z�u��T�E���d�z�u��T�E���ԑ���E���`
��͂��s���A�W���T������W���U���̂Q���Ԃł́A���ԉ��H�Q�Ƃ��āA�n�C�X�z�u��U�E���ʎd�グ�U�E���d�z�u��
���̉��H���K���s���܂����B�Q���҂͂Q�ǂɕ�����Ď��K���s���A�M�S�ɍu�t�̐������ƍH��������������ȂǁA
���Ȍ��s�ɗ��ł��܂����B �@
�u�t�̐����ɔM�S�Ɏ����X����Љ�l�Z�p�� �@ �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
���w�������̌��J�u���u�G���N�g���j�N�X�T�}�[�X�N�[���v���J��
�@���u���ɂ́A�v���Ďs���y�ыߍx�̒��w���Q�W�����Q�����A�P���ڂɂ̓��C���g���[�X�J�[��g�ݗ��Ă���A�X�^�b�t
�쐻�̃R�[�X�ɂă^�C���g���C�A�����s���A�Q���ڂɂ̓u���b�h�{�[�h���g�����d�q�I���S�[����g�ݗ��āA�d�q�I���S
�[���̎d�g�݂ɂ��Ċw��A�d�C�Ǝ��C���g�����l�X�Ȏ��������w���܂����B
�@�Q���������w�������́A�d�q�H��ׂ̍��Ȓ����Ɠ���e�X�g�̌J��Ԃ��ɋ�킵���A�u�t��w��TA�ɃT�|�[�g
����Ȃ���M�S�Ɏ��g�݁A�d�C�d�q�Z�p�̖ʔ������w��ł��܂����B �@
���C���g���[�X�J�[�̑g�ݗ��Ă�M�S�ɋ���钆�w�� �@ �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
���w�������̌��J�u���u���Ȃ�������T�C�G���e�B�X�g�v���J��
���B
�@���u���ɂ́A�v���Ďs���y�ыߍx�̒��w�P�A�Q�N���Q�O�����Q�����A�����R�[�X�u�G�R���W�[���W�I�i�d�r�̂���Ȃ�
�@�Q���������w���B�́A�����R�[�X�ł͕��i�͂��܂�g�����Ƃ̂Ȃ��H�����Ɉ���ꓬ���Ȃ�����A�d�r���g�p����
���G�R���W�[���W�I�̐����̌����A���w�R�[�X�ł͗��j��H��Ȃ���̐��w��A�����̑����Z�̈������A�S�y���g
���ăt�@�W�[���_�ɂ��Ċw�ԂȂǁA�Q���Ԃ�ʂ��ė��ȁE���w�ւ̋����E�S�����߂�ƂƂ��ɁA���{�R���̐��쎺��
���K�H������w���A�{�Z�ł̑̌����y����ł��܂����B �@
�M�S�Ƀ��W�I�̐���Ɏ��g�ޒ��w�� �@ �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
�w���E�Љ�l�����̂R�c�|�b�`�c���J�u�����J��
�@�w���E�Љ�l�̂R�c�|�b�`�c���S�҂����ƂŊ��p���Ă�������o���҂܂ŕ��L����u�҂���\�����݂�����A�P�V��
�@�u�`�ł́A�R�c�|�b�`�c�̑�\�I�ȃf�W�^���E�G���W�j�A�����O�\�t�g�ł��颃\���b�h�E���[�N�X��̑���ƁA���̊��p���@
�𗝉����邱�Ƃ�����ɓ���A�R�c���f���̍쐬����A���`�F�b�N�A����V�~�����[�V�������A��A�̊�{����ƁA�R�c
���f������̐��@�\����Q�c�}�ʂ̍쐬�A�b�`�d�\����͓��A�����ʓI�ɂR�c�|�b�`�c���g�����Ȃ����߂̉��p�����
�K�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A��u�҂͊w���s�`�̕⏕���Ȃ���A�M�S�ɉۑ�Ɏ��g��ł��܂����B �@
�w���s�`����⏕���Ȃ��瑀����s����u�� �@ �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
��T��C���e�O�����Z�~�i�[���J��
�ƎY�w�A�g�v�̈�Ƃ��āA��T��C���e�O�����Z�~�i�[���V���Q�Q���ɊJ�Â��܂����B
����́u�R�c�|�b�`�c�^�b�`�d�̍ŐV����v�Ƃ����e�[�}�Ŗ{�Z�@�B�H�w�ȏ��䋳���ɂ��u�@�B���}�ƂR�c�|�b�`�c�v�̍u
���Ɏn�܂�A�R�c�|�b�`�c�̋���ւ̓����Ƃ��̊��p�̂��߂̋���ɂ��āA�x���_�[��Ƃɂ��o�k�l�\�����[�V������
���p�ɂ��āA��ƂłR�c�|�b�`�c���������E�v�̃v���Z�X�ɂǂ����p����Ă��邩�ȂǕ����ĂS�̍u�����s����
�����B
�@�Q���҂͔M�S�ɍu�����A�u����ɂ͔��\�҂⑼�̎Q���҂Ɗ����Ɉӌ��������s���Ă��܂����B �@
���A���s�����i�w�Ȓ� �@ �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
�A�E�����Z�~�i�[�J��
�@���̃Z�~�i�[�͕�������Ҏd���T�|�[�g�Z���^�[�̋��͂ɂ��J���ꂽ���̂ŁA�����厖�A�A�E�S�����������̘b
�̂��ƁA�u�t�ɑ命���l�����}���A�d���ɑ���ӎ��A�A�E�����ւ̐S�\���Ɋւ���u�����s���܂����B
�@���悻�P���Ԕ��̃Z�~�i�[�ł��������A���͂����ɖ����ƂȂ�A�I�����ɂ͑傫�Ȕ��肪�N����܂����B
�@�Z�~�i�[�������k����́A�u�A�E�ɑ���ӎ������܂����B�v�u���ꂩ��A�E�������s����Ŗ��ɗ��������B�v�Ȃ�
�����̐������܂����B �@
�A�E�����Z�~�i�[�̗l�q �@ �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
����G���Z�p���E���������J�͂̎�͂��
�@���N�ɓn���ĎЉ�ɍv��������A�D�ꂽ�Ɛт����߂��l�����ɑ�����u�t�̖J�́v�ŁA�{�Z�̍���Z�p���E����
�����J�͂���͂����h�_�ɋP���A����T���Q�Q���A��c�Z���ɑ��ĕɖK��܂����B
����ō��ۂɂ́A�w��̊��o�łP�O�O�O���̂P�~���P�ʂ̔��������s�����Ƃ��ł���m���Șr�������Ă���A�����Q�O�N
�P�P���ɂ́u����̖��H�v�ɂ��I��Ă��܂��B
�p���w������Ă����B�v�ƈӗ~�I�Ɍ���Ă��܂����B �@
��c�Z���ɑ����s������Z�p���E�� �@ �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
�V�K�H�i�u���уp���v�𐼓��{�H�i�Y�Ƒn���W�f�P�O�ɏo�W
�i�J��������R�[�i�[�ɂ����āA�������p���w�Ȃ̋��؏y��������ƂƋ����ŊJ�����s�����A�V�K�H�i�u���уp���v
���o�W���܂����B
�@�����{�H�i�Y�Ƒn���W�f�P�O�͒n�Y�n�����L�[���[�h�ɁA���������������V���ȐH�����̍\�z��ڎw�����̂ŁA���
�ɂ͑����̊�Ƃ��o�W���A�R���ԂŖ�P�W�C�O�O�O�l���K��܂����B
���A���������������킹���V�����g�ѐH�ł���A�W���u�[�X��K�ꂽ�l�X�͂��уp���̎��H�����Ȃ���A���̐V����
�H���ɋ����Ȃ���������������A�b���Ă��܂����B �@
�����{�H�i�Y�Ƒn���W�ɏo�W�������؏y���� �@ �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
���_�������^�������s �@
�@�{�Z�ł́A����T���Q�P���ɍZ�����ɂ����Ė��_�������^�������s���܂����B
�@���^���ł́A�R���R�P���t���Ŗ{�Z��ސE���ꂽ�O�c�O�j�@�O�v���č���Z���ɑ��Ė��_�����̏̍������^����A
��c�Z������؏�����n����܂����B
�@���^���̌�ɂ́A��c�Z�����獡�܂ł̂����J�ɑ��Ă̎ӈӂ��q�ׂ���ȂǁA�I�n�a�₩�ȕ��͋C�̒��ʼn�b
���e��ł��܂����B
�@�y�O�c�搶�A�{�Z�̂��߂ɂ��s�͂�������A���肪�Ƃ��������܂����B�����ԁA����ꂳ�܂ł����B�z ���_�������^���̗l�q �@ �@ �@ ����22�i2010�j�N�x
�n�k�ƉЂ�z�肵���h�Д��P�������{
���s���܂����B���̌P���͊w���⋳�E���̖h�Јӎ������߂邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ŁA�w���Ƌ��E�����킹�Ė�P�C�Q�O�O
�����Q�����܂����B
�@�P���ł͏�c�Z������{�����Ƃ����E���ɂ�鎩�q���h�c����������A���E�����A�g��}��A���Ί�̑���A�P�P
�X�Ԃւ̒ʕ�A�w���̔��U���A���������w���̉�����ꂼ�ꂪ�������ʂ����Ȃ���^���ɍs���܂����B
�@���I����́A���h�����ɂ����Ί�̎g�p���@��h�Ђ̍ۂ̐S�\���y�ъ�b�m���ɂ��Ă̐����̌�A�����
�h�Д��P���S�ʂ̍u�]���s���A�Q���҂́A���̌P���Ŕ��ɂ������Ă̒��ӎ������m�F�������A�h�Јӎ�������
�Ă��܂����B �h�Д��P���̗l�q �@ �@
�@ ����22�i2010�j�N�x �V���w���Ƃ̍��k����J��
�@���̃C�x���g�́A���N�x�V���ɕғ��w�����V���w���T���ɑ��A�����ł������w�Z�Ɋ���Ă��炦��悤�s��ꂽ����
�ŁA�݊w���闯�w���S���Ɗw���`���[�^�[�A���E���Ȃǖ�S�O�����Q�����܂����B
�@���k��ł́A�Q���ґS�������ȏЉ���s���A�V���w���́u�������{�����肭�b����悤�ɂȂ肽���v�Ƌْ����Ȃ���
�����J�ɕ������q�ׂ܂����B
�@�܂��A��y�̗��w�����u���w�����m�����łȂ��A���{�̊w���Ƃ̌q������ɂ��Ăق����v�ȂǗ����ȓ��{��ŃA�h
�o�C�X�𑗂�p�ɁA���E���ꓯ�͊��Q���A���k��͏I�n�a�₩�ȕ��͋C�̒��A����̂����ɖ�����܂����B �@ �@�V���w�����}���Ă̍��k��̗l�q �@
�@ ����22�i2010�j�N�x
������{�������N���R�̉Ƃɂ�1�N�����h���C���J��
�̉ƂɂĊJ�Â��܂����B
�@���̍��h���C�́A�{�Z�̊w���Ƃ��Ă̐S���܂����w�сA���w�����Ӌ`���l���邱�Ƃ�A���C���̋K���������������
���āA�w�F�E�����Ƃ̐e����[�߂邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ŁA�P�N���̂ق��A�w���������w�ȑ�\�ȂǏ㋉�����܂߁A
��Q�T�O�����Q�����܂����B
�w����Ƃ̌𗬍s���Ȃǂ��s���A�Q�������P�N���͂��ꂩ�狟�ɂT�N�Ԃ��߂������ԂƋ��͂������Ȃ��猤�C�̃v��
�O�����Ɏ��g�݁A�݂��ɐe�r��[�߂Ă��܂����B
�@
�@��{�������N���R�̉Ƃɂ����錤�C�̗l�q �@
�@ ����22�i2010�j�N�x
�������J�����E�Ƌ���𗬖K��c���v���č�������@
�@�S���P�S���A�v���Ďs�ƗF�D�s�s�W�ɂ��钆�����J�ȍ���s����A���J�ȋ��璡�̗��@�a���@��������c���Ƃ���
���J�����E�Ƌ���𗬖K��c�P�Q�����{�Z��K��܂����B
�@����̖K��c�́A�T�N��ы���Ŏ��H�I�Z�p�҂̈琬���s���Ă�����{�̍H�ƍ������w�Z�̋��猻������@����
�ƂƂ��ɁA���J��w�Ɩ{�Z�Ƃ̑��𗬂W�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ĖK�ꂽ���̂ŁA��c�Z�����͂��߁A�n�z�����厖�A
�Óc���厖���̋��E�����o�Ȃ��A�����Ԍ𗬂�w�p�A�g�𗬓��ɂ��Ċ����Ȉӌ��������s���A������獡��
�ϋɓI�Ȍ𗬂���]����|�̔���������܂����B
�@�܂��A�w���̋@�B�v�f�v�������A�@�B�H��H�ꓙ�̊�b�Z�p��ŐV�̋��猤�����s���A�w���{�݂̌��w���s���A
���@�͏I�n�a�₩�ȕ��͋C�̂Ȃ��ōs���܂����B
�@
�@���J�����E�Ƌ���𗬖K��c�̖{�Z���@�̗l�q �@
�@ ����21�i2009�j�N�x
�Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[�v�H�L�O���T�����s
��̃e�N�m�Z���^�[���Ȃǖ�P�Q�O���̏o�Ȃ̂��Ƌ��s�����B
�Ȃǂ��s���A�܂��A�����P�X�N�x�ɍ̑����ꂽ����f�o�̐��ʕɂ��Ă������čs��ꂽ�B
�����Ɋ��҂��鐺���������A���T�͐���̂����ɖ�������B
�@ �@ ����21�i2009�j�N�x
�Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[�v�H�L�O�g�[�N�R���T�[�g���J�� �@ �@�{�Z�ł́A����Q���Q�U���ɑҖ]�̎Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[���v�H��
���B������L�O���A�u���m�̓`�����y�Ƃ��̕���
�I
�w�i�v�Ƒ肵���A�t���[�g�ƃ����[�g�ɂ��g�[�N�R���T�[�g���R���P�O���i���j�ɊJ�Â����B
��ʎs���⋳�E����W�O�����v�H���j�����B
�ŗL������T�N�݊w�̍������I����A����ɉ����t���[�g�t�҂ŎR���Êy�R���N�[���D���A�x���M�[�E�u���[�W�����ی�
�y�R���N�[���Q�ʂȂǂ̎��т������A�O�c�Z���̂������ł�����O�c���q�����}���s��ꂽ�B
�F�Ɖ��t�҂̐����ɐV�N�ȋC�����ŕ��������Ă����B �@ �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x
�v���ăe�N�m�u���b�W�ɂ����Č����V�[�Y�\
���A�r�W�l�X�W�J�����邽�߂̓����r�W�l�X�s�ł���u�v���ăe�N�m�u���b�W�v�ɂ����āA�{�Z�̌����V�[�Y���\���s�����B
�Ɋւ��錤���v�ƁA���Ȃ̏��c�������u�^���p�N����p�����퉷���ł̃S��������@�̌����v�ɂ��āA���܂ł̐��ʂ�
����̉ۑ��W�J�Ȃǂ����ꂼ�ꔭ�\�����B
��ʂ̕��Ɏ��H���Ă��炢�A���z�Ȃǂ�q�˂Ă����B �@ �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x ����f�o�]���ψ�����J��
���H�I�Z�p�҈琬�v���ŏI�N�x���}����ɂ�����A�{��g�̐��ʂɂ��ĊO���̗L���҂������A�]���ψ�����P���P�T ���ɊJ�Â����B
��g���ƐӔC�҂ł���A�������p���w�Ȃ̈ɓ��������璆�ԕ]���̌��ʂ܂��A�{��g�̖ڕW�ł���u�n���Ƃ�
�A�g���Ď��H�I�H�ƋZ�p�҂��琬�����g�v�̒B������{���ʁA����ɔ������������̐��ڂȂǂɂ��Ă̐���
���s��ꂽ�B �@�o�Ȃ����ψ�����́A�n���Ƃɍ��t�����Z�p�ҋ���݂̍���Ȃǂɂ��č����]�������B �@ ����f�o�]���ψ���̗l�q �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x
�����Q�P�N�x�w�������l�����J��
�V�������l���}���������R�T�����j�������B
������ƌN���ӎ����q�ׁA�u���܂ł����b�ɂȂ����Ƒ��A�搶�A�F�l�A�Ɋ��ӂ̈ӂ�\���ƂƂ��ɁA���ꂩ�琬�l�҂Ƃ���
�̎��o�������Ċ撣�肽���B�v�ƕ���������Ă����B �@
�w�������l���̗l�q�Əj�����q�ׂ�]�藾���厖 �@
�@ ����21�i2009�j�N�x
�w�����k�����ʍu������J��
�_�o���_��w�u���y�����̑O�c�������_�Ȉ���u�t�ɏ����A�u�v�t���Ɣ��B��Q�v�Ƒ肵���u������P���U���ɊJ�Â����B
�@�u���ł́A�����ɃA�X�y���K�[�nj�Q�̓����ɂ��āA�l�Ƃ̃R�~���j�P�[�V���������ł���A�Љ��W�c�̒��Ŗ��
���N�����₷�����ƁA���̔��ʁA���l���ł��Ȃ��悤�ȗD�ꂽ�\�͂������ƂȂǁA����������Ȃ���̘b������A�A�X�y��
�K�[�nj�Q�ɑ�����̗͂����Ƃ��̌���F�߁A�K�Ȕz�����s�����Ƃ���ł���Ƃ̐������������B
�@�u����̎��^�ł́A�Q���������E������A�X�y���K�[�nj�Q�̊w���ɐڂ��邱�ƂɂȂ����ꍇ�̑Ή��Ȃǂɂ��đ���
�̎��₪��ꂽ�B
�u�����s���v���đ�w��w���̑O�c���� �y����
�@
�@
�@ ����21�i2009�j�N�x
��R��b�h�l�r�t�H�[�������J��
�Y�w�A�g�v�̈�Ƃ��āA��R��b�h�l�r�t�H�[�������P�Q���Q�T���ɊJ�Â����B
�@����́A�u���Ɛ�����̃��b�Z�[�W�v �`���H�Z�p�҂Ƃ��ĎY�ƊE�œ������߂Ɂ` �Ƒ肵�A�{�Z�̑��Ɛ��ł���đq����
���_�������͂��߁A��ƂŊ��Ă���Q�O�ォ��S�O��̑��Ɛ��T�l�ɂ��u�����s��ꂽ�B
�@�u���ł́A�đq���_��������u�v���č���@�B�H�w�ȗ��j�ɂ��āv�Ƃ����e�[�}�ŁA�{�Z�̑O�g�ł��菺�a14�N����
�����v���č����H�Ɗw�Z���ォ�猻�݂̋v���č���Ɏ���܂ł̕ϑJ���y���̊�Ƃɂ����銈��ɂ��Č���A
�܂���Ƃ̑����Ŋ��Ă��鑲�Ɛ��ɂ��u���ł́A���ƌ�ɂǂ̂悤�Ȏd�����s���Ă����̂��A�w������ɋZ�p
�҂Ƃ��ĉ���g�ɕt���Ă����K�v�����邩�Ȃǂɂ��āA�̌��k�������Ȃ���̍u�����s���A�Q�������w���B�͔M�S
�Ɏ����X���Ă����B �@�u�����s���đq���_�����ƃt�H�[�����̗l�q �@ �@
�@ ����21�i2009�j�N�x
�u��������R���\�[�V�A���v���āv���蒲��
���x�l�ވ琬��Ձ@�|��}��여�摍����w����Ɍ����ā|�@�𐄐i���Ă������߁A�{�Z���܂ގs���T�̍�������@��
�ɂ��u��������R���\�[�V�A���v���āv�ݗ��̂��߂̋��蒲���A�P�Q���P�V���Ɏs���̃z�e���ɂ����čs��ꂽ�B
����@�ւƂ̊Ԃŋ��菑�ւ̒����s��ꂽ�B
���p�X��݂��A�w�E���E�Y�̌𗬂�A�g����������ƂƂ��ɁA�{�Z�ɂ����Ă��P�ʌ݊��⏬���A�g���ȋ���A�Љ�l����
���J�u���ȂNj��犈���A�l�ވ琬�������s���Ă������ƂƂ��Ă���B
�@
�@�R���\�[�V�A�����̗l�q
�@
�@ �@ ����21�i2009�j�N�x
�u�������[�^�[�V���[�Q�O�O�X�v�������w������ԗ��W�ɂ����ėD�G�G�R�J�[���
���D��̏o�W�����uKurume-eco���v���D�G�G�R�J�[�܂���܂����B �@�R���̓g���^�A�j�b�T���ȂǁA��Ƃ̐��Ƃɂ��s���A�uKurume-eco���v�͓O�ꂵ��
�ԑ̂̌y�ʉ��A��C��R�� �l�������J�E���A�R��������]������A����̎�܂ƂȂ����B
�Ԃ삷��d���Ɍg��肽���ƁA�����̖ڕW������Ă����B �@
�@�������w������ԗ��W�̗l�q�ƁA�D�G�G�R�J�[�܂���܂����G�R�p���[���D��́uKrume-eco���v �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x
��w���@�x���`���[�r�W�l�X�v�����R���e�X�g�ɂ����ăO�����v�����
�@�w���炪����l�����r�W�l�X�v���������������u��X���w���x���`���[�E�r�W�l�X�v�����R���e�X�g�v���A�P�Q���P�P����
�����s�����ŊJ����A�����w�����_��ƂȂǂ�ʂ��Ă��N��肩��m�b��`�����w�Ԏ��Ɓu�v���}�x�[���v�\����
�{�Z��U�ȂP�N�� ��㖃������A�����R���q����̂Q�l���A�Q����w�E����T�O�Z�̒��Ō����O�����v������܂����B
�L�����v�����{���A�āA�݂��A���傤��A�~�����Ȃnj��ޗ��Â��肩��X�^�[�g���A�Ō�ɒ������s���B �@
�@�R���e�X�g�̗l�q�ƁA�����O�����v������܂�����㖃������i�ʐ^�E��y�E���z�j�ƕ����R���q����i���y�����z�j �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x
��T��@�R�c�|�b�`�c�^�b�`�d���J�u�����J�� �Q�����������B
�@�B�͊w�A�M���̂̊�b�u�����͂��߁A�b�`�d�V���~���[�V�����\�t�g�ł��颃\���b�h�E���[�N�X������p�����\���A�M���́A
�U�����̉�͎��K��L���v�f���\�t�g�E�F�A�ɂ��Y���ό`����͎��K���Ɍv���@����g���������������Ȃ������
�ւ̉��p������ɂ��ꂽ���e�ƂȂ��Ă���A��u�҂͍u�t�̐������Ȃ���A�M�S�ɉۑ�Ɏ��g��ł����B �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x
���a�R�X�N�x�J�ݍ����������w�Z�Z���ɂ��w�Z�^�c��������J��
�@���a�R�X�N�x�ɊJ�݂��ꂽ�S���̍����������w�Z�Z���ɂ��w�Z�^�c��������P�P���R�O���A�P�Q���P���̂Q���Ԃ� �n��A�{�Z�����ԍZ�ƂȂ�J�Â����B ���āv ��
�u��U�Ȃ̌���Ƃ��̏[���ɂ��āv�ȂǁA�e�������芪���������c��Ƃ��āA�e�Z�̏��܂��� ���犈���Ȉӌ��������s��ꂽ�B �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x
�j�@���O�r�[���I�@��S�U���B����n�捂�ꃉ�O�r�[�t�b�g�{�[�����D��
�@��S�U���B����n�捂�ꃉ�O�r�[�t�b�g�{�[���������P�P���P�V���A�F�{���������^�������ōs���A�����ɐi
�v���č��ꂪ�Q�Q�|�V�ō����ۍ�����~���A�����D���A�Q�A�e���������B
�@�����͏��J����̊������Ŏ������s���A�O���͂T�|�O�Ƌٔ����鎎���W�J�̒��A�㔼�Q�g���C�A�P�o�f�œ��_���d�ˁA
�����ۍ���̔������V�_�ɗ}����ȂǁA�U��ɓn��`�[����ۂƂȂ����v���[�Ńm�[�T�C�h�̃z�C�b�X�����}�����B
����\(�P�O�N�A���Q�Q���)�Ƃ��ďo�ꂷ��B �@
�@ �@ ����21�i2009�j�N�x
�v���Ďs���T��w���A�g�ɂ��s�����J�u���i�ŏI���j
�@�A�g���Ă���s���T�̑�w���Ƌ��ɁA�P�O���R������J�u���Ă���s���������J�u���u�v���Ă̖������l����v���P�P��
�Q�P���ŏI�����}���A�{�Z��ʕ��Ȃ̒����������n�߁A�A�g�s���T��w���̍u�t���ꓯ�ɉ�āA�u�`���s��ꂽ�B
�@�u�`�ł́A�e��w���̍u�t���A��ÁE�����E����E�s�s���Ƃ������e��啪�삩��A�v���[�`���s���A�v���Ďs������
�ǂ�����ׂ����ɂ��āA��u�҂̔��������������Ȉӌ��������s��ꂽ�B�@
�@�u�`�ɖK�ꂽ��u�҂́A�e�u�t�ɑ��Ď�����s���ȂǁA�ϋɓI�Ɉӌ������ɎQ�������ʂ�����A�u�`��M�S�ɕ��� �����Ă����B �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x
�u��P�S��}�i�r�B�����h�v�Ɂu�ӂꂠ�����H�w�W�v���o�W
�{�Z�ł͂P�P���W���A�v���Ďs�̐��U�w�K�̋��_�Ƃ�������u���[��s�A�v���āv�ŋv���Ďs������Â��A���N�J�Â�
���Ă���u��P�S��}�i�r�B�����h�v�ɁA�u�ӂꂠ�����H�w�W�v���o�W�����B
���N�y�ш�ʎs���́u���H�w�v�ւ̊S��[�߁A���̖ʔ����A�s�v�c����̌����Ă��炦��悤�̌��A�����R�[�i�[
��݂��A���{�b�g�̋��Z�A���J�������s�����B
���̍Â��́u�v���Đ��U�w�K�t�F�X�e�B�o���Q�O�O�X�v�̃��C�����ƂƂ��āA��ʎs����ΏۂƂ��ĊJ�Â��A�s���̐��U�w
�K�ւ̈ӗ~�ƊS�����߂�Ƌ��ɁA�s�����݂̐�������𗬂�[�߂�ǂ��@��ƂȂ��Ă���B �@���N�́A��P�C�R�O�O�����闈��҂��������B �@ �@
�@ ����21�i2009�j�N�x
�v���Ďs���T��w���P�ʌ݊�����Z�ɂ�鋤���u�`���J�u
�@
�{�Z�ł́A�v���Ďs���̂T��w���Ƃ̊ԂŒ��������P�ʌ݊�����Ɋ�Â������̈�Ƃ��āA�����Z�ŋ����u�`���J
�u���Ă���A���N�x�́u�v���Ă̐����Ɗ��v���e�[�}�ɑS�P�T�u�����s���A�{�Z����͂P�O���Q�U���ɐ������p���w��
�̋��؏y��������u��������p������������v�A�܂��P�P���U���ɂ͐�����H�w�Ȃ̐����������́u�w�U���낵
�ƕ��͔��d�v�Ƃ�����ڂōu�`���s��ꂽ�B
�u�`�ł́A���؏y��������A�V�G�l���M�[�Ƃ��Ē��ڂ��W�߂Ă���o�C�I�G�^�m�[����A�Â���������s���Ă���
�������̗L�����p�ɂ��āA�܂������������͖{�Z�ł̌v���f�[�^����ɁA���͔��d�̂����݂��獡��̉ۑ蓙�A��
�L�����e�ɂ��Đ������s��ꂽ�B �@�e��w�������u�ɖK�ꂽ�w���B�́A����
�A�����ւ̊S�����܂��Ă��邱�Ƃ�����A�M�S�Ƀ��������p���� ��ꂽ�B �@
�@
�@ �@ ����21�i2009�j�N�x
�v���Ďs���T��w���A�g�ɂ��s�����J�u�����J�u �@
�{�Z�ł́A�A�g���Ă���s���T�̑�w���Ƌ��ɁA�u�v���Ă̖������l����v���e�[�}�Ɏs�������̌��J�u����
�P�O��
�R������J�u���Ă���A�{�Z����͈�ʕ��Ȃ̒����������u�t�Ƃ��ĂP�O���R�P���Ɂu�v���Ă��Y�|�e�g���E�����ގ�
�ƕč��������n�l�v�Ƃ�����ڂōu�`���s�����B �@
�u�`�ł́A�����J��ɕč��֓n��A�W���K�C���̍k��ɂ����ŕx��z���������ގ��ɂ��āA�v���Ďs�ݏZ �����̎ʐ^��A�f���������Ȃ���A�ގ����ڏZ���������̕č�����ɂ��Đ������s�����B �@�u�`�ɖK�ꂽ��u�҂́A�ݕē��{�l��̏����Ƃ��āA�����𓊂������Ĕr�����ɐs�͂����A�v���Ďs���Y�� �ږ��̃��[�_�[�Ɏv����y���Ă����B �@ �@ �@
�@ ����21�i2009�j�N�x
�w�Z������E���w����J�Ái�P�j
�@�{�Z�ł́A�w�Z������E���w����P�O���P�V���ɊJ�Â��A���w����]���鑽���̒��w���Ƃ��̕ی�҂��{�Z��K�ꂽ�B
�@������͍Z���̈��A�̌�A�{�Z�̊T�v�╽���Q�Q�N�x�̓��w�����ɂ��Ă̐���������A�I����ɂ͕s����^���
�����钆�w����ی�҂ɑ��āA�����ł��{�Z�̎��ɂ��ė������Ă��炨���ƌʖʒk���s��ꂽ�B
���������s��ꂽ���w��ł́A�e�w�Ȏ������̐ݔ���W�����������J����A�܂��̈�قł͑S���{��s���{�b�g�R��
�e�X�g�œ��܂�����s�@�̃f����s���s����ȂǁA�Q���������w���͍ݍZ���⋳���̐����ɖڂ��P�����Ȃ���M�S��
�������������B �@
�@
�@ ����21�i2009�j�N�x
�w�Z������E���w����ʊ��@�y��s���{�b�g�R���e�X�g�o���s�@�f���t���C�g�z�i�Q�j �@ �@��T��S���{�w��������s���{�b�g�R���e�X�g�ɂ����Č����x�X�g�f�U�C���܂���܂����A�����������ƂЂ�������̃f��
�t���C�g���A�w�Z��������ɑ̈�قōs��ꂽ�B
�@�O�X���ɂ́A�����{�V���Ђ����ނɖK��A�����̐V���Ɍf�ڂ��ꂽ���Ƃ�����A�w�Z������ɎQ���������w���ȊO
�̌��w�҂������K��Ă����B
�@�f���t���C�g�͎��ۂɃR���e�X�g�ōs�����Q�[�g�ʉ߁E�R�b�Ԃ̎������s�̂ق��A�W�̎���s�����s���A�Ō�Ɋ����H
���Y��ɒ�������ƁA���w�҂���傫�Ȕ��肪������ȂǁA�����̂����ɖ�������B �@ �@�����{�V���̌f�ڋL�����������iPDF�F216KB�j�y�L���f�ڗ����ρz �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x ��U��Y�w�������Z�~�i�[�J�� �@ �@�{�Z�ł́A�����P�X�N�x�ɑI�肳�ꂽ����I����j�[�Y��g�x���v���O�����i����f�o�j�u�Y�w���A�g���������ɂ��
���H�I�Z�p�҈琬�v�̈�Ƃ��āA��U��Y�w�������Z�~�i�[���P�O���X���ɊJ�Â����B
�@����́u�Ñ�l���͌��`�X�y�C���Ɠ��{�����l�Êw�҂̒���`�v�Ƒ肵�A�C�M���X�̓L���O�Y�E�J���b�W�E�����h������ �G�X�e�B�o���X�@�A���f�R�A�@�I�^�������������u�o�X�N�n���ɂ����铺�Ί펞��Z���̌Ñ�c�m�`�����v�y�сA��B��w �������������ٓ��ʌ������@�M�����q������u�Ðl�������Ɋ�Â���j�Љ���`�ꕶ�Љ��ΏۂƂ��ā`�v�� �����e�[�}�ŌÑ�l�̐����K����Љ���A�e���W�y�яW�c�W����l���̂c�m�`��p���ĉ𖾂��錤���ɂ���
�u�����s��ꂽ�B
�@���i�A����ł͂��܂�G��邱�Ƃ��Ȃ��u�l�Êw�v�Ƃ�������̍u���ɁA�Q�������w���E���E���́A�����[����ŕ���
���������B �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x
�e�}�Z�N �|���e�N�j�N�̊w�����{�Z��K��
�@��B�E����n��̂P�O����́A�V���K�|�[���̍H�Ȍn��������@�ւ̂R�Z�ƌ𗬋����������Ă���A����A���̒�
�̂P�Z�ł���e�}�Z�N �|���e�N�j�N�Z�̊w���S�S���Ƌ����Q�����A�k����B�ւ̏C�w���s���A�w�Z�Ԍ𗬂̈�Ƃ���
�P�O���V���ɖ{�Z��K�₵���B
�@�Z���̊w�Z�Љ�̌�A�e�}�Z�N�@�|���e�N�j�N�Z�̊w�����Q�̃O���[�v�ɕ����Ċw���̎{�݂���Ƃ����w���A�܂�
�Q�����ڂɂ͐�����H�w�Ȃ̉p��̎��ƂɎQ������ȂǁA�{�Z�̊w���B�ƌ𗬂�[�߂��B
����ꂽ�؍ݎ��Ԃł��������A�w�����m�͂����ɑł����������A���H��ɂ͂��݂��̃��[���A�h���X������������A�� �^�B�e�ɉ�����ȂǁC�L�Ӌ`�Ȏ��Ԃ��߂����ƂƂ��ɁA�M�d�ȑ̌��邱�Ƃ��ł����悤�ł������B �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x
��T��S���{�w��������s���{�b�g�R���e�X�g�x�X�g�f�U�C����� �@
�@�X���P�X���E�Q�O���̂Q���ԁA�������b�Z���ۓW����ŊJ�Â��ꂽ��T��S���{�w��������s���{�b�g�R���e�X�g�ɂ����āA �{�Z�@�B�H�w�ȃ`�[�����ē��D��`�[�����Q�����A�@�B�H�w�ȃ`�[����
��s���Z�łT�ʂɓ��܂��A�����x�X�g�f�U�C��
�܂���܂����B
�@���̃R���e�X�g�́i�Ёj���{�q��F���w���Â��A��w���ɂ�����q��H�w����̐��i�̂��߂ɁA�����ʼn��u���c
�\�ȍq��@��v�E���삵�A��s�������w���̂��ߊJ�Â���Ă�����̂ŁA�x�X�g�f�U�C���܂͍ł��D�ꂽ�@�̂�v
���A���ۂɈ��肵����s���s�����`�[���ɑ�������̂ł���B
�@�����͑�w�E���ꓙ�S�W�`�[�����Q�����A�����P�V�`�[�������\�I�ʉ߂ł��Ȃ����A�R�N���ȉ��̉������𒆐S�Ƃ���
�ē��D��`�[�����A�Q���`�[���̑命������w���̒��Ō������A�\�I��ʉ߂��ĂP�S�ʂ̐��т��c�����Ƃ��ł��A���N��
�����čX�Ȃ���𐾂��Ă����B �@ �\�I�ʉ߂ƌ��������A�ē��D��`�[���̂Ђ������ �@�B�H�w�ȃ`�[�����ē��D��`�[���̃����o �[�ƌږ�̐搶�� ��w�E���ꓙ�S�W�`�[�����Q���A�{�Z�͏��o�� �T�ʂɓ��܂��A�����ăx�X�g�f�U�C���܂��l�������@�@�B�H�w�ȃ`�[�� �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x
�O���]���ψ�����J��
�@�{�Z�ł́A����A�������Ɋւ����ȓ_���E�]�����s���A�w�O�̗L���҂ɋq�ϓI�Ɍ����������A����A�������̉��P
�Ɏ����邽�ߕ]����ړI�ŁA����X���P�V���i�j�O���]���ψ�����J�Â����B �@��c�ɂ́A��B��w��w�@�������H�w�����@���A�v���čH�Ƒ�w���A�v���Ďs���s���A�v���Ďs���w�Z����
�
�y�ђn���Ɠ�����̈ψ������ĂV���̗L���҂������A�{�Z����́A�Z���A�S�厖�A�e�w�Ȓ����Q�Q�����o�Ȃ����B �@�ψ�����Z���̈��A�Ɏn�܂�A�����厖����u�{�Z�̋���̌���Ɖ��P�����ɂ��āv�A�e�w�Ȓ�������uJABEE��
��v���O�����̊T�v��PDCA�T�C�N���̎���ɂ��āv�y�сu�Y�w���A�g�̊����ɂ��āv���ꂼ������̌�A��B
��w��w�@�������H�w�����@���̋c���i�s�ɂ��A�����Ɉӌ������A����ꂽ�B �@�Ō�ɍZ������A�����ʂ���̋M�d�Ȉӌ��ɑ��A����̊w�Z�^�c�Ɋ������Ă��������Ǝӎ����q�ׂ��A����B �@ �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x
�v���Ēn��S�����H�Z�p�Ґl�ވ琬�u�������{
�@�{�Z�ł́A�������H�ƋZ�p�Z���^�[�y�ч��v���ă��T�[�`�E�p�[�N�ƂƂ��Ɍo�ώY�ƏȂ̢�����Q�P�N�x�l�ޗ{����
�x�����ƣ��������A�u�v���Ēn��S�����H�Z�p�Ґl�ވ琬�u���v���X���S�����J�u���Ă���A���̂��і{�Z�ɂ�����
���K�R�[�X�Ƃ��Ė{�Z���L����ݔ���m�E�n�E�����p���āA�S���Z�p�̑S�ʂɂ킽����H�I�m�����K������ƂƂ��ɁA
����Ŏ�̂ƂȂ��ĉۑ������}�邱�Ƃ̋Z�p�̏K����ڎw���u�������{�����B �@���݁A�������ł̓S�����H�Z�p�҂̐l�ވ琬��ʂ�
�A�u�k����B�����ԂP�T�O���䐶�Y���_���i�\�z�v�̎����Ɏ��
�g��ł���A�{�u���ɂ��t�����l�̍����S�����i�̐��Y�ɑΉ��ł���l�ނ��琬���邱�ƂŁA�����Ԋ֘A�Y�Ƃւ�
�Q�����𑣂������Ƃ��Ă���B �@�Ȃ��A�n���S���֘A������Ƃ̎��Z�p�҂P�O���̎�u���͂P�O���P�U���܂ŁA�y�E���j�ɃS���Z�p�̏K���ɗ�ޗ\��B �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x
���Ȏ����E���Z�u�K��ɍu�t��h��
�@
�{�Z�ł́A�v���Ďs�Ƃ̊ԂŒ����������Ƌ��͂Ɋւ��鋦��Ɋ�Â������̈�Ƃ��āA�W���Q�V���A���Ȏ����E���Z
�u�K��Ɉ�ʗ��Ȃ̉z�n�y�������u�t�Ƃ��Ĕh�������B
�@
���u�K��͋v���Ďs���ȋ���Z���^�[����Â��A�w�K�w���v�̉����ɔ������w�Z���ȂɐV�K�ɓ������ꂽ���e��
�e�[�}�Ƃ��āA�s���̏��w�Z������ΏۂɎ��Z�w�����s�����̂ŁA�z�n�y�����͑�U�w�N�ɉ�������u�d�C�̗��p�Ɠ�
���v�Ɋւ��āA�w���̃|�C���g����S��̗��ӓ_���܂ރm�E�n�E�ɂ��Ď����������Ȃ���w�����s���A�Q���������w�Z
�����͔M�S�ɍu�`�Ɏ����X����Ƌ��Ɏ����ۑ�Ɏ��g��ł����B �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x
��S�Q���B�E����n�捂��p��٘_�����J��
�@��S�Q���B�E����n�捑���������w�Z�p��٘_����{�Z�����ԍZ�ƂȂ�A�W���Q�W���ɊJ�Â����B �@���͈��u�ƃX�s�[�`�̂Q����ōs���A��B�E����n�捂��̑�\�Q�P�����M�ق��J��L�����B �@���ʂ͎��̂Ƃ����
�A�X�s�[�`����ɂ����āA�{�Z�̓��䗺���N�i�������p���w�ȂT�N�j�������R�ʂɓ��܂����B �@�܂��A�X�s�[�`����̏�ʂQ���͗��N�P���ɍs�����R��S���������w�Z�p��v���[���e�[�V�����R���e�X�g�� �o�ꂷ��B �@
���u����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�P�ʁ@��{�@�@ ���i���㍂��j�@�@�@ �Q�ʁ@����@�����i�k��B����j�@�@�R�ʁ@�����X�@���i����������j
�@ �@�X�s�[�`����@�@�@�@�@�@ �@�@�P�ʁ@�R���@�F���i�����ۍ���j�@
�@�Q�ʁ@�⌳�����݁i����������j�@�@�R�ʁ@����@�����i�v���č���j
�@�@���ʏ܁@�������@�����i�s�鍂��j �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x
�w���E�Љ�l�����̂R�c�]�b�`�c���J�u�����J��
�@�{�Z�ł́A�w���E�Љ�l�����̂R�c�]�b�`�c���J�u�����W���Q�U���ɊJ�Â����B �@���̍u���́A���N�łS��ڂ��}���A����́u�R�c�]�b�`�c�����E���p�R�[�X�v�Ƒ肵�āA�w���E�Љ�l��
�R�c�]�b�`�c���S�҂��� ��ƂŊ��p���Ă�������o���҂܂ŕ��L����u�ґw�ŁA��W������R�P�����Q�������B �@�u�`�ł́A�R�c�]�b�`�c�̑�\�I�ȃf�W�^���E�G���W�j�A�����O�\�t�g�ł��颃\���b�h�E���[�N�X��̑���ƁA���̊��p���@�� �����邱�Ƃ�����ɓ���A�R�c���f���̍쐬����A���`�F�b�N�A����V���~���[�V�������A��A�̊�{����ƁA�R�c���f���� �̒��ڐ��@�L����Q�c����}�̍쐬�A�b�`�d�\����͓��A�����ʓI�ɂR�c�]�b�`�c���g�����Ȃ����߂̉��p������K������ ���Ƃ�ړI�Ƃ��A��u�҂͊w���s�`�̕⏕���Ȃ���A�M�S�ɉۑ�Ɏ��g��ł����B �@ �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x
��B����n�捑�����ꎖ���n�E�����C���J��
�@�����Q�P�N�x��B����n�捑���������w�Z�����n�E�����C���A�{�Z�����ԍZ�Ƃ��āA�W���Q�S���E�Q�T���ɊJ�Â����B
�@
�{���C�́A��B����n��P�O����̌W���A��C�y�ђ����W����ΏۂɁA�E���̐��s�ɕK�v�Ȓm���Ƌ��{��[�߁A���
�������s�����ƂŁA�Ɩ��\�͂̌����}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ������́B
�@���C�ł́A�S���Ɩ��ʉ�c�A�S�̉�c�ɉ����A����@�\�����ہ@�R���ے��⍲�ɂ��u��������̌���ɂ��āv�A
�{�Z�̟�����u�t�ɂ��u���s�w�E�댯�w�Љ�i���ꋳ��ł̈��S�ӎ��琬�Ɂj�v�̂Q�̓��ʍu�����s���A�Q��
�҂͔M�S�Ɏ����X���Ă����B
�@�܂��A���C�Q���ڂɂ͋v��������В����H������w���A��Ƃ̈��S�Ǘ��̐����ɂ��Đ������A���C���ʂ�
���m���Ȃ��̂Ƃ����B �@ �@
����21�i2009�j�N�x ����GP�v���O�����@��R��C���e�O�����Z�~�i�[���J�� �@ �@�{�Z�ł́A�����Q�O�N�x�ɑI�肳�ꂽ���̍�����w���琄�i�v���O�����i����f�o�j�u�b�h�l�r�����p�����@�B�v�f����� �Y�w�A�g�v�̈�Ƃ��āA��R��C���e�O�����Z�~�i�[���W���Q�T���ɊJ�Â����B �@����́u�R�c�|�b�`�c�̊��p�Ɍ����āv�Ƃ����e�[�}�ŁA�{�Z�̜A���������_�����ɂ��u�@�B���}�ƂR�����b�`�c�v���n�߁A �����ĂS�̍u�����s���A�R�����b�`�c�̓����ɂ����鐻�}����̕ω��A�x���_�[��Ƃɂ��ŐV�̃f�W�^���G���W�j �A�����O�\�t�g�̓����A�܂���Ƃ��R�����b�`�c��b�`�d�̓����ɂ������Ƃɂ��A�v�E�����̃v���Z�X�ɂǂ̂悤�Ȍ��ʂ� ����Ă��邩�̊��p����Ȃǂɂ��ču�����s��ꂽ�B �@�u�������w���B�ɂƂ��ẮA���Ƃōs���Ă���R�����b�`�c�̉��K���A���ۂɊ�Ƃ̐�������
�Ŋ��p����
�A�v�� �������E���Y�R�X�g�̍팸��i������Ȃǂɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă��邱�Ƃ�m�邱�Ƃ��ł���悢�@��ƂȂ����B �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x ���w�������̌��Z�~�i�[���J�� �@ �@�W���P�W���ƂP�X���A�{�Z�ł͒��w����ΏۂɎ��ۂɍ���̎��Ƃ�̌����Ă��炤�̌��Z�~�i�[���J�Â��A����ԂłT�U�S�� �̒��w�����Q�������B �@����łT�̐��w�ȋy�ш�ʉȖڂ̎��Ƃ�̌��w�K���A���x�݂ɂ͖{�Z�w���ɂ�鍂��Ղ̐������s��ꂽ�B�Q�� �������w������́u�������ʔ��������v�A�u�e�w�Ȃ̋�̓I�ȓ��e�����������v�A�u�w�ȑI�т̎Q�l�ɂȂ����v�Ȃǂ̊��z�� �����ꂽ�B �@�Z�~�i�[�J�Ò��A�Z���ɍ���ɂ��Ă̎���R�[�i�[���݂����A�����̕ی�҂��獂��ɂ��Ă̎��₪��ꂽ�B �@ �@ �@ ����21�i2009�j�N�x
���w�������̌��J�u�����J��
�@�{�Z�ł́A���w�������̌��J�u���u���Ȃ�������T�C�G���e�B�X�g�v���V���R�O���A�R�P���̂Q���Ԃɂ킽��J�Â����B
�@���u���ɂ́A�v���Ďs���y�ыߍx�̒��w�P�A�Q�N���P�S�����Q�����A�����R�[�X�u�G�R���W�[���W�I�i�d�r�̂���Ȃ����W
�I�j������Ă݂悤�v�Ɛ��w�R�[�X�u�̌��I���w�����_�[�����h�v�̂Q�̃R�[�X�����ꂼ��P�����̌������B
�@�Q���������w���B�́A���i�͂��܂�g�����ƂȂ��H�����Ɉ���ꓬ���Ȃ�����A�d�r���g�p���Ȃ��G�R���W�[���W�I��
�����������A�Ñ�̐l�����̌v�Z���@��Ђ����g���Ă̌��іڂ̐��w��̌�����ȂǁA�Q���Ԃ�ʂ��ė��ȁE���w�ւ�
�����E�S�����߂�ƂƂ��ɁA���{�R���̐��쎺����K�H������w����ȂNjv���č���ł̑̌����y����ł����B �@ �����S�������̎w���ɂ�钆�w���̃G�R���W�[���W�I�̐��앗�i ���w�S�������ɂ��u�`���i �n�z�����厖�ɂ��C���؏��̎��^ �@
�@ ����21�i2009�j�N�x
�v���čL�揤�k��ɎY�w�A�g�R�[�i�[��ݒu �@ �@�{�Z�ł́A�V���Q�W���A�v���Ďs��n�����Z�@�ւł���k����B�n��r�W�l�X�}�b�`���O���c���Â���u�v���� �L�揤�k��v�ɂ����ĎY�w�A�g�R�[�i�[��ݒu���A�n��������Ƃɑ��āA�����V�[�Y�̐�����Z�p���k�Ȃǂ��s�����B �@���̏��k��͍��N�łS��ڂ��}���A�n��������Ƃ���胁�[�J�[����̎��i��}�邽�߂ɍs���Ă���A������ �s���ɂ������A�n����ƂP�R�R�Ђ��Q�������B �@�Y�w�A�g�R�[�i�[�ɂ́A�n�����Z�@�ւ̗v�����A�{�Z�̂ق��A�����w�A�����w�����Q�����Ă���A�u�[�X�� �K�ꂽ�n���̒�����ƊW�҂ɑ��A�Z�p���k��{�Z�����L���Ă�������ɂ��āA�f�������p�l�����������M�S�� �������s�����B �@ ��ƊW�҂ɑ��Đ������s�����c�Y�w���A�g���i�Z���^�[�� �v���čL�揤�k��̉�ꕗ�i �@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@�{�Z�w�����ł́A�����ɑ��錒�N�Ǘ��̈�Ƃ��ăw���X�`�F�b�N���A�T���P�Q���Ɏ��{���܂����B
�@
�@
�@�����Q�R�N�x���w�����S���U���ɁA�����{��k�ЂŔ�Ђ������k�n���̍���ւ̓��w�\��ł��������w������
�@
�@
�@�{�Z�ł́A�R���Q�R���ɊO�������l�����i�̈�Ƃ��āA�Q���P�S��������̎n�܂����`�|�r�s�d�o�ɂ��Ă̕�W��
�@
�@
�@�{�Z�ł́A�R���Q�T���Ɋ��@�������������a��ٌ�m���u�t�ɏ����A���E����Ώۂɑ�R��e�c��c�u�L�����p
�@
�@
�@�v���Ďs��������j�����قɂ����āA�R���P�Q������u�Ȃ����̕��i�E�}��̋O���v�Ƒ肵�����W���J�Â���Ă�
�@
�@
�@�{�Z�ł́A������\�N�x�Ɏ��̍�����w���琄�i�v���O�����i����f�o�j�ɍ̑����ꂽ�u�b�h�l�r�����p�����@�B�v�f
�@
�@
�@��S�U��{�ȑ��Ǝ��A��P�V���U�ȏC�������R���P�W���ɖ{�Z���̈�قɂ����ċ��s���܂����B���k�n�������m
�@
�@
�@�{�Z�ł́A�{�Z�d�C�d�q�H�w�Ȃ̂R�A�S�N����ΏۂƂ��A�u����E���_��u�d�C�E�G�l���M�[����Ŋ��鍂�ꑲ
�w������p�l���[�ւ̎���̖͗l
�u�t�̒������y�����Ɖ��c������
�@
�@
�@�Q���Q�S���ɁA���X��Z�� �܂��Â���^�c���c�� �ߓ�������A���X��Z�� ���N�琬���c�� ���c�F�K��A
�@
�@
�@�{�Z�ł́A�����Q�O�N�x�ɍ̑����ꂽ���̍�����w���琄�i�v���O�����i����f�o�j�ɂ���g�ł���u�b�h�l�r�����p
�@
�@
�@�{�Z�ł́A����Q���P�O���A�i�Ɓj��������@�\����]�Z�ȑ�A���X�[�p�[�n��Y�w�A�g�{���̐����ď������R�[�f
�@
�@
�@�{�Z�ł́A����P���Q�W���A�s���̑�w�E���ꓙ�ɂ�錤���J���ɂ���Đ��ݏo���ꂽ���ʂ�n���Ƃ̃j�[�Y�Ƀ}
�@
�@
�@����P���Q�T���̌ߑO�A�����}�C�X�^�[���Z����Z���ȂNj����P�W���y�ъ؍��e�N�m�}�[�g�������{�Z��K��܂����B
�����}�C�X�^�[���Z�K��c�Ƃ̏W���ʐ^
�\�E����w�Z���猤�C�@�E�Ƌ���ے��K��c�Ƃ̏W���ʐ^
�@
�@
�@�����Ȋw�ȋy�э����t�H�[�������i�����ǎ�Â̕����Q�Q�N�x��w������v�v���O���������t�H�[�������A����P
�@
�@
�@�{�Z�ł́A�����Q�O�N�x�ɑI�肳�ꂽ���̍�����w���琄�i�v���O�����i����f�o�j�u�b�h�l�r�����p�����@�B�v�f����
�@
�@
�@�{�Z�ł́A�P�P���R�O���i�j�ɋ��E����ΏۂƂ��A�{�Z�Z��ł���v���đ�w��w�����_�_�o�Ȃ̈��������t
�@
�@
�@�{�Z���܂ދv���Ďs���T�̍�������@�ւɂ��\�������u��������R���\�[�V�A���v���āv�̋��_�ƂȂ�T�e��
�@
�@
�@�{�Z�ł͂P�P���P�S���A�s�̐��U�w�K�̋��_�ł���u���[��s�A�v���āv�ɂ����āA�v���Ďs������Â��A���N�J�Â�
�@
�@
�@�{�Z�ł́A�w�Z������E���w����P�P���P�R���ɊJ�Â��A���w����]���鑽���̒��w���Ƃ��̕ی�҂����Z��K���
�@
�@
�@�{�Z�ł́A�S�����i�������Ƃ�������c�̂ł���A���{�S���H�Ɖ�̒�����ƈψ�������̕�����A����
�@
�@
�@�{�Z�w�����ł́A�����ɑ��錒�N�Ǘ��̈�Ƃ��ăw���X�`�F�b�N���A����P�P���Q���Ɏ��{���܂����B
�@
�@
�@����P�O���Q�Q���ɁA���j�����ƂŁA�{�Z�@�B�H�w�ȑ�P�Q�����Ɛ��i���a�T�Q�N�R�����Ɓj�ł�����������Y�����{
�@
�@
�@�{�Z�ł́A�v���Ďs���̂T��w���Ƃ̊ԂŒ������Ă���P�ʌ݊�����̈�Ƃ��āA�e��w���̌�����F��
�@
�@
�@�A�C�f�A�Ό��E�S���������w�Z���{�b�g�R���e�X�g2010��B����n����A����P�O���P�V���ɋv���Ďs�݂Âܑ�
�@
�@
�@��B�E����n�捑������@�V�Z�p�}�b�`���O�t�F�A���A�P�O���P�T���Ƀ��m�Â���t�F�A�Q�O�P�O�i�}�������b�Z�����j�ɂĊJ
�@
�@
�@��B�E����n��̂X����́A�V���K�|�[���̍H�Ȍn��������@�ւ̂R�Z�ƌ𗬋����������Ă���A����A���̒���
�@
�@
�@�v���Ďs�Z�c�咬�̕������Ǝ{�݁u����߂肠�Z�c��v������P�O���Q���ɃO�����h�I�[�v�����܂����B�v���Ďs���T
�@
�@����X���Q�Q���ɁA�@�B�H�w�Ȃ̑�P�����Ɛ��i���a�S�P�N�R�����Ɓj���{�Z��K��܂����B
�@���Ɛ��̒��ɂ́A���ƈȗ��S�S�N�Ԃ�ɗ��Z���ꂽ��������A�w���̕ς��悤�ɋ����ƂƂ��ɁA�{�Z�̔��W������
�@
�@
�@�����n��R����̘A�g���ƂƂ��āA�����n��R���ꎖ���E���i�W�����j���C��A�{�Z�łX���P�R���ɊJ�Â���܂�
�@
�@����X���P�R�A�P�S���̂Q���ԂɁA�v���Ďs��A�n�����Z�@�ւō��k����B�r�W�l�X�}�b�`���O���c���Â���
�@���̏��k��͒n�ꒆ����Ƃ̎@��̊m�ۂ�n��Y�Ƃ̊�������}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A���N�łT��ڂ��}���A
�@
�@�{�Z�ł́A����W���P�W���ƂP�X���ɁA�����ʂ��Ė{�Z�̂T�w�ȋy�ш�ʉȖڂ̎��Ƃ�̌����Ă��炤���Ƃ�ړI��
�������s���A�Z���ɐ݂���ꂽ����R�[�i�[�ɂ́A�ی�҂⒆�w�Z�̐搶����{�Z�ɂ��Ă̎��₪������
�@
�@�{�Z�ł́A�{�Z���܂ދv���Ďs���T�̍�������@�ւɂ��\������u��������R���\�[�V�A���v���Ƃ̈�Ƃ��āA
�@�u���ɂ͎s���̒��w�Z�����R�W�����Q�����A��B��w�A�C�\�g�[�v�����Z���^�[�̐��������Ƌv���đ�w�̓y����
�@�W���U���ɊJ����������߂肠�Z�c��T�e���C�g�E�L�����p�X�ɂ����āA�W���V���A�W���̗����A�I�[�v�j���O�C�x���g��
�̓c����y�����ɂ������u���炭��V�E�q��̏��C�@�֎ԁv���J�Â���܂����B
�@
�@�{�Z���܂ގs���T�̍�������@�ցi�{�Z�̂ق��A�v���đ�E�v���čH�Ƒ�E���}���A�w�@��E�v���ĐM�����w�@
�������ƃr���u����߂肠�Z�c��v�U�K�ɃI�[�v�����A�J�������s���܂����B
�@
�@�{�Z�ł́A��B��w�������j�l�ށi�R�A�E���[�_�[�j�琬�v���O�����u���Ԑ����R�[�X�v�J���L�������̈�ł��鎕
�m�E�n�E���K�����A����ɐ�[�Z�p�Ƃ̗Z�������ʂ����Ԑv�Z�p�҂̈琬��ڎw�����̂ŁA���K�ɂ͎Љ�l�T�P��
�@
�@�{�Z�ł́A���w�������̌��J�u���u�G���N�g���j�N�X�T�}�[�X�N�[���v���W���R���A�S���̂Q���Ԃɂ킽��J�Â��܂����B
�@
�@�{�Z�ł́A���w�������̌��J�u���u���Ȃ�������T�C�G���e�B�X�g�v���V���Q�X���A�R�O���̂Q���Ԃɂ킽��J�Â��܂�
���W�I�j������Ă݂悤�v�Ɛ��w�R�[�X�u�̌��I���w�����_�[�����h�v�̂Q�̃R�[�X�����ꂼ��P�����̌����܂����B
�@
�@�{�Z�ł́A��V��R�c�|�b�`�c���J�u���`�R�c�|�b�`�c���p�Ɋւ����b�u�K��`���V���Q�R���ɊJ�Â��܂����B
���Q�����܂����B
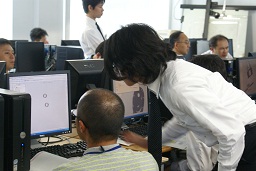
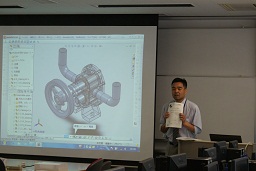

�@
�@�{�Z�ł́A�����Q�O�N�x�ɑI�肳�ꂽ���̍�����w���琄�i�v���O�����i����f�o�j�u�b�h�l�r�����p�����@�B�v�f����
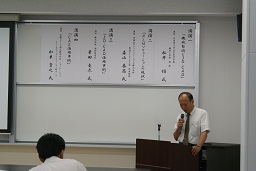

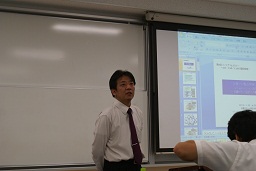
�@
�@�{�Z�ł́A�S�N���y�ѐ�U�ȂP�N����Ώۂɂ����A�E�����Z�~�i�[���V���P�T���ɊJ�Â��܂����B



�@
�@
�@����Z�p���E���͔����̕��~�H�Ƃ��āA���^�Z�p�̐v�E�����E���^�ۑS�ɗD�ꂽ�Z�p��m���������A���^����
�@���K�̎��Ƃ����Ă��A�w���B�ɑ������̋Z�p��ɂ��݂Ȃ��`���Ă���A��c�Z���Ƃ̍��k�ł́u�m���ȋZ�p�E�Z�\��
�@
�@�{�Z�ł́A�T���P�X������Q�P���ɂ����ă}�������b�Z�����ōs��ꂽ�����{�H�i�Y�Ƒn���W�f�P�O�̐����{�@�\���H
�@���уp���͈����������Ă��������̂悢���тƕۑ����ɗD�ꂽ�p����g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ���Ă��ꂼ��̒Z�����
�@
�@
�@
�@�{�Z�ł́A����T���P�X���ɋv���Ďs���h��������̌��A�k�x�T���̒n�k�ɂ��Д�����z�肵���h�Д��P��
�@
�@�{�Z�ł́A����S���Q�W���A�E�F�[�u�z�[���ɂ����ĐV���w���Ƃ̍��k����J�Â��܂����B
�@
�@
�@�{�Z�ł́A���N�x���w�̂P�N����ΏۂƂ������h���C���S���Q�R���E�Q�S���̂Q���Ԃɓn��A������{�������N���R
�@���C�́A��c�Z���ɂ��u�b�A�x�@���ɂ���ʈ��S�u�K��Ɏn�܂�A�I���G���e�[�����O��㋉���ɂ��w�ȏЉ�
�@
�@
�@�{�Z�ł́A �R���P�T���i���j�ɎY�w���A�g�e�N�m�Z���^�[�v�H���j���A �v�H�L�O���T���������E�n���ƁE����@�ցE�e��
�@���T�ł́A�O�c�Z���̈��A�̂��ƁA�v���Ďs���̏j���A���c�Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[������̏v�H�A�L�O�u��
�@���T�ɖK�ꂽ�n��̊�ƊW�҂���́A����̖{�Z�ɂ�����A�n��ɍ��������Z�p�x���A���������Ȃǂ̎Y�w���A�g
�@
�v�H�L�O���T�ƌ���GP���ʕ�̗l�q
�@
�@
�@
�@
�@�����̓R���T�[�g�J���O�ɁA�O�c�Z���ƃZ���^�[���߂铡�c�����ɂ�菜�������s���A�R���T�[�g�ɐ\���A
�@�R���T�[�g�ł́A�I�����_�̃n�[�O�������y�@�̌������ŁA�����[�g�E�̐��E���l�҂ł��鍲���L�F���Ƃ��̂�����
�@�R���T�[�g�ɖK�ꂽ��ʎs���⋳�E���́A���i�͂��܂蕷���@��̂Ȃ��A�Êy��̃t���[�g����[�g���t�ł��������
�v�H�L�O�g�[�N�R���T�[�g�̗l�q
�@
�@
�@
�@
�@�{�Z�ł́A�Q���S���A�v���Ďs���̑�w�E���ꓙ�ɂ�錤���J���ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�Z�p��n���Ƃ̃j�[�Y�ɍ���
�@���̔��\��͋v���Ďs���B�o�ώY�Ƌǂ���Â��A�{�Z����͐������p���w�Ȃ̋��؏y�������u�V�K�H�i���уp��
�@�܂��A�����Č������ʂ�W�������u�[�X���ݒu����A�u���уp���v�̃u�[�X�ł͎��H�R�[�i�[��݂��A�K�ꂽ�n���Ƃ�
���\���s�����؏y�����Ə��c����
�@
�@�{�Z�ł́A�����P�X�N�x�ɑI�肳�ꂽ����I����j�[�Y��g�x���v���O�����i����f�o�j�u�Y�w���A�g��������ɂ��
�@�ψ���ł́A�O�c�Z���̈��A�̂��ƁA�ψ����ł��錢�{�Y�ƋZ�p������������B�Z���^�[�����㗝���c���������
�@
�@�{�Z�ł́A�����Q�P�N�x�w�������l�����P���P�R���ɊJ�Â��A�ݗ����Ă���P�N�������U�Ȑ��܂ł̖�P�Q�O�����Q�����A
�@���ł́A�]�藾���厖���V���l�ւ̏j���ƋL�O�i�̑��悪�s��ꂽ���ƁA�V���l���\���A�d�C�d�q�H�w�ȂT�N��
�@
�@
�@
�@�{�Z�̊w�����k���ł́A���E����ΏۂƂ��Ĕ��B��Q�҂ւ̊ւ����Ƃ��̗�����[�߂邽�߂ɁA�v���đ�w��w��
�@
�@
�@
�@�{�Z�ł́A�����Q�O�N�x�ɑI�肳�ꂽ���̍�����w���琄�i�v���O�����i����f�o�j�u�b�h�l�r�����p�����@�B�v�f�����
�@
�@
�@�����Q�P�N�x�̕����Ȋw�ȁu��w����[���̂��߂̐헪�I��w�A�g�x���v���O�����v�ɍ̑����ꂽ�n�拤�n�̂��߂�
�@���ł́A��g��\�Z�ł�����藴�v�v���čH�Ƒ�w���̈��A�̌�A�v���Ďs�̗���̉��A�A�g�Z�ł���T�̍���
�@����͂��̃R���\�[�V�A�����u�m�v�̑n����̂ƈʒu�t���A��g�𐄐i���銈�����_�Ƃ��Ďs�����S���ɃT�e���C�g�L��
�@
�@
�@�P�Q���P�P������P�S���܂ŊJ�Â��ꂽ�u�������[�^�[�V���[�Q�O�O�X�v�������w������ԗ��W�ɂ����āA�{�Z�G�R�p���[
�@���̎ԗ��W�ɂ́A�������̑�w�E����̃G�R�����J�[�E�\�[���[�J�[�E�t�H�[�~�����Ȃǎԗ��W���W���B
�@NHK���������ǂ̎�ނ����G�R�p���[���D��̒��c�����N�N�i��U�ȂQ�N�j�́A�n�����g�����~�߂��悤��
�@
�@
�@���Ɠ��e�́A�q���B�ɒ����т��ޗ��������Ă��炤�Ƃ������̂ŁA���N�����u�t�Ɍ}���A�P�N�Ԃ�ʂ��Ēf���I��
�@�Ȃ��A�O�����v������܂����Q�l�́A���N�R���ɓ����ŊJ�����L�����p�X�x���`���[�O�����v���S�����ɏo�ꂷ��B
�@
�@�{�Z�ł́A�P�Q���P������P�Q���R���܂ł̂R���ԁA�Љ�l�����R�c�|�b�`�c�^�b�`�d���J�u�����J�Â����B
�@���̍u���́A����܂łS��s�����R�c�]�b�`�c���J�u���̉��p�҂ƂȂ��Ă���A��ƂŎ����Ɍg����Ă���Љ�l�P�U����
�@����̍u�`�ł́A����܂ł̃A���P�[�g�ŗv�]�����������@�B�H�w����ł̗��_�I�����u�`��������A�ޗ��͊w�A
�M�S�ɉۑ�Ɏ��g�ގ�u���B�̗l�q
�@
�@
�@
�@
�@
�@������ł́A���ԍZ�ł���O�c�Z���̈��A�̌�A �u�e�n��ł̕����Q�Q�N�x���w�ґI���w�͎����ɂ�����ǎ�����
�e����̍Z���ƌ�����̗l�q
�@
�@
�@
�@�Ȃ��A�D�������v���č���͗��N�P���S���ɐ_�ˎs�ŊJ�Â����u��S�O��S�����ꃉ�O�r�[�t�b�g�{�[�����v�ɋ�B
�D���������O�r�[���ƕ\�����̗l�q
�@
�@
�@
�@
���������͂��߁A�A�g�s���T��w���̍u�t�ɂ��ӌ������̗l�q
�@
�ӂꂠ�����H�w�W�ɂ�������J�����̗l�q
�@
���؏y�����Ɛ�������ɂ��u�`�̗l�q
�@
�s�����J�u���̗l�q
�u�`���s����������
�@
�O�c�Z���ɂ��w�Z�T�v����
�e�w�Ȓ��ɂ��ʖʒk�̗l�q
���w���ɑ��������s�������y����
�����{�V���Ђɂ���ނ̗l�q�i����j�Ɗw�Z������ɂ�����f���t���C�g�̗l�q
�@
�M�S�ɍu�����s���A�I�^�������ƏM�����q��
�@
�O�c�Z���ɂ��55����Ɩ{�Z�̐��� �L�O�i�̎��^����O�c�Z�� ���ƌ��w�̍ۂɎ��������A�e�}�Z�N�̊w��
�o���̊w�����������p��̎��� �p��̎��Ƃɂ�����𗬂̗l�q �e�}�Z�N�̊w���Ƌ��ɋL�O�B�e
�@
�@�̐R������A�@�B�H�w�ȃ`�[���̃���������
�@
�{�Z�ɂ��Ă̐������s���O�c�Z�� �c���i�s���s���A�{����B��w��w�@�����@���H�w�����@�� �O���]���ψ���̗l�q
�@
���K�w�����s���������Z�p�� �M�S�Ɏ��K�Ɏ��g�ގ�u�� ��u���ɑ��u�`���s���X����
�@
���w�Z�̋����ɑ��A���Z�������Ȃ���w�����s���z�n�y����
���̊J�Õ��i�@
�W�F�X�`���[�������ăX�s�[�`���s���w���B �@ �X�s�[�`����R�ʂ̓��䗺���N�Ɖp��b�� �Q���ґS���ł̋L�O�B�e
�@
�Ίۏy�����ɂ�鎕�ԃ|���v�̑g�ݗ��Ă̍u�`
�RD-CAD�u���̎�u���i
�����y�����ɂ�鎕�ԃ|���v���i�̃��f�����O�̍u�` ��u�҂���̎���ɑΉ�����w��TA
�R������@�\�����ە⍲�̍u�� ���㍂�`�搶�ɂ��u�� ��㎖�������ɂ��C���؏��̎��^
�@
�u���u�@�B���}�ƂR�����b�`�c�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�t�F�{�Z���_�����@�A��������
�u���u�b�`�d���p����v�i�R�c�]�b�`�c�^�b�`�d���p�ɂ��v�������j�u�t�F������Ё@�����쏊�@�@���c�B�
�u���u�R�����f�W�^�����̂Â���̌��݂ƍ���v�@�u�t�F�\���b�h���[�N�X�W���p���@�ԑ㐭�G�� �u���u�R�c�]�b�`�c���p����v�i�R�c�]�b�`�c�ɂ��Ɩ����P�j�@�u�t�F������Ё@�O���@�@�{�n�@�D��
�̌��Z�~�i�[�ɂ�������Ƃ̗l�q
�@
�@
����21�i2009�j�N�x
����f�o�v���O�����@��Q��b�h�l�r�t�H�[�������J��
�@
�@�{�Z�ł́A�����Q�O�N�x�ɑI�肳�ꂽ���̍�����w���琄�i�v���O�����i����f�o�j�u�b�h�l�r�����p�����@�B�v�f�����
�Y�w�A�g�v�̈�Ƃ��āA��Q��b�h�l�r�t�H�[�������V���Q�S���ɊJ�Â����B
�@����́A��B��w�H�w�����@�̍��͏y��������u��B��w�ɂ�����v���}����̌���v�y�юO�H�d�H�Ɗ������
���葢�D���̏��Y���H�암��������u�O�H�d�H�ƒ���̂��̂���ɂ�����f�W�^���Z�p�ɂ��āv�Ƃ����e�[�}�ŁA
��w�E��Ƃ̎��_���猩���v���}����݂̍����A�R�����b�`�c����g�����v���}�Z�p�ɂ��ču�����s��ꂽ�B
�@�܂��A���̌�̋v���āE�L���E�k��B�̕����R����̐v���}����S�������ɂ��p�l���f�B�X�J�b�V�����ł� �A�e��
��ɂ�����v���}����̌���⍡��̉ۑ�ɂ��āA���݂��Ɉӌ������킵�A��w�N���ɂ�����菑�����}����
�b����̑����A���w�N���ɂ����ĂR�����b�`�c��p�������K�ɂ��@�B�H�w�Ȗڂ̗���x�A���p�͂�[�߂邽�߂�
��g��ۑ�ɂ��Ċ����ȋc�_���s���A�Q�������w�����ƊW�҂ȂǔM�S�Ɏ����X�����B
�@
|
| |
| ���c�Y�w���A�g���i�Z���^�[���ɂ��f�o�v���O�������� | |
|
��B��w�@���͏y�����ɂ��u�� | |
|
�O�H�d�H�Ɓi���j���葢�D���@���Y�����ɂ��u�� | |
|
|
|
|
�@������ �@�@�����v���č���y�����E���ΗL�����ꋳ�� �@�@���]�k��B����y���� | |
|
�@ |
�@�@�v���āE�L���E�k��B�̕����R����ɂ��p�l���f�B�X�J�b�V���� |
�@
�@
�@