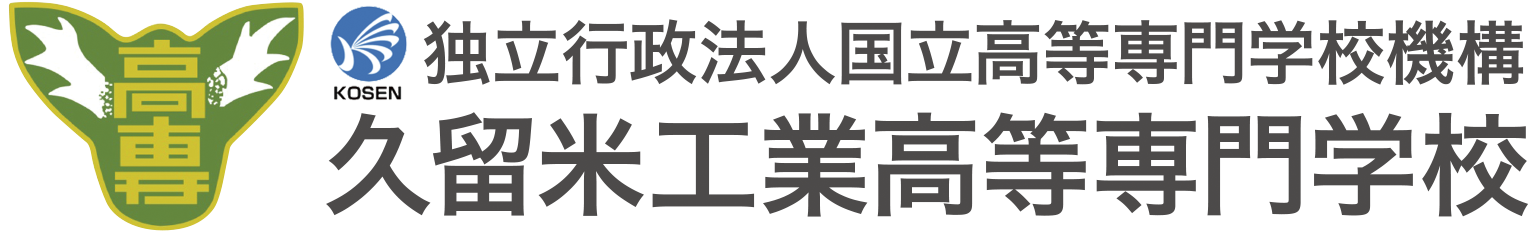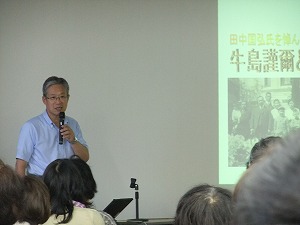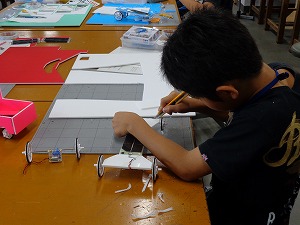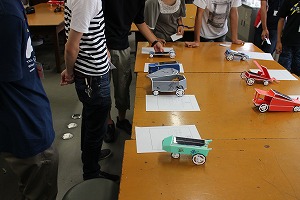去る9月7日(日)、久留米市主催の「ポテト王牛島謹爾生誕150年記念展」において、本校の中畑義明教授(一般科目文科系)が「牛島謹爾と日系移民」と題して、記念講演をくるめりあ六ツ門で行いました。
この記念展は久留米市出身の実業家で、アメリカにおいて「馬鈴薯王(ポテトキング)」と呼ばれ、在米日本人会の初代会長を務めた牛島謹爾の生誕150年を記念して、7月5日から9月23日まで、久留米市立六ツ門図書館展示コーナーで開催されています。
講演では、牛島謹爾の出生からアメリカで残した業績、謹爾が活躍した時代における日系移民の生活の様子を当時の写真を紹介しながら解説を行いました。
定員80人の会場はほぼ満席となり、記念講演は盛況のうちに終了しました。
講演を聴いた人たちからは「写真などが多用されており、当時の様子をイメージしやすかった」「説明がわかりやすかった」などの声が聞かれました。
講演する中畑教授