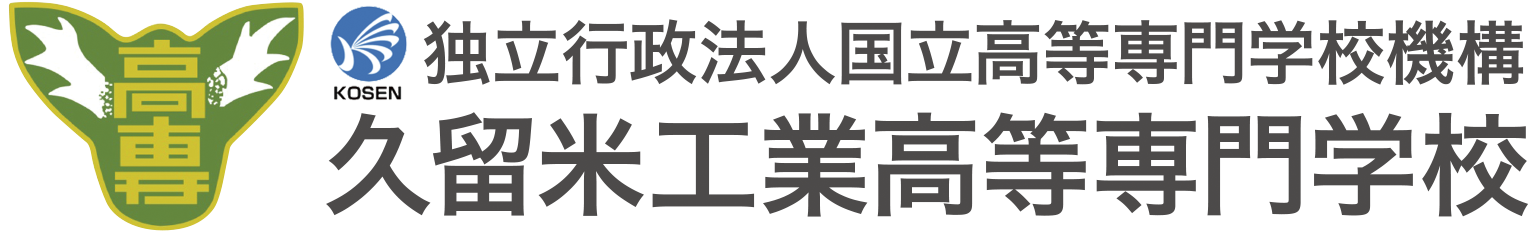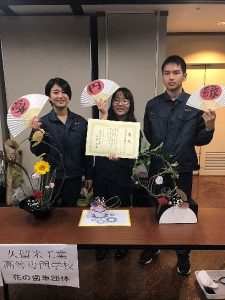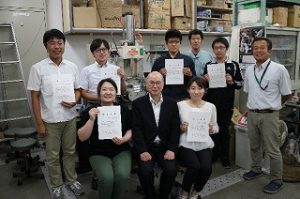平成30年9月19日(水)、主に係長を対象とするSD研修を地域連携多目的室にて実施しました。これは狭義の管理運営に加え、教育や研究の支援までの役割を含めた、事務組織の質の向上を図るための取り組みです。
三川校長から、冒頭の挨拶として財務上・人事上のコンプライアンスの大切さ、広報活動のあり方について訓示があった後は、寺田事務部長より、「新しい久留米高専を創造していくために」と題して、高専を取り巻く現状と課題の説明がありました。
津田総務課長からは公文書の作成方法等を改めて確認する講義があり、その後は、最近学外で開催された各種研修について、各係長・主任からのプレゼンテーションが続々と行われました。これにより他係・他高専・他大学の情報を共有することはもちろん、発表者にとってはプレゼンスキルを磨くよい機会になりました。
それぞれが久留米高専というチームの一員として意識改革・能力開発に励んでいくことを確認し、本校にとって初の取り組みである本研修は盛会のうちに終了となりました。参加者のアンケートでは、今後は一般職員も対象としてほしいという意見や、ワークを含めたプログラムにしてほしいという提案等前向きな感想が寄せられました。



<本件担当>
総務課人事・労務係
電話:0942-35-9305